東京校の講義レポート
平成26年 1/7(火)・1/8(水) 吉田松陰先生の故郷・萩「第5回 松下村塾合宿」1日目
2014/01/07 松下村塾合宿
コメント (0)
 ●合宿1日目…1月7日(火曜日)
●合宿1日目…1月7日(火曜日)12:00 松陰神社前集合
山口県萩、松陰神社に到着して感じたのは
世田谷の松陰神社と大きく違うことだ。
その大きさからは松下村塾誕生の地であるということの誇りと
萩にとって、松陰先生がいかに重要な存在かを感じることができる。
参拝に行く道中、さりげなく左手に松下村塾があった。
右手にある至誠館に注目していたため
危うく見逃すところだった。
それぐらいされげなくあり、またそれが松下村塾らしくて
本物を見ることができたことにとても感動した。
鳥居前の石碑には「明治維新胎動之地」とあり
「胎動」という言葉の表現がとても松下村塾のことを上手く表していて
感動して興奮した。
松陰神社内のお土産屋さんにあるうどん屋さんで
松陰だんご(330円、柚の香りがさわやか)を食べていると、
外に続々と各校の学生や
参加経営者の方々も集まってきた。
いよいよ萩研修が開始するのだという緊張感も高まった。
12:30 杉家幽囚室、松下村塾
改めて松下村塾を見ると
本当にこじんまりとしていた。
その場所に松陰先生が謹慎させられ
講義を行っていたと考えると
なんとなく緊張した。
裏手にある井戸も見たが
今元さんは「その井戸を見て何を感じるか」と学生に尋ねたとき
自分は特にぴんと来ていなかった。
しかし、今元さんがその井戸の石でできている部分を触りながら、
木は腐るから新しいものに変わるかもしれないが
この石はきっと当時からあったはず、
とお話しされたときにとても納得した。
現場に来た時に何が一番大切かというと
場所の距離感、そして観る、触れる、澄ます、嗅ぐ、なめる
やってみる、であるということが身に染みた。
13:00 歴史ウォーク
吉田稔麻呂生家跡、伊藤博文旧家跡を見る。
今までは塾生の中でも超メジャーな人物のことしかよくは知らず
他の塾生はあまり親近感ももてていなかったが、
今回、生家をめぐる中で松陰先生とのエピソードや
松陰先生死後の行動なども聴くことができ
今までより興味が沸いた。
それにしても歩いてみるとわかるが、本当に松下村塾から近いことがわかる。
伊藤博文は来原良蔵の紹介で入塾し
松陰先生からは人と人をつなぐのが得意なため
政治家に向いているとアドバイスをもらったそうだ。
松陰先生がいかに人を見る目があったかがよくわかる。
それだけでなく後の講義で聴くが伊藤博文は松陰先生から
「才能はないし、学もない。素直であるが花がない。
僕すこぶるこれを愛す」
という言葉を遺している。
この言葉だけでも暖かい愛情を感じ、
松陰先生がなぜ慕われるのかがよくわかった。
玉木文之進旧宅、団子岩と向かう。
玉木文之進旧宅は松下村塾発祥の地であり
杉家がかつてあった団子岩のところから
坂を下りてすぐのところにある。
かつて松陰先生が学び、生き方のルーツとなった場所である。
団子岩のところには杉家の間取りを見ることができ
10人近く住んでいた場所と思えないその狭さに驚いた。
その狭さや父と農業をして過ごした日々は
きっと家族のきずなを強くしたのだろう。
そしてこの場所から見える指月山と萩の城を見て
公に仕える志を育てていったのだろう。
そう考えるとこの場所が松陰先生の精神的なルーツでもあるのだと感じ
印象強い景色は目に焼き付いた。
今回の萩合宿では松陰先生の家族のつながりを
知ることができたと感じる。
産湯の井戸に触り、指月山を背に集合写真を撮り
松陰先生や萩出身の名だたる方々のお墓をお参りし
松陰先生と金子重之助の銅像前で写真を撮った。
この場所は春は桜がきれいだそうだ。
次は来るときは春に行こう。
14:30 「至誠館」見学
松陰神社に戻り至誠館を観る。
ここには本物の留魂録がある。
とても小さい紙の束だと感じたが
松陰先生から留魂録を託された沼崎吉五郎は
それを4つ折りに小さくし衣服に縫い付けて
大切に守ったからのようだ。
自分が死ぬとしてもやるべきことを教え子に託し
日本を変えていったのだから
その想い、使命感と行動力はすごいものだと感じた。
そして家族にあてた永訣の書。
今までは留魂録にばかり注目していたが
萩で松陰先生と家族のつながりを知ったこともあり
永訣の書に今回改めて惹かれた。
『蒼天の夢』の中で、幼い松陰先生は
「家族を幸せにしたいと思うことは私の心」
というようなことを言っていたことを思い出すが
どんなに公のために尽くしても
それでも何より大切なのは家族だったのではないか
と今回の研修では強く感じた。
それが永訣の書にも現れているようで
今までよりもそこに書かれている文章が染み入った。
しかし、個人的に至誠館で一番衝撃的だったのは
松陰先生のグローバルで研ぎ澄まされた先見性だ。
展示されている與地全図のところで
今元さんと梅地さんがお話しされているのが耳に入ったのだが
松陰先生は、かつて竹島についても
「早く日本の領土にすべきだ」ということを発言した記録があるそうだ。
今も続く問題に150年以上も前から問題意識を持っているなんて
桁違いの天才なのだということを今まで以上に感じた。
16:00 萩城下町
バスで移動し、萩の城下町にたどり着く。
桂小五郎、高杉晋作の生家を続けてみると
本当に近いことがわかる。
身分のある家同士の青春もきっとあったのだろう。
松陰先生の基礎的な部分は少しずつ知れてきたので
周囲の人間ももっと知りたくなってきた。
北尾さんの案内で菊谷家住宅と萩の町のマークの話や
鍵曲についてのお話も聴くことができる。
16:30 高杉晋作の通塾路(晋作生家~松下村塾)
高杉晋作がかつて親の目を盗み
松下村塾へ通っていた道を皆で歩く。
晋作は、この道を何を考えながら歩いたのか
自分なりに想像しながら歩いてみた。
当時の親は絶対的な存在である中で
その目を盗んでまで通う理由、通いたい気持ちは何か、
勉強になるからか、より多く学び国に尽くすという使命感か。
自分の中で一番しっくりきたのは、
ただただ楽しかったから行きたいだけではないかと感じた。
自分の知らないことを知ることができ、
自分の考えを発し、塾生の考えを聴き、松陰先生の考えを聴き、
今まで藩校で学んでも満たされなかった
好奇心が満たされたのではないかと感じた。
そして松下村塾に通う時も
昨日に学んだことを思い返したり、
自分の考えをまとめたりしながら、
松下村塾で今日は何を言い、
どんな議論をするか、何を質問するかなど
いろんなことを考えながら歩いていたのではないかと感じた。
そう考えていると、自分がベン大に入るよりさらに前、
大学4年生の夏休みに見学で通っていた時のことを思い出した。
少し見学するつもりが、毎日見学し、
ほぼ夏休みをベン大で過ごしたあの時は
今までの学校とは違うことを知ることができて
ただただ楽しくて通っていたように感じる。
あの時にあって今はないものが何かあるように思えて
とても大事なことに気付いたような気がした。
そんなことを考えながら歩いていたら松下村塾にたどり着いた。
この日気づいたことは一生大切にしよう。
18:00 民宿美城浜荘へ到着
夕食を終え民宿に到着した。
部屋の名前が吉田、高杉、桂などなど
何とも心をくすぐる名前だった。
しかも自分の部屋は吉田。
同じく吉田部屋で隣に一緒にいた早稲田大学の浅見さんと
若干はしゃいだ。
19:30 松陰先生に迫る講義
風呂を終え、講義に移る。
松陰先生についてまだまだ知らないことや
うまく落とし込めていないことがたくさんあった。
まず基本的なこととして松下村塾の何がすごいのかというところで
他の私塾のように優秀な人材を集めたのではなく
近所の若者が日本を変える人物に育ったことが
他の私塾と圧倒的に違うということが確認できた。
また今回改めて特に感じたことを3つ挙げるならば
一つ目は「華夷弁別」だ。
どんな場所でも世界の中心であり、
萩から日本を変えていった松陰先生の言葉として聞くと
とても説得力を感じる。
今の自分でも全力で何かに取り組めば
それが何かにつながり、少しずつ大きなことにつながっていく。
今回の研修を終えて振り返ると
新聞を読んでも何か見方が変わった気がする。
小さな自分でも大きな何かを変えることができるかもしれない、
そのためにももっと勉強しようと感じた。
二つ目は、送序についてだ。
松陰先生は塾生を送り出す時
その人がこれからどうすべきかのアドバイスだけでなく
自分の人脈を利用してその学生のためになる人を
紹介していたそうだ。
それが死後も明治維新を後押しする原動力になったのではないかと感じた。
そして三つ目がバックボーンとしての「家族の存在」だ。
今回の研修ではこのことに多く触れる機会があったが
一つ気になっていたのが、なぜ松陰先生は
文之進のスパルタ教育に対して反発等をしなかったのかということだ。
当時の親は絶対的ということもあるのだろうが
梅地先生に質問をすると、それは玉木文之進が
まじめな人間であることが幼い松陰先生にもよく伝わり
信頼関係ができていたからではないかと教えていただいた。
このことは松陰先生の至誠にもつながっていると感じ、
松陰先生のルーツには家族との信頼関係が一番にあるのだと感じた。
24:00 『蒼天の夢』鑑賞
懇親会も終わり、最後に蒼天の夢の鑑賞会を行った。
松陰本舗での店番のこともあり
耳に残るぐらい聴いているのは事実だが
それでも萩で松下村塾にいて学んだ後に
見る映像はまた違った。
松陰先生の家族や塾生とのつながりが
一層強く印象に残った。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
 ●松下村塾合宿日報、1日目
●松下村塾合宿日報、1日目12:30 萩の松陰神社で集合
私が日本ベンチャー大學を知ったのは、ちょうど1年前の松下村塾合宿だった。
山近理事長の鞄持ちとして参加させていただいたのだが、大学時代の当時は
合宿にきちんと向き合うことができず、全く学びにならなかった。
ひどい姿勢だったと思う。
しかし、そこでベンチャー大學を知り、当時の学生の皆さんの輝きを見て、
先輩方に励まされ、それがきっかけでベンチャー大學への入学を決めた。
それから一年、ふたたび松下村塾合宿の日を迎えた。
今回人一倍、思い入れは強かったと思う。
また今回の合宿の、個人的な目標は、自らの今後の行動を律することだった。
吉田松陰先生や塾生たちの生き方を全身で感じて、自分の行動に繋げる。
13:00 吉田松陰先生や塾生たちの当時の生の物語を実感
まずは本物の松下村塾を見学し、梅地先生の案内で、塾を取り巻く人々の
ゆかりの地を巡った。
松下村塾や塾生たちの家々、周囲の町並みに実際に行って、見て聞いて、
ときには触れていると、知っていた事実の他の、現実感のあるドラマが
次々と浮かんできた。
そこには青春の輝きや、熱い意見のぶつけ合い、袖を濡らした
悲しみの体験もあったのだろう。
それらは現場だから感じることができたことで、松下村塾のドラマに親しみが湧き、
胸にぐっと込み上げてくるような気持ちも湧いた。
山口県萩、本家の松陰神社の規模は東京よりさらに巨大で、塾の威厳と、
その存在の大きさを感じた。
本物の松下村塾の建物を取り囲むようになっていて、塾と幽囚の館では
松陰先生の引きつけ力、塾生たちの熱心な学習の日々を感じた。
井戸もあり、その石は恐らく当時からのものであり、見るだけではなく、
時には触れることで、全身で感じることの大切さを学んだ。
松陰神社の外、塾生たちの生家などを巡っていると、当時の松下村塾に通う
日々の様子を思い浮かべることができる。
松陰先生ご自身の生家やお墓がある団子岩まで、先生に解説をしていただき
ながら歩く。
細かい事実、エピソードまで教えていただき、松下村塾を巡る人々について、
より深く知ることができた。
松陰先生の生家はかなり小さく、豊かでないご自身の幼少期の生活が
よくわかった。
ただその場所は高台で眺めがよく、萩の街や城、その全体を見渡すこと
ができた。
松陰先生も幼い頃より、そこから萩全体を眺め、さらにそれより外に
思いを巡らして育ったのだろう。
松陰神社から団子岩までのウォークだけでも、松下村塾を取り巻いた環境を
立体的に掴むことができ、人々の感情面での動きも想像することができた。
14:30 貴重な史料が収められた、至誠館を鑑賞
松陰先生ゆかりのものが多く展示されていた。
幼少時代、藩主に講義をしたときに身につけた裃、松浦松洞の書いた松陰先生の
肖像画など、松陰先生の歩んだ人生が体に染み入るようだった。
その中、一番奥に留魂録があった。
至誠の志は永遠で、たとえ死んだとしても魂が朽ちることはない。
そう書き記し、松陰先生は、弟子たちに未来を託した。
松陰先生の大和魂はやはり朽ちることがなく、塾生たちは日本を変えた。
まさに今の日本を作った、魂の留まった書だと思った。
その魂に、私たちも学ばなければならないだろう。
実際の書に出会って、学ぶ決意を新たにした。
16:00 高杉晋作が松下村塾に通った道を辿る
高杉晋作は何に引き寄せられ、夜中に、親の目を盗んでまで松下村塾に
通ったのか。
その理由を推測しながら歩いた。
自由な気質の晋作だから、そこにはよっぽど面白いものがあったのだろう。
ひょっとして松下村塾にのみ、自らの生き甲斐を感じていたのかもしれない。
身分制度がはっきりしていた当時、身分の差のある者同士では話すことも
ままならなかったという。
それが松下村塾では、身分に関係なく語り合える。
また松陰先生は各人それぞれの本質を見て、長所短所は指摘し、長所は
伸ばしてくれる。
松下村塾に、人間としての喜びを感じていたのではないだろうか。
のらりくらりとした自由人の晋作は、意外にも確固たる意志で、一つの場所を
目指していた。
19:30 今元さん・梅地さんによる、松陰先生についての講義
名もない近所の青年たちが日本をひっくり返した。
それがどういうことか。
吉田松陰先生が、指導者としてあまりに優れていた。
もう一つ。
誰にでも何かを成し遂げられる可能性がある。
松陰先生は人の性質を見抜き、長所を伸ばすことが上手かったという。
人はそれぞれ、長所短所があるが、誰にでも何か大きなことができるのでは
ないかと思った。
それは大きな励ましにもなる。
私自身も、短所は数限りなくあるが、それでも何か、私にも大きなことができる
のではないかと思っている。
今回の研修で、その確信はより確かものとなった。
今元さんの講義で、吉田松陰先生、松下村塾の凄さが、実感として分かり始めた。
塾費無料で賄い付き、24時間営業で、期間はたった1年間。
身分の差はなく、松陰先生は例えば品川弥二郎のような当時幼かった者にも
熱く教えたという。
根っからの教育者であった。
ご自身の行動はことごとく失敗しても、塾生たちに夢を持たせて、大成功させた。
それは松陰先生の成功と同義だろう。
続いて梅地先生も講義をしてくださった。
先生には昨年鞄持ちで参加させていただいたときお世話になり、今回私のことも
覚えていてくださった。
先生はご病気で大変な状態だが、私たちのために合宿に付きっきりで
教えてくださった。
吉田松陰先生はやったこと全てが失敗したが、失敗など屁とも思っていなかったと
いう。
実行してだめなら次へ。
それでいいのだ。
先生も最後には成し遂げた。
実行するしかないのだ。
また梅地先生にお会いできて、お話を聞くことができて、本当に良かった。
知識だけでなく、熱も、活力もいただいた。
先生の実行力、行動力が、何よりの学びだった。
いつまでも元気でいていただきたい。
一年後、またもっと色々なことを教えていただきたいと思った。
21:00 参加された方々と「日本を熱く語る」懇親会
今回、鈴江社長、岡崎社長、梶井社長という分校の
校長の方々や、事務局の皆さん、分校の皆さん、大学生の相馬くん、浅見くんなど、
多くの方の参加で成り立っていた。
この合宿で学んだことは、私たちが今の時代で活かしていかなければならない。
そうでなければ、松陰先生や塾生たちに全く申し訳が立たないだろう。
話していて、皆さん意識が高いと感じた。
私ももっと時代に向き合わなければ。
ここで一緒に学んだ方々、同志の皆さんを今後も大切にしていく。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
平成25年(2013)【12月23日(月)】 大阪研修
2013/12/23
コメント (0)
 --------------------------------
--------------------------------●1日の流れ
・適塾見学
・インスタントラーメン研究所見学
・大西昌宏社長の講義
--------------------------------
●適塾と懐徳堂@大阪大学中之島センター
かつて大阪にて緒方洪庵が主宰し
大村益次郎、福沢諭吉、橋本佐内などを輩出した
適塾に行った。
今回は適塾自体は工事中で休館だったため
大阪大学の中之島センターの臨時展示を見に行った。
適塾の塾風は「自由闊達、自主独住」であり
貴賤を問わず病人を救済するための
医療を勉強する塾だったようだ
しかし医学だけでなく、国についてや兵学についても学んだため
兵学者も輩出していったそうだ。
この塾で塾生は限られた教科書を
皆で奪い合うように勉強したため
辞書の置いてある部屋は、常に明かりが消えることはなかったそうだ。
なんという勉学への精神だろうか。
この塾で学んだことは医学や国学、兵学なのだろうが
その学び方はただ知識を詰め込むものでもなかったようだ。
緒方洪庵は数々の洋書の翻訳を行ったが
それは直訳ではなく大意を取って意訳する方法であり
こうした本質を見抜く師匠の教えが
数々の偉大な教え子を輩出していったのだろう。
また大阪大学中之島センターには
懐徳堂についての展示もあった。
懐徳堂というのは大阪の商人の出資によって設立された
町人の学問所である。
商業活動の基本精神を朱子学から学び
学風としては「自由で批判精神あふれる」ものであり
大阪財界、市民をはぐくんでいったそうだ。
大阪大学はこの二つの塾を手本、前身としていることを感じ、
今でも世界から見て日本では4位の大学となっている。
教育における根幹の重要性を感じた。
●安藤百福&小林一三@池田市
大阪・池田に移動し、日清の
インスタントラーメン発明記念館に行き
日清食品の創業者であり
インスタントラーメンの開発者である
安藤百福について学ぶことができた。
安藤百福は些細な日常の気づきから
ひらめきを得てインスタントラーメンを開発し、
事業化していった。
きっかけは戦後の人々の姿を見て
食を豊かにすることが人々を豊かにすることを感じ、
小さな小屋から製麺、味付け、調理法を確立し
チキンラーメンを開発した。
そしてそのチキンラーメンの需要の増加から
大量生産の必要性を感じラインの開発につながった。
そして街頭テレビに群がる人々を見て
CM宣伝の効果を確信し手を付け、
スーパーマーケットが存在するようになったことで
インスタントラーメンのヒットを確信したそうだ。
日々の日常のひらめきを事業につなげていったが、
これは安藤百福の言葉である
「事業化できないアイデアは単なる思い付きに過ぎない」
という言葉そのものだと感じた。
「ベンチャーとは無から有を生み出すこと」
という言葉も残しているが
インスタントラーメンの場合、
家庭の調理という労力を企業が肩代わりする
という今までにない価値がヒットの秘訣のようだ。
こういったひらめきは簡単に思いついたわけではなく
「ひらめきは執念から生まれる」
「私は眠るときもメモとペンを置く。常に考える習慣を身につけなさい」
という言葉からわかるように
常日頃の習慣が現在でも世界に影響を与える
ヒット商品を生み出したのだと感じた。
ひらめきをメモし、考えをする習慣は
自分も身に着ける。
インスタントラーメン開発記念館を後にし
大阪城に行こうとしていたところ
池田には小林一三記念館というものがあることが分かった。
知らなかったので調べると小林一三は
阪急東宝グループの創業者である実業家とのことだった。
今回はすでに年内は休館となっていたため
館内は見ることができなかったが
大阪という昔からのビジネスの地で
二人の実業家について学ぶことができた。
●大西社長講義
株式会社リビアスに移動して
大西社長の講義を受けさせていただいた。
人生を良くするのは
①仕事
②家庭
③個人 の3つであり
この3つをバランスよく大きくしていくことが
豊かな人生を織りなす。
そして人の一日のそれぞれ3分の1は
睡眠、食事、仕事でできているため
人生を豊かにするためのセンターピンは
仕事であるということからお話ししていただいた。
また仕事において成功するためには
①正しいものの考え方
②行動と継続 であり、
①の正しいものの考え方は
人生の結果=能力×熱意×考え方
という稲盛さんの考え方からわかるように
成功に導く大きな要素であり、
意識してプラス思考にもっていかせるには
教育においてその役割が果たさせるとのお話もしていただいた。
②の行動と継続は正しい習慣によって生まれ
それは他者管理による「せざるを得ない環境」を作るという
仕組みが大切になるとお話ししていただいた。
そして正しいかどうかをどう判断するかというと
①本を読むこと
②人ができるようになった習慣を真似をすること
の二つを行っていくことが大切なようだ。
学生が必要とされる要素は記憶力であるが
社会人は判断力が必要とされるというお話をしていただいた。
そしてその判断力を高めるには
①体験②経験を重ねることであり
それは仕事を選り好みしないことが重要となり
それが出世にもつながる、
だから人がやらないことも
チャンスであるとのことで
大西社長の髪切り処でのお話しなどから
お話ししていただいた。
そして引き受けた仕事において
何より大切なのは質ではなく
速さであるというのがとても印象に残った。
未熟な新入社員に求められるのは
無い質ではなく、やれと言われたことを
翌日に提出するような速さであるとのことだった。
これは自分がこれから心がけなくてはいけないことだと強く感じた。
そして何においてもできない理由をもとにあきらめるのではなく
切り開くことが大切であるとお話ししてくださり、
大西社長が今まで事業として行ってきたことを
考えるととても説得力があった。
仕事を選り好みしない、
本を週に二冊読む、
質より速さ、この3つを心がける。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
 ●緒方洪庵
●緒方洪庵医は仁術。
松下村塾のように明治の時代を切り拓いた塾生を多数輩出した、適塾に行ってきた。
適塾を開いた緒方洪庵は教育者としてだけでなく、医者としても
数々の功績を残した。
緒方洪庵は社会的活動の重要性を説いており、人の命を救う医術は
まさに世のため、人のための活動に直結する。
医学を志して入学したものが兵学に目覚め、明治維新で活躍した例も多いという。
緒方洪庵が優れた教育者であり、彼の経世への思いが
福沢諭吉などの人財を育てていったことに間違いはないだろう。
●安藤百福
インスタントラーメン発明記念館で、食の偉人について学んだ。
安藤百福さんについては日本ベンチャー大學ラジオで学んだことが
あるだけに、現地に行くことができて良かった。
食足世平(しょくたりてよはたいらか)。
安藤百福さんは戦後貧しい国民のようすを見て、
「お腹を満たせば笑顔も生まれる」、「人々に幸せになってもらいたい」、
その想いでチキンラーメンを生み出す。
さらには日清食品の社長としてカップラーメンという日本が誇る大発明をし、
世界の貧しい人々への慈善活動も行った。
安藤百福さんの経営も利益のためではないという。
また、「時は命なり」という言葉も大切にされていた。
「時間か進むことによって刻一刻と人々の命はきざまれていく。
それだけの切迫感を持って生きて欲しい。」という意味だ。
私も安藤百福さんのように、どうしたら人々のお役に立てるかを考え、
「時は命なり」の教えを大切にしていく。
●大西昌宏社長
一年の締めくくりとして、大阪校の大西昌宏校長に講義をしていただいた。
人にはそれぞれ使命がある。
その使命には恐らく終わりはなく、その遂行の過程に幸せがある。
私も人に皆、与えられる使命はあると思う。
ではどうすればそれを成し遂げられるか。
やはり人生の3分の1を占める「仕事」が鍵なのだろう。
はじめは、私利私欲でも良いともおっしゃっていた。
しかし仕事をしていく中で徐々に自分の為すべきことがわかってくるのだという。
私もまずは自分の信じた道を進む。
社長も人生を豊かにしたいとおっしゃっていた。でもそれは金持ちになると
いうことではなく、違う豊かさなのだそうだ。
今回、リビアスさんの会社を見学させていただいて、
著書「関西・学生道」の内容のような
苦難の過程と比較すると、心にぐっとくるものがあった。
大西社長はこれからさらに広い世界に目を向けているという。
私もそのようなストーリーを、自分の人生で作りたい。
石田梅岩先生、後藤敬一社長、緒方洪庵先生、安藤百福さん、大西社長…。
日本ベンチャー大學での今年最後の講義は、公への志を持った偉大な
経営者、教育者の熱い想いだった。
現場だから伝わる、生きた学びの研修だった。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
 ●適塾見学
●適塾見学適塾が今耐震工事中ということで、大阪大学にある展示を見に行った。
展示品はごく一部だったが、それでもすごさが伝わってきた。
医学の学校だが、そこから福沢諭吉や大村益次郎など、医療以外の偉人も多く出ている。
それは全国から学びに来るほど教えの質が高いことと、集まった人の
やる気と愛国心が高かったためだろう。
松下村塾の塾生といい、この適塾の塾生といい、日本を変える原動力と
なった人々はよい教育から生まれ出た。
教育が日本を救うなどと聞くが、こういった例をみると、本当のことなのだなと感じる。
自分は今、すごく恵まれた環境で学ばせて頂いている。
吸収できることをとにかく吸収し、日本をよりよく変える一員となる。
●インスタントラーメン研究所見学
インスタントラーメンを開発した安藤百福さんについて学んだ。
大企業の日清食品だが、チキンラーメンを開発し、フリーズドライ製法、そしてカップヌードル、
最近では宇宙食のラーメンを開発するなど常に挑戦し、新しいものを追い求め続け、
世界に驚きを与えるベンチャースピリット溢れた企業なのだなと感じた。
安藤百福さんの残した言葉を紹介しているコーナーがあった。
心に残る言葉ばかりだったが、一番印象に残ったのは
「ひらめきは執念から生まれる」
という言葉だ。
自分はアイディアなどを思いつくことがなかなか出来ない。
振り返ってみると、思いつかないと思ったらすぐに考えるのを諦めていた。
安藤さんは毎日毎日一つについて考え続け、その果てに一つ一つの課題を乗り越えていかれた。
自分はこのように連日一つについて考え続け、アイディアを出すということをしない。
少し考えただけでアイディアが出ないと諦めるのではなく、
頭がどうにかなりそうな位考えることをしてみる。
●大西社長の講義
お話の中で、人生の方程式の話をしていただいた。
人生の結果=能力×熱意×考え方 だそうだ。
考え方のみマイナスがあるということで、熱を込めてやっても
考え方がマイナスならば意味がないどころか
むしろ逆効果になることがある。
大西社長が言われるには人間は本能的にマイナス思考になるように出来ている。
実際私は意識しなければマイナス思考に陥っていることが多い。
思考をいつでもプラスになるようプラスな人と多く関わっていく。
本を読むことも大事だと話されていて、一週間に二冊は読んだ方がよいとのことだった。
実際大西社長の鞄には本が5冊ほど入っていた。
最近本を読む量が少なくなってきている。
お金がない等言い訳せずに、寮にある本を読む、図書館へ行くなどして週二冊本を読む。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
 ●適塾
●適塾オフィス街のまん中にある塾の遺構は江戸時代にタイムスリップでも
したかのような錯覚を覚えます。
今日は耐震工事のために中は見ることのができませんでしたが、
この小さな家屋が戦災を逃れて今日まで当時のままの姿を残すために
どれだけの人が頑張ったのだろうかと思うと感慨深いです。
臨時の展示会に移動して、まず思ったのが何故大阪大学に?
という疑問でした。
聞いてみたところ、大阪大学は適塾が源流となり
医学部をつくり、引き続ぎでいるからという解答をいただき、納得が行きました。
今回の臨時展示は、小さく緒方洪庵先生の履歴が書いてあるだけだった。
次回は、是非中に入り直に感じて行きたいです。
●インスタントラーメン発明記念館
語録に理想的な商品を作ってから、
設備を整えよというものがあった。
まずは、自身の理想、相手のためを思い商品を作り、
効率的なことはその次、
商品に合わせて考える。
最初から効率を考えると
良きものは作れないというものだと
私は感じた。
●大西社長
自分一人で悩まず、そして過信せず、
目標とする人、そこに近いと思う人に相談する。
そうすることで、自身の考え、行動を修正することができ、
より自分の目標に近くなっていける。
そのためにも尊敬する人には積極的に話しかけ、
相談をできる体制を整えて行きます。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
--------------------------------------------------------
平成25年(2013)【12月22日(日)】 現地歴史学/後藤敬一先生(滋賀ダイハツ社長)、 レイクスターズバスケ観戦
2013/12/22
コメント (0)
--------------------------------
●1日の流れ
9:00 京都駅集合
9:15 山近社長と合流
・石田梅岩の出生地、亀岡へ
10:00 京都市亀岡駅到着、生家に移動
10:30 石田梅岩のご子孫、石田二郎さんによる講義
・石田梅岩について
・経営について
・私たちに向けて
・質疑応答
11:15 石田梅岩お墓、参拝・記念撮影
11:30 移動
12:00 道の駅で昼食、アウトプット
13:00 亀岡からバスケットボール会場に移動
・山近社長と別れる
14:00 滋賀のバスケットボール会場に到着
・滋賀ダイハツ株式会社の後藤敬一社長に挨拶
14:30 バスケットボール試合観戦
・滋賀レイクスターズの応援
16:30 試合終了
17:15 後藤敬一社長と懇親会
・ご自身の人生について
・バスケットボールについて
・経営について
19:30 終了、解散
--------------------------------
●石田梅岩
石田梅岩という人物について初めて耳にしたので
朝からさっそく調べる。
石田梅岩は京都亀岡出身の江戸時代の思想家であり、
45歳で塾を開き、石門心学を説いた人物である。
その石田梅岩の出身地である京都・亀岡に行く。
亀岡駅に着くと、改札を出たところに石田梅岩の像が堂々とあった。
観光案内所に行くと、石田梅岩の子孫にあたる方がいるとのことで
ご連絡を取っていただき、その方のご自宅にお伺いさせていただけることになった。
亀岡では有名な人物なのだと感じたが
この後の移動のタクシーで運転手の方に聴くと
名前は知ってはいてもよくは知らないというのが
実際のところだということがよくわかった。
石田さんのお宅に到着すると
部屋に通していただき、お話を聴かせていただけることになった。
石田梅岩、石門心学は現在でも経営者などいろいろな方が学び
少ないながらも太い方が来ると石田さんはおっしゃっていた。
ただ中にはその教えの都合の良いところだけを利用し
利益を得るところをよしとする根拠としたり
そういった点では石田さんも憤りを感じるところもあるようだった。
しかし石門心学の教え自体はとても価値があるものだということは
今でも変わりはなく、
もったいないという考えや、実践を重視するという教えは
他の後、世に影響を与えた偉人の教えや
ベン大で来ていただいた講師の方々と共通するところも多くあった。
ただ道徳的なだけでなく商業的な教えを含み
現代でも影響を与えている石田梅岩と石門心学の教え、
今回をきっかけとして学んでいく。
●滋賀レイクスターズ試合観戦
滋賀ダイハツ後藤敬一社長のご招待で
バスケットボールチーム、滋賀レイクスターズの試合を
観戦させていただいた。
初めての生のバスケットボール観戦、
レイクスターズのホームゲームということもあり
チームカラーの青でほとんどが埋められた観客席、
満員の会場の熱気にはすごいものを感じた。
試合が始まる前からスポンサーである後藤社長のご挨拶があり
滋賀ダイハツさんと後藤社長のすごさを感じるが
さらに驚いたのは、この後の試合直前の挨拶のフリースローの際に
後藤社長がサンタクロースの格好で現れ
担いでいた袋からバスケットボールを取り出し
フリースローを行ったことだ。
後の懇親会で後藤社長からお話を聴くことになるが
すべては見る人を楽しませるために行っているとのことだった。
さらにチアリーダーによるダンスによって盛り上げられる中で
試合が始まった。
ホームゲームなため掛け声の多くがレイクスターズへの声援で
会場の一体感もあり、初めて観戦した人でも
声援をそろえやすいようになっており
初観戦の自分たちでも盛り上がって見ることができた。
今回はクリスマスということもあり
休憩中にはこどもも混ざってのX'masパフォーマンスがあり
通常のチアリーディングも含めて
ハーフタイムのような試合の合間の時間でも
見る人が楽しめるようなエンターテイメント性の高さを感じた。
試合はレイクスターズの負けという悔しい結果に終わったが
初めて見るチームに、気づけば強い思い入れを持っていることを感じた。
それは観客を退屈させない工夫と
初めての観客も参加できるような工夫の結果であり、
ただ楽しいだけの試合観戦でなく
どのようにしてファンを作っていくのかという勉強にもなった。
●後藤社長を囲んでの懇親会
試合後のお忙しいときにも限らず
ベン大生に時間を作っていただき
たくさんのお話を聴かせていただくことができた。
バスケットボールを昔からやっている方なのかと思っていたが
意外にそうではなく、バスケットボールとの関わりは
娘さんがバスケットボールをしていることが始まりとのことだった。
もともと滋賀県にはスポーツチームがなく、
その中でバスケットチームができるとの話が上がる中で
これは盛り上げていかなくてはいけないとのことで
後藤社長も応援していく形になったそうだ。
県を代表する企業として、会社の業績だけでなく
いかに地元に貢献し盛り上げていくか、
そういった気持ちがなくてはできないことである。
サンタクロースの格好をしてのフリースローについてのお話を尋ねると
見ている人をどのようにして楽しませるかという発想であり、
それは後藤社長にとってはもともと持っている考えのようである。
滋賀ダイハツ以前には楽器メーカーで働いていたこともあり
バンド活動などもし、そういった中で人を楽しませることが
自然と身についていったそうだ。
その考えが今の滋賀ダイハツのCSにもつながっているのだ。
店舗をカフェにしたり、車を店舗の外にしか展示しなかったりと
CSを上げるために様々な取り組みを滋賀ダイハツさんは行っているが
滋賀ダイハツさんのすごいところはCSと同時にESも高めているということだ。
CSを高めればESが下がるといわれる中でどうしているかというと
社員の努力や成果が社長にも届き、それが評価される仕組みができているため
社員にとって報われるというのは大きなところに感じた。
クレームなどは上司にも挙げられるのは普通だと思うが
社員の取り組みがボイスメールで社長にまで届くのは
社員にとって大きな励みになり頑張る原動力になる。
とても大きな取り組みだと感じた。
また近江商人についてもお話をしていただき
その正直さを学ぶことができた。
近江商人についての映画である「天秤の詩」についても
紹介していただいたので、まずこの映画を見ることで
近江商人について、ビジネスについて学ぶ。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
●1日の流れ
9:00 京都駅集合
9:15 山近社長と合流
・石田梅岩の出生地、亀岡へ
10:00 京都市亀岡駅到着、生家に移動
10:30 石田梅岩のご子孫、石田二郎さんによる講義
・石田梅岩について
・経営について
・私たちに向けて
・質疑応答
11:15 石田梅岩お墓、参拝・記念撮影
11:30 移動
12:00 道の駅で昼食、アウトプット
13:00 亀岡からバスケットボール会場に移動
・山近社長と別れる
14:00 滋賀のバスケットボール会場に到着
・滋賀ダイハツ株式会社の後藤敬一社長に挨拶
14:30 バスケットボール試合観戦
・滋賀レイクスターズの応援
16:30 試合終了
17:15 後藤敬一社長と懇親会
・ご自身の人生について
・バスケットボールについて
・経営について
19:30 終了、解散
--------------------------------
●石田梅岩
石田梅岩という人物について初めて耳にしたので
朝からさっそく調べる。
石田梅岩は京都亀岡出身の江戸時代の思想家であり、
45歳で塾を開き、石門心学を説いた人物である。
その石田梅岩の出身地である京都・亀岡に行く。
亀岡駅に着くと、改札を出たところに石田梅岩の像が堂々とあった。
観光案内所に行くと、石田梅岩の子孫にあたる方がいるとのことで
ご連絡を取っていただき、その方のご自宅にお伺いさせていただけることになった。
亀岡では有名な人物なのだと感じたが
この後の移動のタクシーで運転手の方に聴くと
名前は知ってはいてもよくは知らないというのが
実際のところだということがよくわかった。
石田さんのお宅に到着すると
部屋に通していただき、お話を聴かせていただけることになった。
石田梅岩、石門心学は現在でも経営者などいろいろな方が学び
少ないながらも太い方が来ると石田さんはおっしゃっていた。
ただ中にはその教えの都合の良いところだけを利用し
利益を得るところをよしとする根拠としたり
そういった点では石田さんも憤りを感じるところもあるようだった。
しかし石門心学の教え自体はとても価値があるものだということは
今でも変わりはなく、
もったいないという考えや、実践を重視するという教えは
他の後、世に影響を与えた偉人の教えや
ベン大で来ていただいた講師の方々と共通するところも多くあった。
ただ道徳的なだけでなく商業的な教えを含み
現代でも影響を与えている石田梅岩と石門心学の教え、
今回をきっかけとして学んでいく。
●滋賀レイクスターズ試合観戦
滋賀ダイハツ後藤敬一社長のご招待で
バスケットボールチーム、滋賀レイクスターズの試合を
観戦させていただいた。
初めての生のバスケットボール観戦、
レイクスターズのホームゲームということもあり
チームカラーの青でほとんどが埋められた観客席、
満員の会場の熱気にはすごいものを感じた。
試合が始まる前からスポンサーである後藤社長のご挨拶があり
滋賀ダイハツさんと後藤社長のすごさを感じるが
さらに驚いたのは、この後の試合直前の挨拶のフリースローの際に
後藤社長がサンタクロースの格好で現れ
担いでいた袋からバスケットボールを取り出し
フリースローを行ったことだ。
後の懇親会で後藤社長からお話を聴くことになるが
すべては見る人を楽しませるために行っているとのことだった。
さらにチアリーダーによるダンスによって盛り上げられる中で
試合が始まった。
ホームゲームなため掛け声の多くがレイクスターズへの声援で
会場の一体感もあり、初めて観戦した人でも
声援をそろえやすいようになっており
初観戦の自分たちでも盛り上がって見ることができた。
今回はクリスマスということもあり
休憩中にはこどもも混ざってのX'masパフォーマンスがあり
通常のチアリーディングも含めて
ハーフタイムのような試合の合間の時間でも
見る人が楽しめるようなエンターテイメント性の高さを感じた。
試合はレイクスターズの負けという悔しい結果に終わったが
初めて見るチームに、気づけば強い思い入れを持っていることを感じた。
それは観客を退屈させない工夫と
初めての観客も参加できるような工夫の結果であり、
ただ楽しいだけの試合観戦でなく
どのようにしてファンを作っていくのかという勉強にもなった。
●後藤社長を囲んでの懇親会
試合後のお忙しいときにも限らず
ベン大生に時間を作っていただき
たくさんのお話を聴かせていただくことができた。
バスケットボールを昔からやっている方なのかと思っていたが
意外にそうではなく、バスケットボールとの関わりは
娘さんがバスケットボールをしていることが始まりとのことだった。
もともと滋賀県にはスポーツチームがなく、
その中でバスケットチームができるとの話が上がる中で
これは盛り上げていかなくてはいけないとのことで
後藤社長も応援していく形になったそうだ。
県を代表する企業として、会社の業績だけでなく
いかに地元に貢献し盛り上げていくか、
そういった気持ちがなくてはできないことである。
サンタクロースの格好をしてのフリースローについてのお話を尋ねると
見ている人をどのようにして楽しませるかという発想であり、
それは後藤社長にとってはもともと持っている考えのようである。
滋賀ダイハツ以前には楽器メーカーで働いていたこともあり
バンド活動などもし、そういった中で人を楽しませることが
自然と身についていったそうだ。
その考えが今の滋賀ダイハツのCSにもつながっているのだ。
店舗をカフェにしたり、車を店舗の外にしか展示しなかったりと
CSを上げるために様々な取り組みを滋賀ダイハツさんは行っているが
滋賀ダイハツさんのすごいところはCSと同時にESも高めているということだ。
CSを高めればESが下がるといわれる中でどうしているかというと
社員の努力や成果が社長にも届き、それが評価される仕組みができているため
社員にとって報われるというのは大きなところに感じた。
クレームなどは上司にも挙げられるのは普通だと思うが
社員の取り組みがボイスメールで社長にまで届くのは
社員にとって大きな励みになり頑張る原動力になる。
とても大きな取り組みだと感じた。
また近江商人についてもお話をしていただき
その正直さを学ぶことができた。
近江商人についての映画である「天秤の詩」についても
紹介していただいたので、まずこの映画を見ることで
近江商人について、ビジネスについて学ぶ。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
●石田梅岩
滋賀研修一日の最初は、松下幸之助さんも心の師と仰ぐという、石田梅岩先生について学んだ。
山近理事長が案内してくださり、梅岩先生の故郷に向かう。
駅の改札を出るとすぐ正面に梅岩先生の銅像が迎えてくれ、
ゆかりの地も多々あり、町全体が先生を讃えているのだとわかる。
観光案内所に行くと、今もご子孫がいらっしゃるという生家を教えてくださった。
連絡をすると、なんとご子孫がご在宅で、待っていてくださるというので
すぐに生家に向かう。
雪の降る日に昔の名残を残す梅岩先生の生家で、先生について学ぶ。
この日したような現地での体験としての学びは恐らく生涯忘れないだろう。
儒教・仏教・道教の説を取り入れながら、質素倹約など日本の精神を据えた心学を講釈した。
それも聴講料不要、女性も歓迎という当時の常識を越えた活動だった。
そして何より、実行しないと意味がない、という教えだという。
生家には今も多くの経営者が訪れ、企業研修をやる会社もあるという。
ご子孫の石田二郎さんが、私たちにこれからの社会を生きる上での
実践的なお話をしてくださったのも、実行を大事になさっているからだろう。
帰りは山近理事長に名物のうどんと丹波牛の牛丼をご馳走になりながら、アウトプットを行った。
貴重な学び、体験をさせていただいた。
●後藤敬一社長
滋賀レイクスターズのバスケットボールの試合観戦は、滋賀ダイハツ株式会社の
盛り上げや応援が会場全体を包み込み、終始楽しませていただいた。
滋賀のチアリーダーチームやアナウンサーらがコールを誘い、
私たちも自然と声が出て、体が動く。
ハーフタイムやたった60秒間の休憩でも応援のパフォーマンスがあり、
トイレに行くのももったいないと感じるほどだった。
完全なホーム空間を作り上げていたあの場には大きな学びがあった思う。
盛り上げる工夫があり、徹底された展開があり、その裏には県の活性化という強い想いが感じられた。
滋賀ダイハツ株式会社は日本経営品質賞を受賞された会社で、
後藤敬一社長は大会で挨拶もされていた。
さらになんと社長はこの試合のあとの大事な夜を、毎年ベンチャー大學のために空けてくださっている。
後藤社長との懇親会に参加させていただいた。
ベンチャー大學と後藤社長という席だったので、たっぷりお話を聞き、質問をすることができた。
社長の根底にあるのはお客様や社員の皆さんを楽しませたいという想いで、
儲けのための経営ではないということを強く感じた。
このご時勢で滋賀ダイハツさんの車の販売台数が伸びているのには、
店舗をカフェのようにしたり、女性や子供が行きたいと思う工夫をしたり、
そこには普通は思いつかない理由がある。
それは後藤社長の経営の志から生まれているのだろう。
近江商人の、自らの私欲を顧みない粋な話もしてくださり、
その心意気にも社長のお考えの源が感じられた。
滋賀の小さい鮎が県外に出れば大きくなるように、滋賀ダイハツ株式会社も
これからさらに発展していくのだろう。
近江商人のように。
近くでお話を聞くということはおかんがえの熱が近くから直接伝わってくる。
バスケットボールをいい席で見せていただいたばかりでなく、ありがたい経験をさせていただいた。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
滋賀研修一日の最初は、松下幸之助さんも心の師と仰ぐという、石田梅岩先生について学んだ。
山近理事長が案内してくださり、梅岩先生の故郷に向かう。
駅の改札を出るとすぐ正面に梅岩先生の銅像が迎えてくれ、
ゆかりの地も多々あり、町全体が先生を讃えているのだとわかる。
観光案内所に行くと、今もご子孫がいらっしゃるという生家を教えてくださった。
連絡をすると、なんとご子孫がご在宅で、待っていてくださるというので
すぐに生家に向かう。
雪の降る日に昔の名残を残す梅岩先生の生家で、先生について学ぶ。
この日したような現地での体験としての学びは恐らく生涯忘れないだろう。
儒教・仏教・道教の説を取り入れながら、質素倹約など日本の精神を据えた心学を講釈した。
それも聴講料不要、女性も歓迎という当時の常識を越えた活動だった。
そして何より、実行しないと意味がない、という教えだという。
生家には今も多くの経営者が訪れ、企業研修をやる会社もあるという。
ご子孫の石田二郎さんが、私たちにこれからの社会を生きる上での
実践的なお話をしてくださったのも、実行を大事になさっているからだろう。
帰りは山近理事長に名物のうどんと丹波牛の牛丼をご馳走になりながら、アウトプットを行った。
貴重な学び、体験をさせていただいた。
●後藤敬一社長
滋賀レイクスターズのバスケットボールの試合観戦は、滋賀ダイハツ株式会社の
盛り上げや応援が会場全体を包み込み、終始楽しませていただいた。
滋賀のチアリーダーチームやアナウンサーらがコールを誘い、
私たちも自然と声が出て、体が動く。
ハーフタイムやたった60秒間の休憩でも応援のパフォーマンスがあり、
トイレに行くのももったいないと感じるほどだった。
完全なホーム空間を作り上げていたあの場には大きな学びがあった思う。
盛り上げる工夫があり、徹底された展開があり、その裏には県の活性化という強い想いが感じられた。
滋賀ダイハツ株式会社は日本経営品質賞を受賞された会社で、
後藤敬一社長は大会で挨拶もされていた。
さらになんと社長はこの試合のあとの大事な夜を、毎年ベンチャー大學のために空けてくださっている。
後藤社長との懇親会に参加させていただいた。
ベンチャー大學と後藤社長という席だったので、たっぷりお話を聞き、質問をすることができた。
社長の根底にあるのはお客様や社員の皆さんを楽しませたいという想いで、
儲けのための経営ではないということを強く感じた。
このご時勢で滋賀ダイハツさんの車の販売台数が伸びているのには、
店舗をカフェのようにしたり、女性や子供が行きたいと思う工夫をしたり、
そこには普通は思いつかない理由がある。
それは後藤社長の経営の志から生まれているのだろう。
近江商人の、自らの私欲を顧みない粋な話もしてくださり、
その心意気にも社長のお考えの源が感じられた。
滋賀の小さい鮎が県外に出れば大きくなるように、滋賀ダイハツ株式会社も
これからさらに発展していくのだろう。
近江商人のように。
近くでお話を聞くということはおかんがえの熱が近くから直接伝わってくる。
バスケットボールをいい席で見せていただいたばかりでなく、ありがたい経験をさせていただいた。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
●気付き
・石田梅岩先生の生家訪問
山近社長の案内で石田梅岩先生の生家へ行き、そこで子孫の方よりお話をうかがった。
駅の改札前に銅像があったり、経営者の方が社員さんをつれてお話を聴きに来たりされているそうで、
それだけ偉大な人物なのかと驚いた。
実際お話を伺ってみると、士農工商と一番下の身分とされていた商人の意識改革をした学問、
「心学」を創始されたというとても偉大な方だった。
まるで知らなかったことが恥ずかしい。本を読み、調べ直す。
時代時代で便利に使われて、儲けを優先する言い訳にも使われたりするそうだ。
しかし教えとしては儲けよりも欲を抑え、共生することが大事で、むしろ利益追求とは逆だ。
それを言葉を一部引用して持ち出されているということだ。
先人について正しく学んでゆく。
・バスケットボール試合見学
滋賀ダイハツの後藤社長のご厚意でバスケットボールの試合を見学させていただいた。
プロのバスケットボールの試合を見るのは始めてだったが、一瞬すらも観客を退屈させないように、
タイムアウトの60秒ですらもチアリーダーがパフォーマンスをされていた。
休憩時間であってもトイレに行く間もないほど目が離せなかった。
おかげでテンションが落ちることはなく、後半になるごとに
会場の熱気も私のモチベーションもより上がっていき、
最後はルールもよく分からないが、また来たいと思わせられた。
・滋賀ダイハツ後藤社長との懇親会
滋賀ダイハツの後藤社長がお時間をとっていただき、懇親会をしていただいた。
経営品質賞をとられたほどの方にわざわざベンチャー大學のために時間を作っていただき、本当にありがたい。
CSを上げるとESが下がり、ESを上げるとCSが下がってしまう。
世の中の経営者はこのバランスで悩んでいるが、この一段階上に両方とも
高いという状態があると信じていると話されていた。
世間一般で言えばそんなものはないのではないかと思うが、お役立ちできて
お客様の喜ぶ姿でこちらも嬉しいということで双方が上がっていくのだそうだ。
そしてお役に立つという精神は滋賀にもともと根付いているとのことだった。
困っている人がおられたらお客様ではなくとも社員さんが自主的に動こうと
思える仕組みを作られていて、
地域も会社も良くしようという気概を感じた。
相手も自分も喜べる、そんな仕組みを自分も考える。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
●岩田梅岩先生
・商人を志すものとして、
今の日本の商人の心の道筋を作った方を、
知らなかった事で、とても恥ずかしい思いをした。
またこの方は、「もったいない精神」にも
通じているというお話もあった。
不況の度に取り上げられてきたそうだが、
これからの時代に質素倹約、
買い手良し、売り手良しの精神でする経営する
経営者にならねばと思いました。
そのように常に考えて行動します。
・生で観る試合の迫力
スピード感があり、たとえルールが分からなくても、
何と無くわかってくる。
最初は恥ずかしかったが、
少しづつ声を出し腕を振り上げるようになった。
こう言ったことができるようになるのも、
直で見て感じて行くことの効能だと思う。
●後藤社長
CS、ESはシーソーと同じだとよく言われているが、
さらに先があるのではないかと仰られていた。
一つ上の段階にでは、両立し、
両方が幸福になれる会社をつくれるんのではないかと
考え行動に移している。
既存のもので満足せず、
一つ上のものを求めるように考えを持っていきます。
社員は宝だとすっと言える社長は滅多にいない、
自分が実際に会社を持った時、
部下が育たない、いい人が入ってこないと思わずに
どうしたら良い人になるか、相手にとって自分は、
より良い影響を与えていれるかを考えて注意して行きます。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
--------------------------------------------------------
・石田梅岩先生の生家訪問
山近社長の案内で石田梅岩先生の生家へ行き、そこで子孫の方よりお話をうかがった。
駅の改札前に銅像があったり、経営者の方が社員さんをつれてお話を聴きに来たりされているそうで、
それだけ偉大な人物なのかと驚いた。
実際お話を伺ってみると、士農工商と一番下の身分とされていた商人の意識改革をした学問、
「心学」を創始されたというとても偉大な方だった。
まるで知らなかったことが恥ずかしい。本を読み、調べ直す。
時代時代で便利に使われて、儲けを優先する言い訳にも使われたりするそうだ。
しかし教えとしては儲けよりも欲を抑え、共生することが大事で、むしろ利益追求とは逆だ。
それを言葉を一部引用して持ち出されているということだ。
先人について正しく学んでゆく。
・バスケットボール試合見学
滋賀ダイハツの後藤社長のご厚意でバスケットボールの試合を見学させていただいた。
プロのバスケットボールの試合を見るのは始めてだったが、一瞬すらも観客を退屈させないように、
タイムアウトの60秒ですらもチアリーダーがパフォーマンスをされていた。
休憩時間であってもトイレに行く間もないほど目が離せなかった。
おかげでテンションが落ちることはなく、後半になるごとに
会場の熱気も私のモチベーションもより上がっていき、
最後はルールもよく分からないが、また来たいと思わせられた。
・滋賀ダイハツ後藤社長との懇親会
滋賀ダイハツの後藤社長がお時間をとっていただき、懇親会をしていただいた。
経営品質賞をとられたほどの方にわざわざベンチャー大學のために時間を作っていただき、本当にありがたい。
CSを上げるとESが下がり、ESを上げるとCSが下がってしまう。
世の中の経営者はこのバランスで悩んでいるが、この一段階上に両方とも
高いという状態があると信じていると話されていた。
世間一般で言えばそんなものはないのではないかと思うが、お役立ちできて
お客様の喜ぶ姿でこちらも嬉しいということで双方が上がっていくのだそうだ。
そしてお役に立つという精神は滋賀にもともと根付いているとのことだった。
困っている人がおられたらお客様ではなくとも社員さんが自主的に動こうと
思える仕組みを作られていて、
地域も会社も良くしようという気概を感じた。
相手も自分も喜べる、そんな仕組みを自分も考える。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
●岩田梅岩先生
・商人を志すものとして、
今の日本の商人の心の道筋を作った方を、
知らなかった事で、とても恥ずかしい思いをした。
またこの方は、「もったいない精神」にも
通じているというお話もあった。
不況の度に取り上げられてきたそうだが、
これからの時代に質素倹約、
買い手良し、売り手良しの精神でする経営する
経営者にならねばと思いました。
そのように常に考えて行動します。
・生で観る試合の迫力
スピード感があり、たとえルールが分からなくても、
何と無くわかってくる。
最初は恥ずかしかったが、
少しづつ声を出し腕を振り上げるようになった。
こう言ったことができるようになるのも、
直で見て感じて行くことの効能だと思う。
●後藤社長
CS、ESはシーソーと同じだとよく言われているが、
さらに先があるのではないかと仰られていた。
一つ上の段階にでは、両立し、
両方が幸福になれる会社をつくれるんのではないかと
考え行動に移している。
既存のもので満足せず、
一つ上のものを求めるように考えを持っていきます。
社員は宝だとすっと言える社長は滅多にいない、
自分が実際に会社を持った時、
部下が育たない、いい人が入ってこないと思わずに
どうしたら良い人になるか、相手にとって自分は、
より良い影響を与えていれるかを考えて注意して行きます。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
--------------------------------------------------------
平成25年(2013)【12月21日(土)】 大掃除
2013/12/21
コメント (0)
--------------------------------
●1日の流れ
9:00 五反田事務所集合
9:05 朝礼
9:15 年末大掃除&会員様への発送
発送作業(佐藤、南出)
大掃除(高岸、小林、大森)
荷物移動
蛍光灯掃除
床磨き
ワックスがけ
11:30 昼食
12:00 掃除再開
荷物再移動
13:00 佐藤さん、高岸さん出発
14:00 終礼、解散
--------------------------------
●事務所掃除
五反田事務所の
年末大掃除をお手伝いさせていただいた。
荷物をすべて移動させ
机や椅子を動かして、何もない状態にすることから始めた。
さまざまな書籍があるのを見ることができた。
いろいろなものが作られてきた会社の歴史の
一部を感じた。
天井の蛍光灯などの掃除をするときには
安全のためにと全体の電気を消したが
「それでは汚れが見えない」と今元さんからアドバイスいただいた。
その通りにしてみると、きれいに拭いたようで
まだまだ汚れているところがあるのがよくわかった。
なんとなくでやるのではなく、きちんと目で見て
確認しながら行うのが大切だと感じた。
そのあとの床磨き、ワックスがけの際にも
目で見ることを心がけた。
床磨きの際もどこが汚れているのかきちんと見なくては
時間も手間もかかって無駄が多くなり、
ワックスがけに関してもどこが塗れていないのか
目で確認しないとムラができてしまう。
目で見てきちんと確認するのは大切だと感じた。
●発送学
今回は自分は掃除の分担だったので
発送作業自体は行わなかったが、
すべての作業が終わり、
今元さんが確認してみると、
発送する封筒の中身に
資料が足りないことなどが判明した。
大量の作業を行う以上、ミスはあるとは思うが
それを起こさないためにも最後の確認が大切だと学んだ。
すべての資料をそろえ、最後に誰か一人が責任を持って
中身を確認することは、大きな手間ではあるが
その手間を省くとミスにつながってしまう。
何事においても、最終段階での確認を怠らないようにしていく。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
●1日の流れ
9:00 五反田事務所集合
9:05 朝礼
9:15 年末大掃除&会員様への発送
発送作業(佐藤、南出)
大掃除(高岸、小林、大森)
荷物移動
蛍光灯掃除
床磨き
ワックスがけ
11:30 昼食
12:00 掃除再開
荷物再移動
13:00 佐藤さん、高岸さん出発
14:00 終礼、解散
--------------------------------
●事務所掃除
五反田事務所の
年末大掃除をお手伝いさせていただいた。
荷物をすべて移動させ
机や椅子を動かして、何もない状態にすることから始めた。
さまざまな書籍があるのを見ることができた。
いろいろなものが作られてきた会社の歴史の
一部を感じた。
天井の蛍光灯などの掃除をするときには
安全のためにと全体の電気を消したが
「それでは汚れが見えない」と今元さんからアドバイスいただいた。
その通りにしてみると、きれいに拭いたようで
まだまだ汚れているところがあるのがよくわかった。
なんとなくでやるのではなく、きちんと目で見て
確認しながら行うのが大切だと感じた。
そのあとの床磨き、ワックスがけの際にも
目で見ることを心がけた。
床磨きの際もどこが汚れているのかきちんと見なくては
時間も手間もかかって無駄が多くなり、
ワックスがけに関してもどこが塗れていないのか
目で確認しないとムラができてしまう。
目で見てきちんと確認するのは大切だと感じた。
●発送学
今回は自分は掃除の分担だったので
発送作業自体は行わなかったが、
すべての作業が終わり、
今元さんが確認してみると、
発送する封筒の中身に
資料が足りないことなどが判明した。
大量の作業を行う以上、ミスはあるとは思うが
それを起こさないためにも最後の確認が大切だと学んだ。
すべての資料をそろえ、最後に誰か一人が責任を持って
中身を確認することは、大きな手間ではあるが
その手間を省くとミスにつながってしまう。
何事においても、最終段階での確認を怠らないようにしていく。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
●大掃除
私は残っていた発送作業を中心にやったのだが、
なぜ普段あまり使わない五反田の事務所の大掃除をやるか、
田中さんが教えてくださったその理由が印象に残った。
ベンチャー大學の事務的なことは多くを五反田でやっている、
その仕事がなければベンチャー大學での学びもない。
この一年の学びのありがたさを感じるとともに、裏で支えてくださった
事務局の方々に改めて感謝の気持ちが生まれた。
ものごとは裏にある深いところまで考えるべきだ。
自然にそのような気持ちを持てるようにする。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
●大掃除
学ばしていただいている自分達が
少しずつでも恩返しできるのは、
こういった行事の時だと思い、
日頃の感謝を込めて掃除をさせていただいた。
年度末の締めくくりにしっかりと、
片付け、新年を気持ちよく迎えてもらえれるようにしました。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
--------------------------------------------------------
私は残っていた発送作業を中心にやったのだが、
なぜ普段あまり使わない五反田の事務所の大掃除をやるか、
田中さんが教えてくださったその理由が印象に残った。
ベンチャー大學の事務的なことは多くを五反田でやっている、
その仕事がなければベンチャー大學での学びもない。
この一年の学びのありがたさを感じるとともに、裏で支えてくださった
事務局の方々に改めて感謝の気持ちが生まれた。
ものごとは裏にある深いところまで考えるべきだ。
自然にそのような気持ちを持てるようにする。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
●大掃除
学ばしていただいている自分達が
少しずつでも恩返しできるのは、
こういった行事の時だと思い、
日頃の感謝を込めて掃除をさせていただいた。
年度末の締めくくりにしっかりと、
片付け、新年を気持ちよく迎えてもらえれるようにしました。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
--------------------------------------------------------
平成25年(2013)【12月19日(木)】 事業創造/鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)
2013/12/19
コメント (0)
 --------------------------------
--------------------------------●1日の流れ
9:10 朝礼、掃除
9:40 松陰神社参拝
10:10 新聞アウトプット
・原発廃炉
・アフリカ投資
・ビットコイン
11:30 昼食
12:30 鳥越昇一郎先生による「事業創造」講義開始
・講義
・プレゼンテーションのワーク
・プレゼン発表 →見学者の大南くん、相馬くん、新館くんも参加
16:30 終礼、解散
--------------------------------
●気付き
・新聞アウトプット
記事を、単純に議論をしやすいかどうかで選んでしまった。
なぜ選ぶのか、なぜ議論するのか、そこが重要だ。
議論のための議論ではなく、今後に繋がる議論をするためにテーマ選びから考える。
時流を掴み、その後のチャンスを掴めるような議論にする。
・事業創造
鳥越先生に事業創造の講義をしていただいた。
自分の事業について調べてその上で色々と決めたつもりだったが、
収支やターゲット、仕組みが甘い。
付加価値をつけて料金を高めに設定するなどの工夫が必要になる。
改めて自分の事業を具体化し、練り直す。
今日は5期生以外の聴講生が3人。外部の意見を聞くことができた。
いつものメンバーからは中々でないであろう意見も多く出て、刺激となった。
今回いただいたアドバイスを活かして、1ランク上の段階へ上がる。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
●より具体的に
もう卒業まで3ヶ月。
事業創造も完成まで3ヶ月。
残り時間は少ない。
この日はベンチャー大學生以外に3人のゲストが来てくれた。
いつもの仲間ではない助言はためになることばかりだった。
人が変わればそれだけ新鮮な意見もいただける。
もっと多く人に話を聞いてみる。
これからさらに内容を具体化し、事業としての魅力をつけていく。
残りの期間で志を全うでき、かつ成功可能なビジネスを作り上げる。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
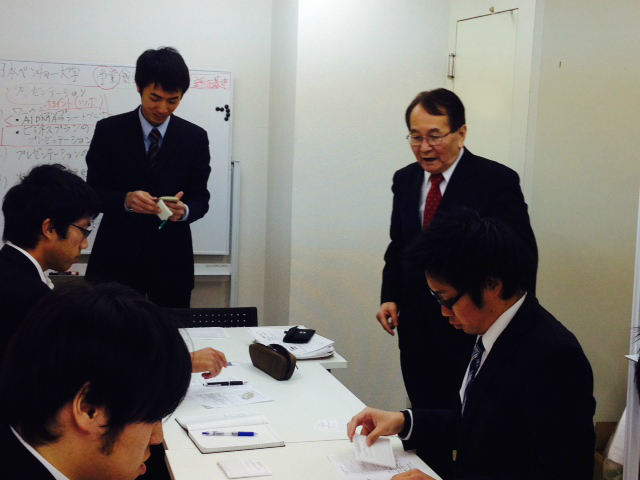 ●新聞アウトプット
●新聞アウトプット今までやってきて
次を見通すということが、
ちゃんと出来ていなかったなと感じる。
今ある情報から、先のことを予測する力は、
これから特に必要になってくると考えれるので、
養って行きます。
●事業創造
今回感じたことは、
相手に対して、共感を与えられていない
ということを感じた。
自分の説明がヘタとか、
それ以前に、自分の言葉が相手に
伝わっていない。
よく言われますが、
ワクワク感が無いということの意味を
痛感しました。
●鳥越先生/事業創造
何度もやっているせいか、
知らない人に向けての説明を
うまくできていないことに気がついた。
自分がやり始めて資金を提供や
仕事の依頼をもらう時は、
必ず知らない人に向けての説明をしなければならない。
誰が聴いても分かるプレゼンをするように練習します。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
---------------------------------------------------------
















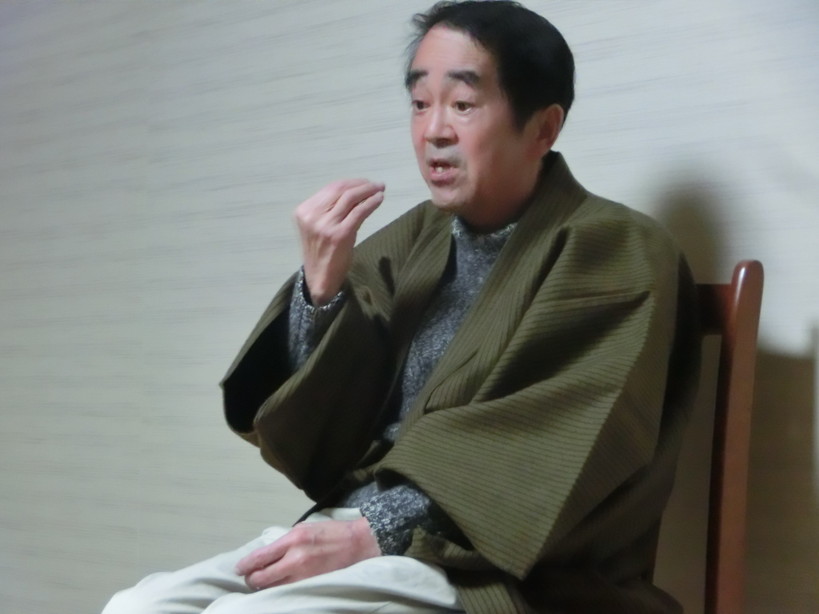



 RSS 2.0
RSS 2.0












