東京校の講義レポート
令和2年(2020)【10月13日(火) 】秋の出版編集トレーニング2日目 4期生4組
2020/10/13
コメント (0)
------------------------------------------------------
令和2年(2020)【10月13日(火)】
秋の出版編集トレーニング2日目
4期生4組
--------------------------------------------------------
《新聞の重要性》
私は今まで、新聞を読む習慣がありませんでした。
しかし、今回のお話を聞いて、新聞で現在経済や、昨日の出来事を知ることによって、未来の予測ができると聞いて、新聞の重要性を理解しました。
そして、未来を知るには、やはり現状をしっかり把握しておく必要があることを改めて理解しました。
《続けること》
新聞は、一度読むだけだなく、毎日続けて読むことに意味があるのだと思いました。これは、新聞だけでなく、色々なことに言えると思います。
毎日少しずつでも、新聞の1面かそれ以上を読むことを続けて、半年後には日本の経済について詳しく知っていたいです。
・日経新聞の1~3面をできるだけ毎日読む。忙しくても1面は読む
・夜11時のニュースを見る
・流通新聞を読む
・出版業界を描いた映画やドラマに触れる
・話を聞いている間、どんなことを質問すべきか考える。何事にも疑問点を持って接する。
M.K@関西大学
--------------------------------------------------------
《社会に出てからの当たり前》
本日の講義を経て、新聞、主に日経新聞を読むことへのモチベーションが上がりました。
主に、日経新聞がどのように構成されていて、どういった優先順位で読み進めていくべきかということ、
日経新聞を読むことがどう役に立っていくのかということについて学びました。
日経新聞について、私は毎週土曜日に開催してくださっている新聞アウトプットの時間をきっかけに、しっかりと読み始めたばかりです。
活字の羅列を読むのは得意な方だと思っているのですが、わからない語を調べたり、どういうことだったかとわからなくなって
もう一度読み直すなどの作業があることで、まだまだ読み進めるのに時間がかかります。
しかし、こうした過程を積むことにも意味があるのだと思いました。特に、本日上がった「経済」という単語を一つ取ったとしても、
いざ説明してくださいと言われた際には、なんとなくの言葉しか出ず、本当の意味というものを知らずに使用していたということに気づかされました。
知識があるかないかは、用語を出したときの反応でわかるとおっしゃっていた通り、自分に自信をつけるためにも知識を習得することは重要であり、
大きな武器になると改めて感じました。また、わからない単語を調べて内容をある程度把握するだけではなく、そこから自分はどういう社会にしたいのか、
そして将来的にどういった社会になりそうかというところまで考えるようにしていきたいと思いました。
日経新聞の一面は、社会に出た際には知っていて当たり前、むしろ知らなければ恥ずかしいという内容であることも踏まえ、
今から日経新聞に目を通すことを習慣化していきたいと思います。徐々にでも、成長を自分で感じるためにも、
まず継続して行うということに重点を置いて日経新聞、そして現代の社会に向き合っていければと思いました。
・日経新聞を購読する
・どんなに忙しいという時にでも、一面だけ読むでもいいので、継続して読む
・わからない単語はわからないままにせず、知識を増やしていく
・記事の内容から、未来のことを予測するような視点も持てるよう意識する
R.S@明治学院大学
令和2年(2020)【10月13日(火)】
秋の出版編集トレーニング2日目
4期生4組
--------------------------------------------------------
《新聞の重要性》
私は今まで、新聞を読む習慣がありませんでした。
しかし、今回のお話を聞いて、新聞で現在経済や、昨日の出来事を知ることによって、未来の予測ができると聞いて、新聞の重要性を理解しました。
そして、未来を知るには、やはり現状をしっかり把握しておく必要があることを改めて理解しました。
《続けること》
新聞は、一度読むだけだなく、毎日続けて読むことに意味があるのだと思いました。これは、新聞だけでなく、色々なことに言えると思います。
毎日少しずつでも、新聞の1面かそれ以上を読むことを続けて、半年後には日本の経済について詳しく知っていたいです。
・日経新聞の1~3面をできるだけ毎日読む。忙しくても1面は読む
・夜11時のニュースを見る
・流通新聞を読む
・出版業界を描いた映画やドラマに触れる
・話を聞いている間、どんなことを質問すべきか考える。何事にも疑問点を持って接する。
M.K@関西大学
--------------------------------------------------------
《社会に出てからの当たり前》
本日の講義を経て、新聞、主に日経新聞を読むことへのモチベーションが上がりました。
主に、日経新聞がどのように構成されていて、どういった優先順位で読み進めていくべきかということ、
日経新聞を読むことがどう役に立っていくのかということについて学びました。
日経新聞について、私は毎週土曜日に開催してくださっている新聞アウトプットの時間をきっかけに、しっかりと読み始めたばかりです。
活字の羅列を読むのは得意な方だと思っているのですが、わからない語を調べたり、どういうことだったかとわからなくなって
もう一度読み直すなどの作業があることで、まだまだ読み進めるのに時間がかかります。
しかし、こうした過程を積むことにも意味があるのだと思いました。特に、本日上がった「経済」という単語を一つ取ったとしても、
いざ説明してくださいと言われた際には、なんとなくの言葉しか出ず、本当の意味というものを知らずに使用していたということに気づかされました。
知識があるかないかは、用語を出したときの反応でわかるとおっしゃっていた通り、自分に自信をつけるためにも知識を習得することは重要であり、
大きな武器になると改めて感じました。また、わからない単語を調べて内容をある程度把握するだけではなく、そこから自分はどういう社会にしたいのか、
そして将来的にどういった社会になりそうかというところまで考えるようにしていきたいと思いました。
日経新聞の一面は、社会に出た際には知っていて当たり前、むしろ知らなければ恥ずかしいという内容であることも踏まえ、
今から日経新聞に目を通すことを習慣化していきたいと思います。徐々にでも、成長を自分で感じるためにも、
まず継続して行うということに重点を置いて日経新聞、そして現代の社会に向き合っていければと思いました。
・日経新聞を購読する
・どんなに忙しいという時にでも、一面だけ読むでもいいので、継続して読む
・わからない単語はわからないままにせず、知識を増やしていく
・記事の内容から、未来のことを予測するような視点も持てるよう意識する
R.S@明治学院大学
 《洞察力を鍛えろ》
《洞察力を鍛えろ》今起こっていることが分からなければ新しいものは作れない、という言葉にハッとしました。確かに世の中の現状を知らなければ、
人々に楽しんでもらえるコンテンツは生み出せないと気付きました。
また、その洞察力を鍛えるために新聞を読むことは、社会人になるにあたって大事であることも気付かされました。
《自分のペースでコツコツと》
最初は毎日新聞買って読んでアウトプット、できるかな…と心配でした。
しかし、自分が続けられるやり方でやればいいとアドバイスしていただいて、自分のペースでやっていいんだ、と安心しました。
できるかなと思い留まる前に、自分ができる範囲でまずやってみることが大きな一歩になることに気付きました。
・新聞を読む(自分のペースで)
・読んで学んだことを、人と共有する
・疑問点を持ちながら話を聞き、質問を積極的に投げかける
N.J@都留文科大学
--------------------------------------------------------
《源流》
個人面談を数週間前に終え、日経新聞を読み始めたもののやはり内容が難しく、読んでは概要をノートにまとめる毎日。
自分の考えを書き出すなど到底できず、何度か諦めようと思いました。
しかし今回の講義を終えて、何に着目して読もうとしてたのか改めて考えると、ただひたすら文を追うことしか頭になかったのだとようやく学習しました。
今後も毎日読む上で、今回教えていただいた着眼点など、よく噛み締めて読み進めていこうと思います。
ノートに内容をまとめる際に、ただ真新しいことだけ選出するのではなく、前の日に関わりのある事象と比較し、
次はどんなことが起こりそうかなど、分からなくともまずは自分の頭で何かしら考えます。
S.S@国士舘大学
《洞察力を鍛えろ》
今起こっていることが分からなければ新しいものは作れない、という言葉にハッとしました。確かに世の中の現状を知らなければ、
人々に楽しんでもらえるコンテンツは生み出せないと気付きました。
また、その洞察力を鍛えるために新聞を読むことは、社会人になるにあたって大事であることも気付かされました。
《自分のペースでコツコツと》
最初は毎日新聞買って読んでアウトプット、できるかな…と心配でした。
しかし、自分が続けられるやり方でやればいいとアドバイスしていただいて、自分のペースでやっていいんだ、と安心しました。
できるかなと思い留まる前に、自分ができる範囲でまずやってみることが大きな一歩になることに気付きました。
・新聞を読む(自分のペースで)
・読んで学んだことを、人と共有する
・疑問点を持ちながら話を聞き、質問を積極的に投げかける
N.J@都留文科大学
--------------------------------------------------------
《源流》
個人面談を数週間前に終え、日経新聞を読み始めたもののやはり内容が難しく、読んでは概要をノートにまとめる毎日。
自分の考えを書き出すなど到底できず、何度か諦めようと思いました。
しかし今回の講義を終えて、何に着目して読もうとしてたのか改めて考えると、ただひたすら文を追うことしか頭になかったのだとようやく学習しました。
今後も毎日読む上で、今回教えていただいた着眼点など、よく噛み締めて読み進めていこうと思います。
ノートに内容をまとめる際に、ただ真新しいことだけ選出するのではなく、前の日に関わりのある事象と比較し、
次はどんなことが起こりそうかなど、分からなくともまずは自分の頭で何かしら考えます。
S.S@国士舘大学
今起こっていることが分からなければ新しいものは作れない、という言葉にハッとしました。確かに世の中の現状を知らなければ、
人々に楽しんでもらえるコンテンツは生み出せないと気付きました。
また、その洞察力を鍛えるために新聞を読むことは、社会人になるにあたって大事であることも気付かされました。
《自分のペースでコツコツと》
最初は毎日新聞買って読んでアウトプット、できるかな…と心配でした。
しかし、自分が続けられるやり方でやればいいとアドバイスしていただいて、自分のペースでやっていいんだ、と安心しました。
できるかなと思い留まる前に、自分ができる範囲でまずやってみることが大きな一歩になることに気付きました。
・新聞を読む(自分のペースで)
・読んで学んだことを、人と共有する
・疑問点を持ちながら話を聞き、質問を積極的に投げかける
N.J@都留文科大学
--------------------------------------------------------
《源流》
個人面談を数週間前に終え、日経新聞を読み始めたもののやはり内容が難しく、読んでは概要をノートにまとめる毎日。
自分の考えを書き出すなど到底できず、何度か諦めようと思いました。
しかし今回の講義を終えて、何に着目して読もうとしてたのか改めて考えると、ただひたすら文を追うことしか頭になかったのだとようやく学習しました。
今後も毎日読む上で、今回教えていただいた着眼点など、よく噛み締めて読み進めていこうと思います。
ノートに内容をまとめる際に、ただ真新しいことだけ選出するのではなく、前の日に関わりのある事象と比較し、
次はどんなことが起こりそうかなど、分からなくともまずは自分の頭で何かしら考えます。
S.S@国士舘大学
《もったいない》
今回、新聞アウトプットの意義についての話で、新聞には昨日起こった最新情報が書いてあり、
経済や政治などのトピックスが詰まっている宝庫であるとわかりました。今までの事を知ることで未来の予測ができると言われ、
今までぼんやりと新聞を見るだけだったのはとてももったいないことであると気づきました。
就活のためだけでなく、社会人になってからも、新聞を読んで情報を仕入れることは大切であると気づきました。
《舞台としての出版社》
出版社の雰囲気を知ることができるドラマや映画、漫画を教えていただきました。
いくつかは見たことがあったのですが、私が知っているよりもずっと多くの作品に出版社が登場していました。
ドラマや漫画など、満遍なくどのコンテンツでも出版社が舞台のものがあるということに気づきました。
さらに、働く側と経営している側というふたつの視点があるという言葉を聞いて、
ただ見るだけではなく視点を考えて見ることが大切であると気づきました。
・わからない言葉を学ぶつもりで新聞を読む
・少しでも疑問に思ったことは質問する
・ニュースを見ること、新聞を読むことを継続する
Y.H@関西学院大学
--------------------------------------------------------
《新聞の情報》
新聞を読む習慣が私にはなかったため、初めての新聞アウトプットでした。
また、新聞は今の情報を詳しく教えてくれる教科書であると言うことを教えていただき確かにと思いました。
新聞は今だけでなく未来も理解することができるものであるため読む習慣をつけていきたいと思った。
《疑問は学びながら考える》
最後に、質問をする機会があったのですが自分はいつも質問ありますか?という場面において質問を出せません。
自分は学んでいるときに教えてもらっている事だけを飲み込むだけであったため自分ではあまり考えていないのかもしれないと思いました。
・学んでいる時に、自分で考える癖をつける。
・新聞を読むことを習慣づける。
・わからないことは調べる癖をつける。
C.W@東洋大学
--------------------------------------------------------
《空虚になっていました》
新聞アウトプットにおいて、ある人が記事内容と田舎の日本の暮らしとの間にある関連性について話していた。
このように、社会の出来事と実践的な物事との結びつきを意識する考えが自分には欠けていると気づいた。
特に私は抽象的な言葉や概念を多く用いてしまい、議論が机上の空論のような空虚さを纏ってしまう。
彼女のように現実世界との具体的なリンクを意識していかなければ、議論が説得性に欠けてしまうと思わされた。
《新聞はストーリーテラー》
新聞が思考の流れを生みだすように構成されていることを知った。
まずは経済を行う際の基盤である政治、それから経済活動、そして外的要因としての国際問題へと読み手の視点を誘導しているとは見事だ。
社会を一つのストーリーとしてみると、それまで分断されて難しく感じていた事象も理解しやすくなるだろう。
今後は新聞に隠されたそうした社会の流れを意識して読んでいきたい。
・抽象的な言葉を避ける事
・分からない言葉の意味をきちんと調べる事
・質問や意見を積極的に言う事
R.T@同志社大学
今回、新聞アウトプットの意義についての話で、新聞には昨日起こった最新情報が書いてあり、
経済や政治などのトピックスが詰まっている宝庫であるとわかりました。今までの事を知ることで未来の予測ができると言われ、
今までぼんやりと新聞を見るだけだったのはとてももったいないことであると気づきました。
就活のためだけでなく、社会人になってからも、新聞を読んで情報を仕入れることは大切であると気づきました。
《舞台としての出版社》
出版社の雰囲気を知ることができるドラマや映画、漫画を教えていただきました。
いくつかは見たことがあったのですが、私が知っているよりもずっと多くの作品に出版社が登場していました。
ドラマや漫画など、満遍なくどのコンテンツでも出版社が舞台のものがあるということに気づきました。
さらに、働く側と経営している側というふたつの視点があるという言葉を聞いて、
ただ見るだけではなく視点を考えて見ることが大切であると気づきました。
・わからない言葉を学ぶつもりで新聞を読む
・少しでも疑問に思ったことは質問する
・ニュースを見ること、新聞を読むことを継続する
Y.H@関西学院大学
--------------------------------------------------------
《新聞の情報》
新聞を読む習慣が私にはなかったため、初めての新聞アウトプットでした。
また、新聞は今の情報を詳しく教えてくれる教科書であると言うことを教えていただき確かにと思いました。
新聞は今だけでなく未来も理解することができるものであるため読む習慣をつけていきたいと思った。
《疑問は学びながら考える》
最後に、質問をする機会があったのですが自分はいつも質問ありますか?という場面において質問を出せません。
自分は学んでいるときに教えてもらっている事だけを飲み込むだけであったため自分ではあまり考えていないのかもしれないと思いました。
・学んでいる時に、自分で考える癖をつける。
・新聞を読むことを習慣づける。
・わからないことは調べる癖をつける。
C.W@東洋大学
--------------------------------------------------------
《空虚になっていました》
新聞アウトプットにおいて、ある人が記事内容と田舎の日本の暮らしとの間にある関連性について話していた。
このように、社会の出来事と実践的な物事との結びつきを意識する考えが自分には欠けていると気づいた。
特に私は抽象的な言葉や概念を多く用いてしまい、議論が机上の空論のような空虚さを纏ってしまう。
彼女のように現実世界との具体的なリンクを意識していかなければ、議論が説得性に欠けてしまうと思わされた。
《新聞はストーリーテラー》
新聞が思考の流れを生みだすように構成されていることを知った。
まずは経済を行う際の基盤である政治、それから経済活動、そして外的要因としての国際問題へと読み手の視点を誘導しているとは見事だ。
社会を一つのストーリーとしてみると、それまで分断されて難しく感じていた事象も理解しやすくなるだろう。
今後は新聞に隠されたそうした社会の流れを意識して読んでいきたい。
・抽象的な言葉を避ける事
・分からない言葉の意味をきちんと調べる事
・質問や意見を積極的に言う事
R.T@同志社大学
令和2年(2020)【10月8日(木) 】秋の出版編集トレーニング1日目 4期生5組
2020/10/08
コメント (0)
------------------------------------------------------
令和2年(2020)【10月8日(木)】
秋の出版編集トレーニング1日目
4期生5組
--------------------------------------------------------
《解釈と取捨選択》
「他己紹介の感想」の時間でも触れたが、インパクトのある、そして中身のある他己紹介(発表)をするには、
聞いたことをただそのまま伝えるのではなく、聞いた材料をもとに自分なりに解釈して自分の言葉で本人の特徴を言い表す、
ということが必要であることに気付いた。
また、聞いたこと全てを紹介するのではなく、その人の特徴がより表れていると思う部分をピックアップすることの重要さも実感した。
話題を絞って話すことで、一つ一つの話題が濃いものになり、全体としても意義のある内容になることを理解することができた。
また、今日は全体的に時間オーバーで話してしまったが、先ほど述べたポイントを意識することで、それを改善することもできるのではないか思う。
上記の気付きを意識して、発表の場はもちろん、できれば普段の会話の中でも、工夫のある話し方を明日から少しずつでも実践します。
A.U@武庫川女子大学
--------------------------------------------------------
《鏡》
他己紹介をするのは、聞いたことをまとめる力を鍛えるものだと思っていたが、他人から自分がどう見えるかを知ることもできるのだということに気づいた。
また、自分は自分自身が◯◯な人間だと思っていても、それは鏡に映っている自分であり、左右反対の像である。
したがって正面から見てもらえる機会があってよかった。
とにもかくにも、敬語を練習すること。理想としては、最後に木曜メンバーから敬語が上手くなったと言われるくらいにしたい。
T.I@近畿大学
令和2年(2020)【10月8日(木)】
秋の出版編集トレーニング1日目
4期生5組
--------------------------------------------------------
《解釈と取捨選択》
「他己紹介の感想」の時間でも触れたが、インパクトのある、そして中身のある他己紹介(発表)をするには、
聞いたことをただそのまま伝えるのではなく、聞いた材料をもとに自分なりに解釈して自分の言葉で本人の特徴を言い表す、
ということが必要であることに気付いた。
また、聞いたこと全てを紹介するのではなく、その人の特徴がより表れていると思う部分をピックアップすることの重要さも実感した。
話題を絞って話すことで、一つ一つの話題が濃いものになり、全体としても意義のある内容になることを理解することができた。
また、今日は全体的に時間オーバーで話してしまったが、先ほど述べたポイントを意識することで、それを改善することもできるのではないか思う。
上記の気付きを意識して、発表の場はもちろん、できれば普段の会話の中でも、工夫のある話し方を明日から少しずつでも実践します。
A.U@武庫川女子大学
--------------------------------------------------------
《鏡》
他己紹介をするのは、聞いたことをまとめる力を鍛えるものだと思っていたが、他人から自分がどう見えるかを知ることもできるのだということに気づいた。
また、自分は自分自身が◯◯な人間だと思っていても、それは鏡に映っている自分であり、左右反対の像である。
したがって正面から見てもらえる機会があってよかった。
とにもかくにも、敬語を練習すること。理想としては、最後に木曜メンバーから敬語が上手くなったと言われるくらいにしたい。
T.I@近畿大学
《インパクトが重要》
伝える相手にイメージが湧きやすくするためにもインパクトがあるキャッチコピーや内容を話すことが大切だということが分かりました。
また、先に結論を言うと言うのは文章を書くときには意識していたことですが、話すときには意識していなかったので心掛けたいと思います。
他の人の他己紹介を聞いているととても要約が上手で自分の感じた印象も混ぜて話されていたので、私自身も簡潔に要約してこれからは話せるようにしたいです。
また、緊張せずにリラックスして素の自分を出せるように場慣れしていきたいです。
K.I@相模女子大学
--------------------------------------------------------
《説明と選択》
書籍紹介と他己紹介を通じて、自分が脳内で考えていることを忠実に説明するのは難しいと気づいた。
自分の考えている内容が全員にしかも時間内に伝わるようにするには、自分の脳内にある必要な情報と不必要な情報を取捨選択することが大切であると考える。
・人の話したことはメモをする
・思考をアウトプットする癖をつける
N.O@愛知大学
--------------------------------------------------------
《伝えるって難しい》
他己紹介をしてみて、自分の伝える力の乏しさに気づいた。
内容を簡潔にまとめて制限時間内に発表する、ということはとても難しかった。
自分が得た情報から取捨選択し、相手に分かりやすく伝えるにはまだまだ練習が必要であると学んだ。
また、質問も単に聞くだけではなく、相手から聞き出したい情報は何かを考えながらする必要があることを学んだ。
《インパクトある発表を》
キャッチコピー力が足りないことに気づいた。相手の関心を引きつけるには、インパクトが大事であると学んだ。
続きが気になるような、どういうこと?と思わせるキャッチコピーを考えれるようになれば、より話が面白くなることを学んだ。
・結論は最初に述べる
・制限時間内に伝わるようにまとめる
・インプットしたものはアウトプットする癖をつける
・色々なことに疑問を持つ
N.J@都留文科大学
伝える相手にイメージが湧きやすくするためにもインパクトがあるキャッチコピーや内容を話すことが大切だということが分かりました。
また、先に結論を言うと言うのは文章を書くときには意識していたことですが、話すときには意識していなかったので心掛けたいと思います。
他の人の他己紹介を聞いているととても要約が上手で自分の感じた印象も混ぜて話されていたので、私自身も簡潔に要約してこれからは話せるようにしたいです。
また、緊張せずにリラックスして素の自分を出せるように場慣れしていきたいです。
K.I@相模女子大学
--------------------------------------------------------
《説明と選択》
書籍紹介と他己紹介を通じて、自分が脳内で考えていることを忠実に説明するのは難しいと気づいた。
自分の考えている内容が全員にしかも時間内に伝わるようにするには、自分の脳内にある必要な情報と不必要な情報を取捨選択することが大切であると考える。
・人の話したことはメモをする
・思考をアウトプットする癖をつける
N.O@愛知大学
--------------------------------------------------------
《伝えるって難しい》
他己紹介をしてみて、自分の伝える力の乏しさに気づいた。
内容を簡潔にまとめて制限時間内に発表する、ということはとても難しかった。
自分が得た情報から取捨選択し、相手に分かりやすく伝えるにはまだまだ練習が必要であると学んだ。
また、質問も単に聞くだけではなく、相手から聞き出したい情報は何かを考えながらする必要があることを学んだ。
《インパクトある発表を》
キャッチコピー力が足りないことに気づいた。相手の関心を引きつけるには、インパクトが大事であると学んだ。
続きが気になるような、どういうこと?と思わせるキャッチコピーを考えれるようになれば、より話が面白くなることを学んだ。
・結論は最初に述べる
・制限時間内に伝わるようにまとめる
・インプットしたものはアウトプットする癖をつける
・色々なことに疑問を持つ
N.J@都留文科大学
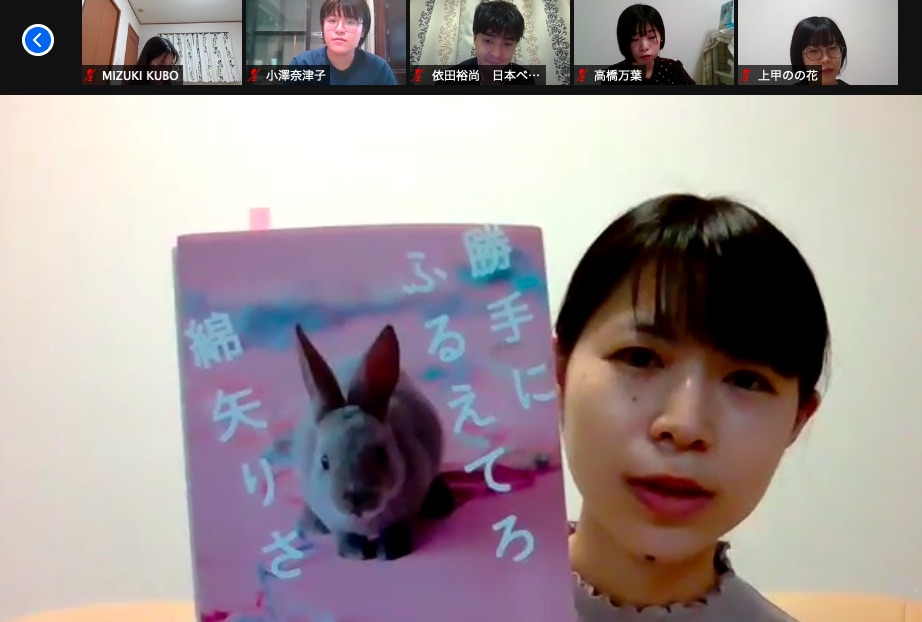 《発想力は、強い》
《発想力は、強い》本の紹介でさまざまな本が紹介されていましたが、とくに板持君の教科書を持ってくるという発想に驚かされました。
アピール文を考える際にも、この他人がすぐには思いつかない独自の発想が大切だと感じました。
また、上甲さんの紹介のときに、世界で5番目に読まれているという情報に引き付けられたので、
どのような順番で伝えるかという発想力も肝心であることがわかりました。
自分の話し方のクセ、弱いところを周りの方に聞いて、まず知るところから始めます。
また、他の方の話し方をよく観察して、良いところを盗んで真似していきます。
M.T@都留文科大学
--------------------------------------------------------
《自分は堂々とした人だった!?》
私は自分の話をするのが大好きだ。
しかし、と同時に話を聞くのも大好きだ。だからずかずかと質問するし、自分も答える。
それを自分自身積極性はあるかもしれないが、すこしばかり図々しいことだと思っていた。
しかし彼女は私を紹介する際、私を堂々とした人だったと語った。正直にとても嬉しかった。
自身堂々とする意識は全くせずただその場を楽しんで話をしていただけなのに、そんな風に感じていたとはびっくりした。
それが大きな発見であり、楽しいと思った。ではそんな他己紹介を聞いた他の方の目にはどのように私が写ったのか次に気になるところだ。
思いをしっかり人へ伝える方法を一から学びたい。そのためにまずは上手い人の話をしっかり聞いてなぜ上手いのかそのわけを考えようと思った。
M.K@清泉女子大学
令和2年(2020)【10月6日(火) 】秋の出版編集トレーニング1日目 4期生4組
2020/10/06
コメント (0)
------------------------------------------------------
令和2年(2020)【10月6日(火)】
秋の出版編集トレーニング1日目
4期生4組
--------------------------------------------------------
《時は有限 ~好きな食べ物は?←必要か否か~》
自己紹介、書籍紹介、他者紹介、いずれにしても強く意識させられたのは目安となる時間というものです。特に他己紹介では自分が質問できる時間、
情報を得られる時間というのはたったの5分という中で、初めて顔を合わせた相手を紹介しなければならないという状況。
いかに質の高い質問ができるかということの重要性というものを学びました。相手の答えを聞く時間も合わせると5分で質問できる量は多くて3つ、
その中で彼、彼女はこういう人ですと第三者に伝えなくてはならないとなると自分の質問にも、筋道というものが必要になってくると感じました。
ある程度の返答の推測と誘導という技術が身につけられれば、その後のそれらをまとめるという作業にも繋げやすいのではないかと考えました。
それがどういう意図をもってされたのか、一手二手先を読んだ質問をできるよう経験を積み重ねていけるようにしたいです。
また、普段から時間感覚というものを身につけるためある程度意識していこうと思いました。
普段の生活から時間感覚を養うために、何かを始める前、友達と話す前など、時間をしっかりと確認してから行動に移していこうと考えました。
また、普段の大学の講義などでも積極的に質問を頭では考えておく癖をつけたいと思いました。
質問がないということは、それだけある物事に対して興味、関心を持っていないということにつながるというのは本当にその通りだと思いました。
また、その質問もなんでもいいからというよりかは、しっかりと意図を持った質問が考えつくように訓練していきたいです。
限られた時間の有効活用、質問への意識という点の向上を目指し、意識して実行していきます。
R.S@明治学院大学
--------------------------------------------------------
《伝えるための取捨選択》
他者からの自分の発表に関する感想を聞いて、また、自分の発表を振り返って、時間内に自分の意図を伝えることの難しさを痛感しました。
伝えたいことを全て詰め込むのではなく、要点を絞ってより印象に残るような発表をすることが大事であると思い至りました。
限られた時間内に自分の意図や主張を相手に伝えるため、日頃から時間を決めて発表の練習をしたいと思います。
情報のインプットだけでなく、アウトプットの訓練をすることで、仕事において必要なコミュニケーション能力向上の一助としたいです。
R.M@武蔵野大学
--------------------------------------------------------
《時間内にまとめる力》
今回は初めてのトレーニングであり、決められた時間の中で発表することに慣れておりませんでした。
私は発表をする際、緊張で言いたいことが言えずに時間を余らせがちですが、
逆に時間を多く使ってしまっても伝えたいことが伝わらないこともあると改めて感じました。
《聞きたいことを引き出す力》
今回他己紹介では、ペアになった相手に質問をして、その内容からその人を紹介するということを行いました。
しかし、どのような質問をすれば相手のことを知ることができるかわからなかったので、聞きたいことを上手にまとめる力も重要だと感じました。
・伝えたいことは簡潔に分かりやすく伝える
・インパクトのある言葉で伝える
・人の話を聞くときはただ聞くだけでなく、質問をして内容を深める
Y.S@東洋大学
--------------------------------------------------------
前回の説明会の際に行った自己紹介や、書籍紹介の際に自らの言いたいことや順番などが上手くまとまらず猛省しました。
そうして今回を迎えるにあたって、自己紹介などの下準備をメモに残すなど、あらかじめ用意しました。
「これで上手くいく」と少し自信を持って臨んだのですが、結果は散々。メモ丸読みかつ支離滅裂になってしまいました。
大事だったのは「ただの用意する」のではなく、どれだけそれまでに熟慮してきたのかだったのだと気付かされました。
よく考え、それに対して理解を深めることが本当の「準備」だったのだと。
今後もインターンを受講するにあたって、メモを用意しなくとも、
発信できるぐらいの「最高の準備」を実行していきたいと思います。
S.S@国士舘大学
--------------------------------------------------------
《表現力》
他の人や本を紹介するときに、それをいかに面白く紹介できるか、人の気を引ける話始めができるかなどが、私にはまだ足りていませんでした。
人の気を引くためには、まずは印象的なキャッチコピーを考えることが大事だと気づきました。
また、今回はパッと質問を出すのが難しく、やはり普段から何事にも興味を持って、なぜそうなるのだろうかと考える癖をつけるべきだと感じました。
そうすることで、思考も柔軟にして表現力をつけたいです。
また、人の発表を聞いて、他の人の表現力に驚いたので、これからは他の人のいいところを吸収できるよう尽力します。
また、発表はただやり過ごすだけでなく、人にわかりやすく伝えることを意識することが大切だと感じました。
・新しい話題を積極的に取り入れる
・物事をわかりやすく、興味を持ってもらえるように伝える方法を考える
・何にでも疑問を持つ
・本や雑誌を読んで表現力と語彙を鍛える
M.K@関西大学
--------------------------------------------------------
《インパクトを作り出す》
本の紹介・他己紹介で共通して思ったことですが、他の人を引きつけるためにはインパクトを残すキーワードを用いることが大切であると思いました。
続きが聞きたいと思えるような、心をつかむ言葉を冒頭に持ってくることが大切であると感じました。
《1分間はどれくらい?》
自分の発表をよりはっきりと伝えるには、時間を気にして簡潔にまとめるということが大事であると気づきました。
さらに、他己紹介の際にも5分間を上手く使って相手から話を聞き出さないといけないとわかりました。
今回は1人あたりの時間が決められていました。しかし、時間が決められている時だけでなく、そうでない時にも時間を意識しなければいけないと思いました。
・発表の際、言いたいことをまとめるだけでなく、その中からインパクトを与えるキーワードを作り出すということを意識していきます。
・時間感覚を養うために、日頃から時間を気にして生活します。
・取材の聞き取りなど、自分が聞き取り役に回った時には主体的に相手に質問をしていきます。
U.H@関西学院大学
--------------------------------------------------------
《文章をまとめる》
他己紹介を行った際に、自分はそれなりに多くのことを聞き出せたのですが、それをまとめる力が無くてはいくら情報があっても意味がないと感じました。
《取捨選択》
自分が聞き出した情報は必要なのかそうではないのかわからないと感じました。
様々なことを聞くことが出来たのですが、それは他己紹介に必要なかっだと感じる情報が多かったです。
これが無ければ1つのことを深く聞くことが出来てより深い内容になったはずです。
また、書籍の紹介も簡潔に内容をまとめる必要があると気づきました。無駄は省くべきであると思いました。
自分には、情報をまとめる力が少ないです。それを補う為に、内容を理解して簡潔に説明する練習をしてみようと思います。
また、語彙力が足りていないため、本を読む習慣や新聞を読む習慣をつけたいです。
C.W@東洋大学
--------------------------------------------------------
《“すごい"はすごくない》
自己紹介や本紹介において「すごい」という飾りの言葉を濫用してしまった。
提示してくださった心得の中にも禁句として「めっちゃ」という語が挙げられていたが、
「すごい」も同様の効果を持つと感じた。アドリブで話していると、繋ぎの言葉として「すごい」を使ってしまう。
語彙が少ないことが聞き手に伝わってしまうので、意識して避けるべきだと気づいた。どう"すごい"のか、なぜ"すごい"のかといった具体的修飾を心掛けたい。
《案外楽しいぞ》
今回、他己紹介のために初対面の人と一対一で話すことになった。正直に言うと、ぎょっとした。ほんの1時間くらいの仲の人と一対一は、
会話が続かず気まずい時間が過ぎるのが目に見えている、と思った。しかしその予想は裏切られた。
相手と探り合いながらも、距離を詰めていく感覚は案外楽しいものだったのだ。
もちろん相手のアプローチもあっただろうが、こちらから全力で心を開いて挑めば、会話は怖いものではないのだと学んだ。
・発表の場において「すごい」「とても」といった内容空虚な修飾語は使わないこと
・回りくどい表現を使ったり、一つの話が長かったりしないようにすること
・冒頭に内容の要約を入れること
R.T@同志社大学
--------------------------------------------------------
令和2年(2020)【10月6日(火)】
秋の出版編集トレーニング1日目
4期生4組
--------------------------------------------------------
《時は有限 ~好きな食べ物は?←必要か否か~》
自己紹介、書籍紹介、他者紹介、いずれにしても強く意識させられたのは目安となる時間というものです。特に他己紹介では自分が質問できる時間、
情報を得られる時間というのはたったの5分という中で、初めて顔を合わせた相手を紹介しなければならないという状況。
いかに質の高い質問ができるかということの重要性というものを学びました。相手の答えを聞く時間も合わせると5分で質問できる量は多くて3つ、
その中で彼、彼女はこういう人ですと第三者に伝えなくてはならないとなると自分の質問にも、筋道というものが必要になってくると感じました。
ある程度の返答の推測と誘導という技術が身につけられれば、その後のそれらをまとめるという作業にも繋げやすいのではないかと考えました。
それがどういう意図をもってされたのか、一手二手先を読んだ質問をできるよう経験を積み重ねていけるようにしたいです。
また、普段から時間感覚というものを身につけるためある程度意識していこうと思いました。
普段の生活から時間感覚を養うために、何かを始める前、友達と話す前など、時間をしっかりと確認してから行動に移していこうと考えました。
また、普段の大学の講義などでも積極的に質問を頭では考えておく癖をつけたいと思いました。
質問がないということは、それだけある物事に対して興味、関心を持っていないということにつながるというのは本当にその通りだと思いました。
また、その質問もなんでもいいからというよりかは、しっかりと意図を持った質問が考えつくように訓練していきたいです。
限られた時間の有効活用、質問への意識という点の向上を目指し、意識して実行していきます。
R.S@明治学院大学
--------------------------------------------------------
《伝えるための取捨選択》
他者からの自分の発表に関する感想を聞いて、また、自分の発表を振り返って、時間内に自分の意図を伝えることの難しさを痛感しました。
伝えたいことを全て詰め込むのではなく、要点を絞ってより印象に残るような発表をすることが大事であると思い至りました。
限られた時間内に自分の意図や主張を相手に伝えるため、日頃から時間を決めて発表の練習をしたいと思います。
情報のインプットだけでなく、アウトプットの訓練をすることで、仕事において必要なコミュニケーション能力向上の一助としたいです。
R.M@武蔵野大学
--------------------------------------------------------
《時間内にまとめる力》
今回は初めてのトレーニングであり、決められた時間の中で発表することに慣れておりませんでした。
私は発表をする際、緊張で言いたいことが言えずに時間を余らせがちですが、
逆に時間を多く使ってしまっても伝えたいことが伝わらないこともあると改めて感じました。
《聞きたいことを引き出す力》
今回他己紹介では、ペアになった相手に質問をして、その内容からその人を紹介するということを行いました。
しかし、どのような質問をすれば相手のことを知ることができるかわからなかったので、聞きたいことを上手にまとめる力も重要だと感じました。
・伝えたいことは簡潔に分かりやすく伝える
・インパクトのある言葉で伝える
・人の話を聞くときはただ聞くだけでなく、質問をして内容を深める
Y.S@東洋大学
--------------------------------------------------------
前回の説明会の際に行った自己紹介や、書籍紹介の際に自らの言いたいことや順番などが上手くまとまらず猛省しました。
そうして今回を迎えるにあたって、自己紹介などの下準備をメモに残すなど、あらかじめ用意しました。
「これで上手くいく」と少し自信を持って臨んだのですが、結果は散々。メモ丸読みかつ支離滅裂になってしまいました。
大事だったのは「ただの用意する」のではなく、どれだけそれまでに熟慮してきたのかだったのだと気付かされました。
よく考え、それに対して理解を深めることが本当の「準備」だったのだと。
今後もインターンを受講するにあたって、メモを用意しなくとも、
発信できるぐらいの「最高の準備」を実行していきたいと思います。
S.S@国士舘大学
--------------------------------------------------------
《表現力》
他の人や本を紹介するときに、それをいかに面白く紹介できるか、人の気を引ける話始めができるかなどが、私にはまだ足りていませんでした。
人の気を引くためには、まずは印象的なキャッチコピーを考えることが大事だと気づきました。
また、今回はパッと質問を出すのが難しく、やはり普段から何事にも興味を持って、なぜそうなるのだろうかと考える癖をつけるべきだと感じました。
そうすることで、思考も柔軟にして表現力をつけたいです。
また、人の発表を聞いて、他の人の表現力に驚いたので、これからは他の人のいいところを吸収できるよう尽力します。
また、発表はただやり過ごすだけでなく、人にわかりやすく伝えることを意識することが大切だと感じました。
・新しい話題を積極的に取り入れる
・物事をわかりやすく、興味を持ってもらえるように伝える方法を考える
・何にでも疑問を持つ
・本や雑誌を読んで表現力と語彙を鍛える
M.K@関西大学
--------------------------------------------------------
《インパクトを作り出す》
本の紹介・他己紹介で共通して思ったことですが、他の人を引きつけるためにはインパクトを残すキーワードを用いることが大切であると思いました。
続きが聞きたいと思えるような、心をつかむ言葉を冒頭に持ってくることが大切であると感じました。
《1分間はどれくらい?》
自分の発表をよりはっきりと伝えるには、時間を気にして簡潔にまとめるということが大事であると気づきました。
さらに、他己紹介の際にも5分間を上手く使って相手から話を聞き出さないといけないとわかりました。
今回は1人あたりの時間が決められていました。しかし、時間が決められている時だけでなく、そうでない時にも時間を意識しなければいけないと思いました。
・発表の際、言いたいことをまとめるだけでなく、その中からインパクトを与えるキーワードを作り出すということを意識していきます。
・時間感覚を養うために、日頃から時間を気にして生活します。
・取材の聞き取りなど、自分が聞き取り役に回った時には主体的に相手に質問をしていきます。
U.H@関西学院大学
--------------------------------------------------------
《文章をまとめる》
他己紹介を行った際に、自分はそれなりに多くのことを聞き出せたのですが、それをまとめる力が無くてはいくら情報があっても意味がないと感じました。
《取捨選択》
自分が聞き出した情報は必要なのかそうではないのかわからないと感じました。
様々なことを聞くことが出来たのですが、それは他己紹介に必要なかっだと感じる情報が多かったです。
これが無ければ1つのことを深く聞くことが出来てより深い内容になったはずです。
また、書籍の紹介も簡潔に内容をまとめる必要があると気づきました。無駄は省くべきであると思いました。
自分には、情報をまとめる力が少ないです。それを補う為に、内容を理解して簡潔に説明する練習をしてみようと思います。
また、語彙力が足りていないため、本を読む習慣や新聞を読む習慣をつけたいです。
C.W@東洋大学
--------------------------------------------------------
《“すごい"はすごくない》
自己紹介や本紹介において「すごい」という飾りの言葉を濫用してしまった。
提示してくださった心得の中にも禁句として「めっちゃ」という語が挙げられていたが、
「すごい」も同様の効果を持つと感じた。アドリブで話していると、繋ぎの言葉として「すごい」を使ってしまう。
語彙が少ないことが聞き手に伝わってしまうので、意識して避けるべきだと気づいた。どう"すごい"のか、なぜ"すごい"のかといった具体的修飾を心掛けたい。
《案外楽しいぞ》
今回、他己紹介のために初対面の人と一対一で話すことになった。正直に言うと、ぎょっとした。ほんの1時間くらいの仲の人と一対一は、
会話が続かず気まずい時間が過ぎるのが目に見えている、と思った。しかしその予想は裏切られた。
相手と探り合いながらも、距離を詰めていく感覚は案外楽しいものだったのだ。
もちろん相手のアプローチもあっただろうが、こちらから全力で心を開いて挑めば、会話は怖いものではないのだと学んだ。
・発表の場において「すごい」「とても」といった内容空虚な修飾語は使わないこと
・回りくどい表現を使ったり、一つの話が長かったりしないようにすること
・冒頭に内容の要約を入れること
R.T@同志社大学
--------------------------------------------------------
令和2年(2020)【9月12日(土) 】夏の出版編集トレーニング6日目 4期生3組
2020/09/12
コメント (0)
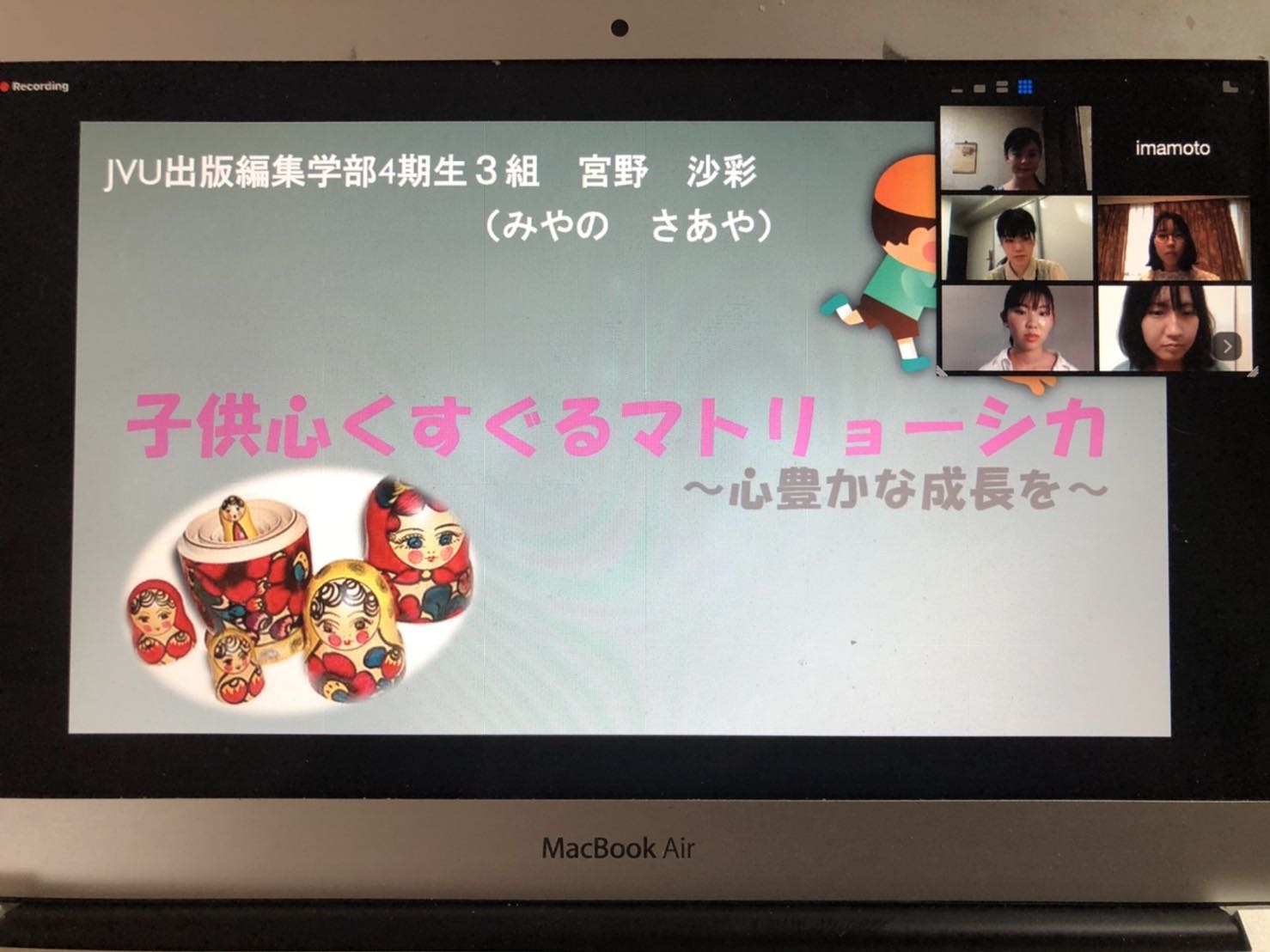
------------------------------------------------------
令和2年(2020)【9月12日(土)】
夏の出版編集トレーニング6日目
4期生3組
--------------------------------------------------------
《知ることの喜び》
「意外と同じだな」「意外と違うんだな」、どちらの感想を持つときも、それは嬉しさがともないました。
SNSの普及もあり、知られることの喜びに目が向きやすいものですが、人を知りたいと思い、そして知ることはこんなにも自らを満たしてくれるものなのかと気付きました。
《書ける人になればいい》
話し上手にならなければと思ったり、もう無理なのだろうと諦めたり、「話す」というテーマには振り回されてきました。
今でも話し上手な人には羨ましさを感じますし、さぞ生きやすいだろうと嫉妬もします。でも、もう振り回されなくてもいい気もしています。
それは、私が書く人だからです。皆得手不得手はあるもの。私は今書く人で、そしてこれからは書ける人になります。
ただ、そうして生き方を絞っていく中で、気を付けなければならないこともあります。それは視野を広く保っておくことです。
気付きをたくさん得るためには、不得手の分野まで目が届く必要があります。
・気付きを外部に求める
・話をしてみる
・よく聞く
・継続的に書く
・夢に誇りを持つ
《1週間を終えて》
私がかつて話すことを怖がるようになっていったのは、どのような経緯からなのかを思い返してみました。
話せなくなったのは、自信を失った時期と一致していました。話す内容が相手にとって異質だったり面白くなかったりして、
不快にさせるのではないかと懸念し、私は次第に話をすることから遠ざかっていました。
今回のインターンを通して、異質は個性の強さの現れだと思いましたし、相手にとって面白くないものも自分にとって面白いなら、話すことを控える理由にはならないとも感じました。
しかも、“面白くない"は対象に備わった特徴ではありません。私の話し方次第で、相手にとって面白いものに変わる可能性もあります。
そのような、ものの捉え方を操作、誘導するのがマスコミ業界の醍醐味とも言えるでしょう。
社会経験の浅さから、辛い、という感想も持ったインターンでした。それでも今晴れ晴れとした気分でいられるのは同志がいたからです。
刺激し合い、互いを知りながら、同じ目標を掲げ突き進む。短い期間ではありましたが、俗に言う青春のようなものが詰まった6日間でした。
関わっていただいた皆様に感謝しています。
特にスタッフのみなさんにはたくさんの優しいお言葉をいただいて、課題をこなす上での糧となりました。ありがとうございました。
大変お世話になりました。
T.T@東北大学
令和2年(2020)【9月12日(土)】
夏の出版編集トレーニング6日目
4期生3組
--------------------------------------------------------
《知ることの喜び》
「意外と同じだな」「意外と違うんだな」、どちらの感想を持つときも、それは嬉しさがともないました。
SNSの普及もあり、知られることの喜びに目が向きやすいものですが、人を知りたいと思い、そして知ることはこんなにも自らを満たしてくれるものなのかと気付きました。
《書ける人になればいい》
話し上手にならなければと思ったり、もう無理なのだろうと諦めたり、「話す」というテーマには振り回されてきました。
今でも話し上手な人には羨ましさを感じますし、さぞ生きやすいだろうと嫉妬もします。でも、もう振り回されなくてもいい気もしています。
それは、私が書く人だからです。皆得手不得手はあるもの。私は今書く人で、そしてこれからは書ける人になります。
ただ、そうして生き方を絞っていく中で、気を付けなければならないこともあります。それは視野を広く保っておくことです。
気付きをたくさん得るためには、不得手の分野まで目が届く必要があります。
・気付きを外部に求める
・話をしてみる
・よく聞く
・継続的に書く
・夢に誇りを持つ
《1週間を終えて》
私がかつて話すことを怖がるようになっていったのは、どのような経緯からなのかを思い返してみました。
話せなくなったのは、自信を失った時期と一致していました。話す内容が相手にとって異質だったり面白くなかったりして、
不快にさせるのではないかと懸念し、私は次第に話をすることから遠ざかっていました。
今回のインターンを通して、異質は個性の強さの現れだと思いましたし、相手にとって面白くないものも自分にとって面白いなら、話すことを控える理由にはならないとも感じました。
しかも、“面白くない"は対象に備わった特徴ではありません。私の話し方次第で、相手にとって面白いものに変わる可能性もあります。
そのような、ものの捉え方を操作、誘導するのがマスコミ業界の醍醐味とも言えるでしょう。
社会経験の浅さから、辛い、という感想も持ったインターンでした。それでも今晴れ晴れとした気分でいられるのは同志がいたからです。
刺激し合い、互いを知りながら、同じ目標を掲げ突き進む。短い期間ではありましたが、俗に言う青春のようなものが詰まった6日間でした。
関わっていただいた皆様に感謝しています。
特にスタッフのみなさんにはたくさんの優しいお言葉をいただいて、課題をこなす上での糧となりました。ありがとうございました。
大変お世話になりました。
T.T@東北大学
【総括】
《身をもって学んだ多様性の意味》
私は将来、起業するのが目標です。自分のやりたいことを実現させ、自分だけで成し遂げたいと思っていました。
しかし今回皆の発表を聞いて、やはり、自分だけよりも皆で視点を共有し合ってなにかを完成させるほうが強いと感じました。
皆それぞれ発表の良さが違ったり、目の付け所やこだわりが異なっていて、お互いの発表のいいところや欠点を指摘し合うことができました。
自分の考えにないことを知るのは皆がいないとできないことです。
また、今回のインターンシップを通して、集団のなかで個性を出し合えるようになるには、皆が意見を言える環境を作ることが大事だと感じました。
今回のメンバーは皆意見を尊重してくれる人たちで、頷きながら話を聞いてくれたり、目を見て話を聞いてくれたり、のびのびと意見を言える雰囲気をつくってくれました。
さらに、それぞれの個性と熱量があって、刺激をくれました。これからもこのように素晴らしい環境に属せるよう、積極的に外と関わっていこうと思います。
・毎日、面白いネタをみつけて文章にする
・積極的に集団に参加する
・自分の意見を発表する場を持つ
・常に実現したいコンテンツについて考える
M.S@東京理科大学
《身をもって学んだ多様性の意味》
私は将来、起業するのが目標です。自分のやりたいことを実現させ、自分だけで成し遂げたいと思っていました。
しかし今回皆の発表を聞いて、やはり、自分だけよりも皆で視点を共有し合ってなにかを完成させるほうが強いと感じました。
皆それぞれ発表の良さが違ったり、目の付け所やこだわりが異なっていて、お互いの発表のいいところや欠点を指摘し合うことができました。
自分の考えにないことを知るのは皆がいないとできないことです。
また、今回のインターンシップを通して、集団のなかで個性を出し合えるようになるには、皆が意見を言える環境を作ることが大事だと感じました。
今回のメンバーは皆意見を尊重してくれる人たちで、頷きながら話を聞いてくれたり、目を見て話を聞いてくれたり、のびのびと意見を言える雰囲気をつくってくれました。
さらに、それぞれの個性と熱量があって、刺激をくれました。これからもこのように素晴らしい環境に属せるよう、積極的に外と関わっていこうと思います。
・毎日、面白いネタをみつけて文章にする
・積極的に集団に参加する
・自分の意見を発表する場を持つ
・常に実現したいコンテンツについて考える
M.S@東京理科大学
《ターゲットのTPOを考える》
自分のコンテンツ発表の際、私は、女子高生というターゲットだけでも充分絞られると思いました。
しかし、女子高生の他のターゲットとの違いは、他の層は1人で読むことが多いが、女子高生はグループで読むことが多いという点です。
ターゲットがどんな状況で読むのか細かくTPOを考え、その上で幅広い状況で読めるものを作らなければならないと思いました。
・これからも毎日新聞を読む
・面白い文章や構成をノートに書く
・ひとつのことに対して沢山疑問を持つ
【1週間の総括】
《心は縮こまるな》
1日目の終わりに元々自分に自信が持てなかった私は、何も出来なかったことに対して悔しいと思いました。
自分の言いたいことがうまく伝えられなかった事も大いに含まれていると思います。
しかし、2日目に「もっとガツンと自分を大きく見せなさい」という言葉で私の中の何かが変わりました。
自分をもっと大きく見せなければ、自分の長所も欠点も分かりません。自分だけでなく周りの人からも気づいてもらえません。
これからの生活でも自分はこういう人間だと大きく見せることで色々な気づきを探します。
《好きの気づき》
今回のインターンで自分はあれこれ色んなことを考えることが好きなんだと改めて感じ、自分の考えで世の中をもっと動かしたいと強く思いました。この気持ちを大切に、さらに自分の足りないものをもっと補いたいと思いました。
1週間ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
S.F@京都女子大学
自分のコンテンツ発表の際、私は、女子高生というターゲットだけでも充分絞られると思いました。
しかし、女子高生の他のターゲットとの違いは、他の層は1人で読むことが多いが、女子高生はグループで読むことが多いという点です。
ターゲットがどんな状況で読むのか細かくTPOを考え、その上で幅広い状況で読めるものを作らなければならないと思いました。
・これからも毎日新聞を読む
・面白い文章や構成をノートに書く
・ひとつのことに対して沢山疑問を持つ
【1週間の総括】
《心は縮こまるな》
1日目の終わりに元々自分に自信が持てなかった私は、何も出来なかったことに対して悔しいと思いました。
自分の言いたいことがうまく伝えられなかった事も大いに含まれていると思います。
しかし、2日目に「もっとガツンと自分を大きく見せなさい」という言葉で私の中の何かが変わりました。
自分をもっと大きく見せなければ、自分の長所も欠点も分かりません。自分だけでなく周りの人からも気づいてもらえません。
これからの生活でも自分はこういう人間だと大きく見せることで色々な気づきを探します。
《好きの気づき》
今回のインターンで自分はあれこれ色んなことを考えることが好きなんだと改めて感じ、自分の考えで世の中をもっと動かしたいと強く思いました。この気持ちを大切に、さらに自分の足りないものをもっと補いたいと思いました。
1週間ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
S.F@京都女子大学
《さまざまな角度から》
今日のコンテンツ発表を通して、需要ある商品を自分で考えることの難しさを実感しました。
自分では良いと思う物が、世間の心にはあまり届かなかったり、不人気だったり‥。
若者の声だけでなく、幅広い年代・立場の人と交流することが大切だと感じます。
そうする事でアイデアが浮かぶと思います。
《常識」を覆せ!》
世間一般に浸透している、しきたりや習慣を
ただ享受するのではなく一歩違った視点から考えてみることが大切だと思いました。
【総括】
トレーニングを通して
人前で意見を言うことへの抵抗感が無くなりました。
新聞アウトプットでは、気付きの共有が出来て
ひとりで新聞を読むよりも充実した時間になりました。
・新聞を鵜呑みにしない
・気付いたことがあったら物怖じせず、口にする
・パワポの技術を上げる
C.I@専修大学
今日のコンテンツ発表を通して、需要ある商品を自分で考えることの難しさを実感しました。
自分では良いと思う物が、世間の心にはあまり届かなかったり、不人気だったり‥。
若者の声だけでなく、幅広い年代・立場の人と交流することが大切だと感じます。
そうする事でアイデアが浮かぶと思います。
《常識」を覆せ!》
世間一般に浸透している、しきたりや習慣を
ただ享受するのではなく一歩違った視点から考えてみることが大切だと思いました。
【総括】
トレーニングを通して
人前で意見を言うことへの抵抗感が無くなりました。
新聞アウトプットでは、気付きの共有が出来て
ひとりで新聞を読むよりも充実した時間になりました。
・新聞を鵜呑みにしない
・気付いたことがあったら物怖じせず、口にする
・パワポの技術を上げる
C.I@専修大学
《自分であること》
「最後に自分たちで企画を作ってもらいます」
インターン1日目、そう伝えられた時漠然と不安が襲ってきた。
はじめてのインターン、はじめての人たち、それらに囲まれ何より久々のパンプスでかかとがひりひりと痛みが増してきているような気もしてきて、どんどん気分が落ち込んでいったのを覚えている。
元より、自分をひけらかすことや話すことが苦手だった。頭の中でよく考えて言葉にするのならまだしも、
声に出すとなると短い時間で整理して相手に伝えなければいけないという行程がどうにも昔から得意になれなかったのだ。
そのせいもあって、アイデアは全く浮かばないし、他の子達はハキハキと自分の意見を話しているし…で、自分と周りの距離がどんどん開いていっているような感覚に陥っていた。
しかし、新聞アウトプットや自己紹介、他己紹介を通じて、半強制に自分の意見を言うという状況になった時、はじめはオドオドとしていたがどんどん自信がついていったのだ。
自分が誰だか分からなかった。けれど、「私ってこう思ってたんだ」「こう、見られているんだ」
「今こんなことが起きているんだ、ならこれはどうなんだろう」って新しい視点や見方が開けていくことがすごく楽しいことに気がついたのだ。
自分を理解するためにまずは声に出すこと。口から出た情報が耳から入ってきてようやくインプットされる。
そう感じた。コンテンツも、出来がどうであれ、私が将来やりたいこと、やっていかなければいけないことについての根っこができたかとは思う。あとはその芽を出すことができるか、そして育てられるのかが勝負だ。
《他人の物語》
人ってやっぱり自分が一番だから、自分目線で物事を捉えてしまう。意見を聞くときも、「この子がこう思うなら私はこう思うな」、
「この子はこんな性格なんだな。私とはこう違うな」といった風に私が、私とは、私よりと勝手に思考がいってしまうのだ。断じて自分大好きってわけではないので、
敢えて訂正はしておく。そうなれば、周りの視野が狭くなってしまうのだと考えた。そこで私は、他人の話をその人の物語として、まるで小説を読んでいるかのように思うことにした。
小説の内容は、かなり学ぶことが多く知識として自分の中に浸透する。それを対人に置き換えてみた。それは、視野や思考の範囲を広げることへ導いた。
確かに、自分との比較は大事だ。しかし、今回他の方のコンテンツ発表の中で、先日の自己紹介の内容と絡ませながら聞いていると、
この人はこんな過去があったから今こういう企画を立てているんだ、だからこそこんな企画が生まれたんだ、というような自分一人で芽生えなかった面白いアイデアがどんどん浮上してきたのだ。そういう意味で、他人の話を聞いていくことも大事だなと思った。
《松陰先生》
最後のお話の中で、吉田松陰が出てきたが、その中でも「死ぬ前にやりたいことは何だ?」という質問に「どうせ死ぬなら、世の中のことを少しでも知ってから死にたい。だから本を読ませてください」と答えたというお話を聞いて思ったことだ。私は中学生くらいのとき、「死ぬ」ということについて夜も眠れないほどの恐怖に陥ったことがある。
特に病院に通う、というほど重症ではないので重くは捉えないでほしい。ずっと死んだらどうなるんだろう?と大学生になってまで考えていたとき、「死ぬときにはじめて気づく人生で大切なこと33」という本に出会った。その中にあった言葉で印象に残っているのが、「生きていることは死ぬまでの暇つぶし。死ぬことを目的として生きている」というものだ。つまり生きるということは自由に楽しむ機会が与えられているだけなのだと。松陰先生が言いたかったのもこんな感じなのかな、と勝手に想像した。死ぬという目的を果たす前に、与えられた機会を充分に利用して、世界をより知りたいと思ったのではないだろうか。
松陰先生を語るとは、失礼甚だしいと自分でも思うのであくまでふと頭に浮かんだこととしてここに残しておく。
このようなお話も含めて、今回のインターンでは出版業界への思いがより強まった。人々の暇つぶしの中でいかにより多くの教養や、娯楽、物語を届けられるかが私の今後の課題だ。
最後に、長くなってしまって申し訳ありません。お言葉に甘えさせて、沢山語らせていただきました。
少し、心がすっきりしています。今後とも、お世話になりますが、何卒よろしくお願い致します。
・文章を書く
・新聞を読む
・日常をアイデアに変えていく
・コンテンツに修正を加える
・与えられる機会はどんどん利用する
・周囲の言葉に目を向ける
・常にアンテナを張る
・息抜きも大事
S.M@立正大学
--------------------------------------------------------
《生活を豊かにするコンテンツ》
自分の発表について、すでに同じようなものがあるという指摘を受けて、下調べが足りなかったと反省した。
また、コンテンツの最終的な目標として、ファッションを手軽なものにしたいのか、ファッションに興味を持って欲しいのか、明確にする必要があると思った。
皆さんの案を聞かせて頂いて、僭越ながら、どのコンテンツも読者の趣味や習慣にアプローチ出来るものだな、という感想を持った。
読者の視野や興味に変化を及ぼすことができる、つまり「生活を豊かにする」ことができるコンテンツだと思う。
・自分が最終的に成し遂げたいことは何か考える
・言葉にたくさん触れ、うまく使いこなせるようになる
【1週間の振り返り】
《瞬発力》
私はあまり頭の回転が速い方ではなくて、パッと意見が出てこないとこも多々ある。だが、それは普段からの脳のトレーニングが足りていないのだとこの3日間で分かった。
素晴らしい意見が瞬時に出てくる人は普段からあらゆることについて考えているのだと思う。
《比喩の大切さ》
人に分かりやすく伝えたり、ネーミングを考える際には比喩が必要不可欠であることがわかった。
比喩を使いこなすには言葉の概念を理解しておかなかればいけなくて、そのためにも普段から言葉を大切にしていきたいと思う。
《何をするかではなく、どのようにするか》
勉学に励むとしても、新聞を読むにしても、ゲームをするにしても、自分が学びを得ようと思えば何か得られるものがあるし、
学びを得ようとしなければ何も得られないのだと分かった。逆に言えば、自分次第で24時間余らず学びの時間にすることができる。
これから時間を無駄にしないよう、心がけていきたい。
Y.S@中村学園大学
--------------------------------------------------------
《人に動かされるのではなく、自発的に動く事が大事。自分の人生は自分で作る》
黒澤先生がおっしゃっていた事で、自分たちは何かに影響を受けて動かされる側ではなく、
自分たちがアイデアを出して他人を動かす側にまわらないと、出版やマスコミ人にはなれないと気付きました。
《熱意や熱心な人に囲まれて、揉まれないと成長しにくい》
今回、日本ベンチャー大學のインターンに参加したことで、様々な熱量を持つ人に出会いました。
その方々と意見を出し合う事で自分の視点が当初に比べると相当変わったと思います。
中々この熱意のある人たちに囲まれる環境というのは無いし、中に入る機会も無いと思うので、貴重な経験を積めました。
・新聞アウトプットを続ける。
・この1週間で導入した、視点を変えていくという練習をこれから積み続ける。
《1週間の総括》
まず、このインターンで最初に思ったことが、視点を変えることがとても難しいという事です。
普段、日常を過ごしているだけでは自分の好きなものの、好きな・良い側面しか見ていなかったので、全く視点を変えることができませんでした。
新聞アウトプットでだんだんと、少しずつ慣れてきた事によって初めよりはマシになりましたが、最後の新しいコンテンツを作るという事で、
視点を変えてモノを新しく見るという事が中々できずに苦しみました。
しかし、この1週間で自分の中に新しく導入できたものが沢山あるので、良い機会と思ってこれからの生活の中でも活かしていこうと思います。
おっしゃっていたように、質より量で練習を重ねて、研鑽を積んで、就活本番までには習慣になっているように努力していきます。
T.O@北海学園大学
「最後に自分たちで企画を作ってもらいます」
インターン1日目、そう伝えられた時漠然と不安が襲ってきた。
はじめてのインターン、はじめての人たち、それらに囲まれ何より久々のパンプスでかかとがひりひりと痛みが増してきているような気もしてきて、どんどん気分が落ち込んでいったのを覚えている。
元より、自分をひけらかすことや話すことが苦手だった。頭の中でよく考えて言葉にするのならまだしも、
声に出すとなると短い時間で整理して相手に伝えなければいけないという行程がどうにも昔から得意になれなかったのだ。
そのせいもあって、アイデアは全く浮かばないし、他の子達はハキハキと自分の意見を話しているし…で、自分と周りの距離がどんどん開いていっているような感覚に陥っていた。
しかし、新聞アウトプットや自己紹介、他己紹介を通じて、半強制に自分の意見を言うという状況になった時、はじめはオドオドとしていたがどんどん自信がついていったのだ。
自分が誰だか分からなかった。けれど、「私ってこう思ってたんだ」「こう、見られているんだ」
「今こんなことが起きているんだ、ならこれはどうなんだろう」って新しい視点や見方が開けていくことがすごく楽しいことに気がついたのだ。
自分を理解するためにまずは声に出すこと。口から出た情報が耳から入ってきてようやくインプットされる。
そう感じた。コンテンツも、出来がどうであれ、私が将来やりたいこと、やっていかなければいけないことについての根っこができたかとは思う。あとはその芽を出すことができるか、そして育てられるのかが勝負だ。
《他人の物語》
人ってやっぱり自分が一番だから、自分目線で物事を捉えてしまう。意見を聞くときも、「この子がこう思うなら私はこう思うな」、
「この子はこんな性格なんだな。私とはこう違うな」といった風に私が、私とは、私よりと勝手に思考がいってしまうのだ。断じて自分大好きってわけではないので、
敢えて訂正はしておく。そうなれば、周りの視野が狭くなってしまうのだと考えた。そこで私は、他人の話をその人の物語として、まるで小説を読んでいるかのように思うことにした。
小説の内容は、かなり学ぶことが多く知識として自分の中に浸透する。それを対人に置き換えてみた。それは、視野や思考の範囲を広げることへ導いた。
確かに、自分との比較は大事だ。しかし、今回他の方のコンテンツ発表の中で、先日の自己紹介の内容と絡ませながら聞いていると、
この人はこんな過去があったから今こういう企画を立てているんだ、だからこそこんな企画が生まれたんだ、というような自分一人で芽生えなかった面白いアイデアがどんどん浮上してきたのだ。そういう意味で、他人の話を聞いていくことも大事だなと思った。
《松陰先生》
最後のお話の中で、吉田松陰が出てきたが、その中でも「死ぬ前にやりたいことは何だ?」という質問に「どうせ死ぬなら、世の中のことを少しでも知ってから死にたい。だから本を読ませてください」と答えたというお話を聞いて思ったことだ。私は中学生くらいのとき、「死ぬ」ということについて夜も眠れないほどの恐怖に陥ったことがある。
特に病院に通う、というほど重症ではないので重くは捉えないでほしい。ずっと死んだらどうなるんだろう?と大学生になってまで考えていたとき、「死ぬときにはじめて気づく人生で大切なこと33」という本に出会った。その中にあった言葉で印象に残っているのが、「生きていることは死ぬまでの暇つぶし。死ぬことを目的として生きている」というものだ。つまり生きるということは自由に楽しむ機会が与えられているだけなのだと。松陰先生が言いたかったのもこんな感じなのかな、と勝手に想像した。死ぬという目的を果たす前に、与えられた機会を充分に利用して、世界をより知りたいと思ったのではないだろうか。
松陰先生を語るとは、失礼甚だしいと自分でも思うのであくまでふと頭に浮かんだこととしてここに残しておく。
このようなお話も含めて、今回のインターンでは出版業界への思いがより強まった。人々の暇つぶしの中でいかにより多くの教養や、娯楽、物語を届けられるかが私の今後の課題だ。
最後に、長くなってしまって申し訳ありません。お言葉に甘えさせて、沢山語らせていただきました。
少し、心がすっきりしています。今後とも、お世話になりますが、何卒よろしくお願い致します。
・文章を書く
・新聞を読む
・日常をアイデアに変えていく
・コンテンツに修正を加える
・与えられる機会はどんどん利用する
・周囲の言葉に目を向ける
・常にアンテナを張る
・息抜きも大事
S.M@立正大学
--------------------------------------------------------
《生活を豊かにするコンテンツ》
自分の発表について、すでに同じようなものがあるという指摘を受けて、下調べが足りなかったと反省した。
また、コンテンツの最終的な目標として、ファッションを手軽なものにしたいのか、ファッションに興味を持って欲しいのか、明確にする必要があると思った。
皆さんの案を聞かせて頂いて、僭越ながら、どのコンテンツも読者の趣味や習慣にアプローチ出来るものだな、という感想を持った。
読者の視野や興味に変化を及ぼすことができる、つまり「生活を豊かにする」ことができるコンテンツだと思う。
・自分が最終的に成し遂げたいことは何か考える
・言葉にたくさん触れ、うまく使いこなせるようになる
【1週間の振り返り】
《瞬発力》
私はあまり頭の回転が速い方ではなくて、パッと意見が出てこないとこも多々ある。だが、それは普段からの脳のトレーニングが足りていないのだとこの3日間で分かった。
素晴らしい意見が瞬時に出てくる人は普段からあらゆることについて考えているのだと思う。
《比喩の大切さ》
人に分かりやすく伝えたり、ネーミングを考える際には比喩が必要不可欠であることがわかった。
比喩を使いこなすには言葉の概念を理解しておかなかればいけなくて、そのためにも普段から言葉を大切にしていきたいと思う。
《何をするかではなく、どのようにするか》
勉学に励むとしても、新聞を読むにしても、ゲームをするにしても、自分が学びを得ようと思えば何か得られるものがあるし、
学びを得ようとしなければ何も得られないのだと分かった。逆に言えば、自分次第で24時間余らず学びの時間にすることができる。
これから時間を無駄にしないよう、心がけていきたい。
Y.S@中村学園大学
--------------------------------------------------------
《人に動かされるのではなく、自発的に動く事が大事。自分の人生は自分で作る》
黒澤先生がおっしゃっていた事で、自分たちは何かに影響を受けて動かされる側ではなく、
自分たちがアイデアを出して他人を動かす側にまわらないと、出版やマスコミ人にはなれないと気付きました。
《熱意や熱心な人に囲まれて、揉まれないと成長しにくい》
今回、日本ベンチャー大學のインターンに参加したことで、様々な熱量を持つ人に出会いました。
その方々と意見を出し合う事で自分の視点が当初に比べると相当変わったと思います。
中々この熱意のある人たちに囲まれる環境というのは無いし、中に入る機会も無いと思うので、貴重な経験を積めました。
・新聞アウトプットを続ける。
・この1週間で導入した、視点を変えていくという練習をこれから積み続ける。
《1週間の総括》
まず、このインターンで最初に思ったことが、視点を変えることがとても難しいという事です。
普段、日常を過ごしているだけでは自分の好きなものの、好きな・良い側面しか見ていなかったので、全く視点を変えることができませんでした。
新聞アウトプットでだんだんと、少しずつ慣れてきた事によって初めよりはマシになりましたが、最後の新しいコンテンツを作るという事で、
視点を変えてモノを新しく見るという事が中々できずに苦しみました。
しかし、この1週間で自分の中に新しく導入できたものが沢山あるので、良い機会と思ってこれからの生活の中でも活かしていこうと思います。
おっしゃっていたように、質より量で練習を重ねて、研鑽を積んで、就活本番までには習慣になっているように努力していきます。
T.O@北海学園大学
令和2年(2020)【9月11日(金) 】夏の出版編集トレーニング5日目 4期生3組
2020/09/11
コメント (0)
------------------------------------------------------
令和2年(2020)【9月11日(金)】
夏の出版編集トレーニング5日目
4期生3組
--------------------------------------------------------
《こだわり》
ESの内容を考えているときに感じたことが、こだわりが強くて常に面白いことを考えている人ほど他人に興味を持たれやすいということだ。
そして就職活動ではそういう人間であることを求められるように感じる。
自分らしくあるということが必ずしも強いこだわりを持つということではないと思いながら、今はこれから何にこだわろうと考えている。
しかし最終的にはどんなことでも面白く書ける文章力が必要なので、まずは毎日文に触れたり書いたりすることが大切だ。
《面白く、端的に話す》
これからは自己アピールを1つに絞ろうと思った。いらない情報は切り捨てて、相手が興味を持ってくれそうな内容を選択して話せるようになりたい。
家に帰ってから、自分の王道の自己紹介と、別バージョンをいくつか考えてみようと思った。
・アイデアをメモする
・よく観察し、色々なことに気がつく
・色んな人と会って、話す練習をする
M.S@東京理科大学
--------------------------------------------------------
《一行目のキャッチ》
ES発表の時のアドバイスで、「刺激に飢えてる人たちに見せるものなので、見てる側のアンテナに普段は入らない事が歓迎される」という事を聞いて、自分も普段本を買う時には最初の1行で気にいるか気に入らないかを選択しろと言われた事があるので、それだけ最初が肝心なのだと気付きました。
《まずは情報仕入れ》
アイデアが思い浮かばないというお話の中で、それはまず知っている情報が足りないとのアドバイスがありました。
誰も掛け合わせた事の無い組み合わせを作るためにもまずは知っていないとどうしようもないので、知る努力を重ねていこうと思います。
・仮説→検証の流れを身に付ける(特に検証)
・知る努力を重ねる(電車内広告は目を通す等)
T.O@北海学園大学
--------------------------------------------------------
《みんなおんなじ》
私だけが特別、異質などと思いがちですが、意外と皆似たようなことを感じる者同士なのだと気付きました。
2日目でやめようかと思った、という吐露を聞いたときは驚きました。まさに私と同じだったからです。
帰りのエレベーターではそれぞれが同様に辛かったことを知り、現地参加の5人が最後までやり遂げたことの大きさを感じました。
今までの人生で、私だけが辛いと思ってきたことも、もしかしたら思い込みだったのかもしれません。口に出して伝えてみること、共感を口に出して返すこと。
これがもっと浸透すれば、物事を達成しやすい組織ができそうです。
《時間はかかるもの》
私の人生を振り返ると、締切前に焦って制作するという経験ばかりです。
追い詰められると力を発揮できるというのは私のような者の言い訳で、スピードを求めすぎると質が落ちるのが道理です。
コロナワクチン問題もドコモ口座問題もそれを体現しているように思います。私は地道な手段でも、何か確立したものをこの世に残したいと思うばかりです。
・秘密主義を緩和する
・一番重要なことは常に考える
・拒絶する前によく知ろうとする
・いいところを探す
・気付きを大切にする
・新コンテンツを完成させる
T.T@東北大学
令和2年(2020)【9月11日(金)】
夏の出版編集トレーニング5日目
4期生3組
--------------------------------------------------------
《こだわり》
ESの内容を考えているときに感じたことが、こだわりが強くて常に面白いことを考えている人ほど他人に興味を持たれやすいということだ。
そして就職活動ではそういう人間であることを求められるように感じる。
自分らしくあるということが必ずしも強いこだわりを持つということではないと思いながら、今はこれから何にこだわろうと考えている。
しかし最終的にはどんなことでも面白く書ける文章力が必要なので、まずは毎日文に触れたり書いたりすることが大切だ。
《面白く、端的に話す》
これからは自己アピールを1つに絞ろうと思った。いらない情報は切り捨てて、相手が興味を持ってくれそうな内容を選択して話せるようになりたい。
家に帰ってから、自分の王道の自己紹介と、別バージョンをいくつか考えてみようと思った。
・アイデアをメモする
・よく観察し、色々なことに気がつく
・色んな人と会って、話す練習をする
M.S@東京理科大学
--------------------------------------------------------
《一行目のキャッチ》
ES発表の時のアドバイスで、「刺激に飢えてる人たちに見せるものなので、見てる側のアンテナに普段は入らない事が歓迎される」という事を聞いて、自分も普段本を買う時には最初の1行で気にいるか気に入らないかを選択しろと言われた事があるので、それだけ最初が肝心なのだと気付きました。
《まずは情報仕入れ》
アイデアが思い浮かばないというお話の中で、それはまず知っている情報が足りないとのアドバイスがありました。
誰も掛け合わせた事の無い組み合わせを作るためにもまずは知っていないとどうしようもないので、知る努力を重ねていこうと思います。
・仮説→検証の流れを身に付ける(特に検証)
・知る努力を重ねる(電車内広告は目を通す等)
T.O@北海学園大学
--------------------------------------------------------
《みんなおんなじ》
私だけが特別、異質などと思いがちですが、意外と皆似たようなことを感じる者同士なのだと気付きました。
2日目でやめようかと思った、という吐露を聞いたときは驚きました。まさに私と同じだったからです。
帰りのエレベーターではそれぞれが同様に辛かったことを知り、現地参加の5人が最後までやり遂げたことの大きさを感じました。
今までの人生で、私だけが辛いと思ってきたことも、もしかしたら思い込みだったのかもしれません。口に出して伝えてみること、共感を口に出して返すこと。
これがもっと浸透すれば、物事を達成しやすい組織ができそうです。
《時間はかかるもの》
私の人生を振り返ると、締切前に焦って制作するという経験ばかりです。
追い詰められると力を発揮できるというのは私のような者の言い訳で、スピードを求めすぎると質が落ちるのが道理です。
コロナワクチン問題もドコモ口座問題もそれを体現しているように思います。私は地道な手段でも、何か確立したものをこの世に残したいと思うばかりです。
・秘密主義を緩和する
・一番重要なことは常に考える
・拒絶する前によく知ろうとする
・いいところを探す
・気付きを大切にする
・新コンテンツを完成させる
T.T@東北大学
《日本語》
校正を通して、自分が日本語を曖昧にしか理解できていなかったことに気づいた。特に、言葉が正しく使えているのか、接続詞を加えた方が良いのか迷うことが多かった。
日常生活で言葉に触れる機会はたくさんあると思うので、一つ一つの言葉を大事にして生活したい。
《知る》
新しいものを生み出すために、まずは、今あるものについて知る必要があることが分かった。
新しいアイデアというのは、何もないところから生み出すものではなく、既存のものを進化させることで見えてくるのかなと思った。
・国語辞典を読む
・企業のビジネスについて分析する
Y.S@中村学園大学
--------------------------------------------------------
《声に出すこと》
このインターンで、声に出すことの大切さを痛感した。
自分の心の内で絡まっていた糸が、言葉にするだけで一本の糸のように出てくるのだ。整理つかないことがあるのならまずは声に出して読んでみる。
スピーチに慣れることも大事だが、それ以上に今自分が考えていることがクリアになる。そう感じた。
《書くこと》
エントリーシートを書く上で、大事なのはとにかく数をこなすこと。その上で、文章力を向上させたいなら文章を書き続けなければならない。
いつも一歩手前で躊躇していたブログをやってみようかなと感考えた。何回も何回も書き続けていれば、新たな視点が生まれると思うのだ。
《聞くこと》
相手の話すことを校正する。それが自分のためにつながる。ストンと心に落ちた。人のふり見て我がふり直せ、ということなのかなと思った。
それに限らず、他人の意見によって自分にないアイデアが生まれるということは、今日のエントリーシートの発表で感じた。
・沢山人と会話する
・新聞アウトプットの継続
・文章を書く
・自分にとってのこだわりをより数をこなしていく
・本を読む
S.M@立正大学
校正を通して、自分が日本語を曖昧にしか理解できていなかったことに気づいた。特に、言葉が正しく使えているのか、接続詞を加えた方が良いのか迷うことが多かった。
日常生活で言葉に触れる機会はたくさんあると思うので、一つ一つの言葉を大事にして生活したい。
《知る》
新しいものを生み出すために、まずは、今あるものについて知る必要があることが分かった。
新しいアイデアというのは、何もないところから生み出すものではなく、既存のものを進化させることで見えてくるのかなと思った。
・国語辞典を読む
・企業のビジネスについて分析する
Y.S@中村学園大学
--------------------------------------------------------
《声に出すこと》
このインターンで、声に出すことの大切さを痛感した。
自分の心の内で絡まっていた糸が、言葉にするだけで一本の糸のように出てくるのだ。整理つかないことがあるのならまずは声に出して読んでみる。
スピーチに慣れることも大事だが、それ以上に今自分が考えていることがクリアになる。そう感じた。
《書くこと》
エントリーシートを書く上で、大事なのはとにかく数をこなすこと。その上で、文章力を向上させたいなら文章を書き続けなければならない。
いつも一歩手前で躊躇していたブログをやってみようかなと感考えた。何回も何回も書き続けていれば、新たな視点が生まれると思うのだ。
《聞くこと》
相手の話すことを校正する。それが自分のためにつながる。ストンと心に落ちた。人のふり見て我がふり直せ、ということなのかなと思った。
それに限らず、他人の意見によって自分にないアイデアが生まれるということは、今日のエントリーシートの発表で感じた。
・沢山人と会話する
・新聞アウトプットの継続
・文章を書く
・自分にとってのこだわりをより数をこなしていく
・本を読む
S.M@立正大学
《人とは違う気づき》
ありきたりの事柄では、エントリーシートが通らないのだと思い知りました。
斬新なアイデアを思いつくには、日頃の観察力が必要だと思いました。
・新聞をななめに読めるようにする
・観察力を鍛える
C.I@専修大学
--------------------------------------------------------
《インパクト》
エントリーシートは人事の人は、膨大な数あるため、あまり時間をかけて読んでいないことがわかった。
例えどんなに良い文章を書いたとしても、はじめにインパクトを持ってこないと見て貰えない上、印象に残らない。日頃からインパクトを与える言葉を考えたいです。
・毎日キャッチコピー付きの日記をつける
・面白いものを頭の中で沢山作る
S.F@京都女子大学
ありきたりの事柄では、エントリーシートが通らないのだと思い知りました。
斬新なアイデアを思いつくには、日頃の観察力が必要だと思いました。
・新聞をななめに読めるようにする
・観察力を鍛える
C.I@専修大学
--------------------------------------------------------
《インパクト》
エントリーシートは人事の人は、膨大な数あるため、あまり時間をかけて読んでいないことがわかった。
例えどんなに良い文章を書いたとしても、はじめにインパクトを持ってこないと見て貰えない上、印象に残らない。日頃からインパクトを与える言葉を考えたいです。
・毎日キャッチコピー付きの日記をつける
・面白いものを頭の中で沢山作る
S.F@京都女子大学






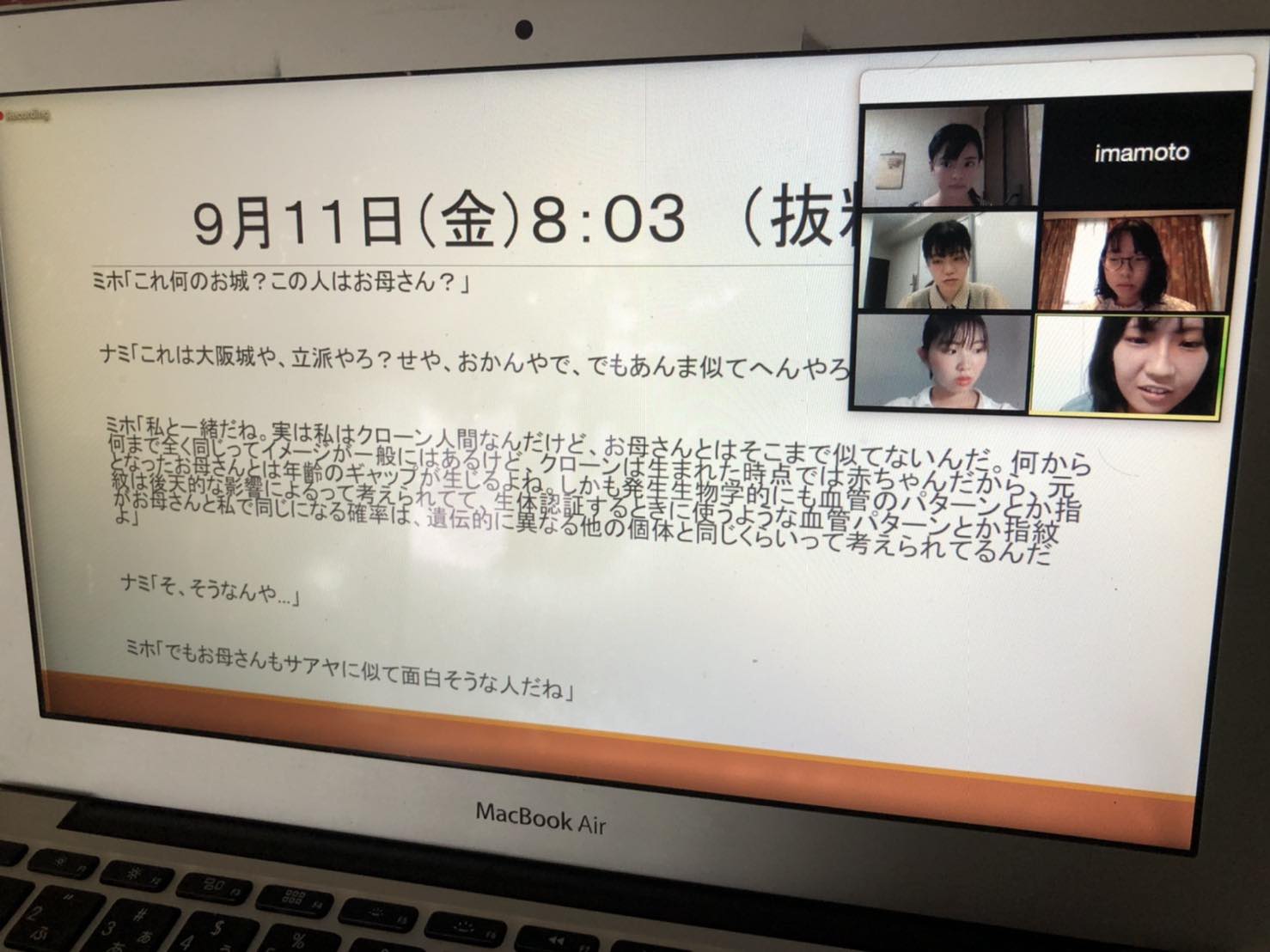
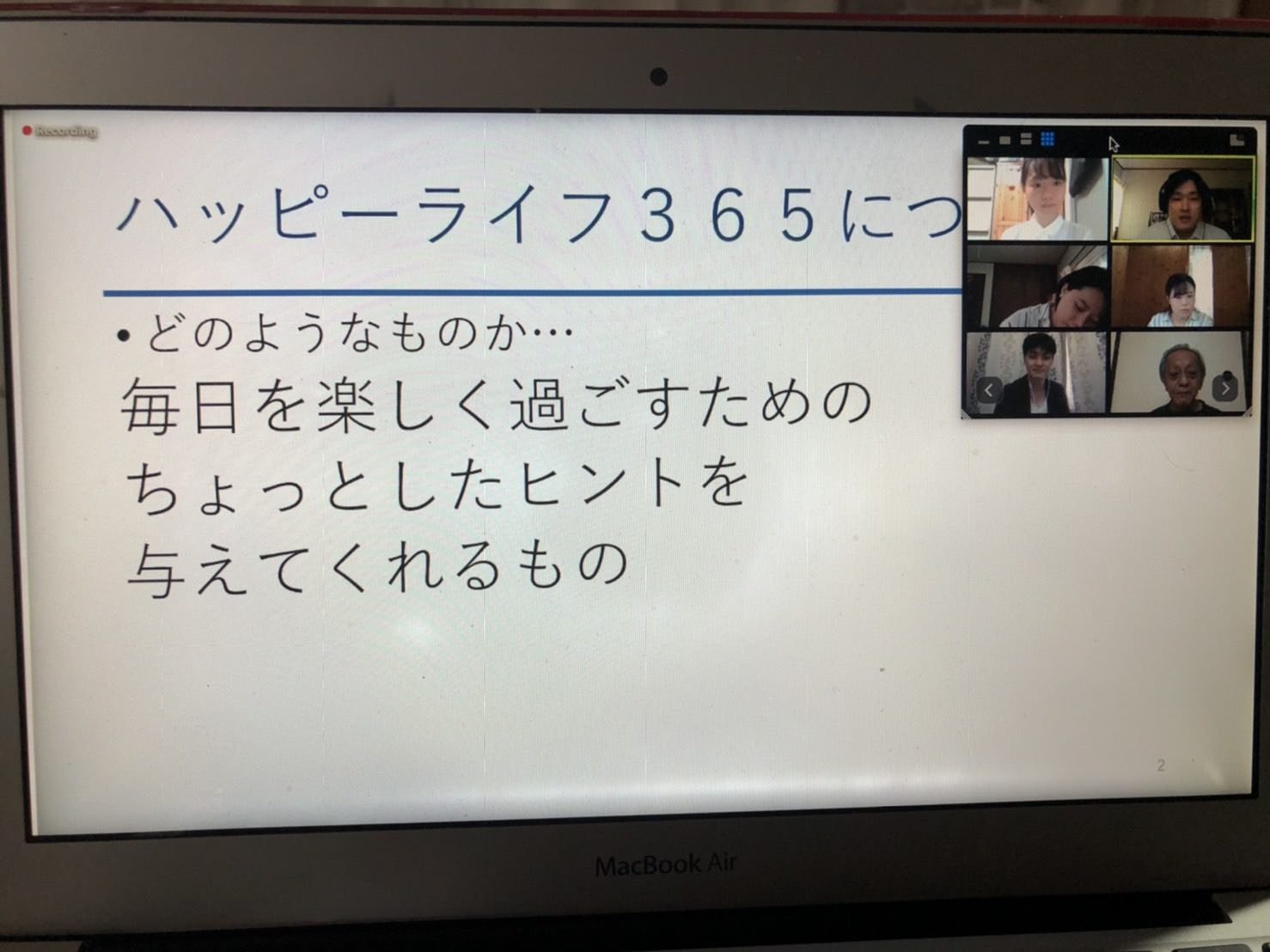


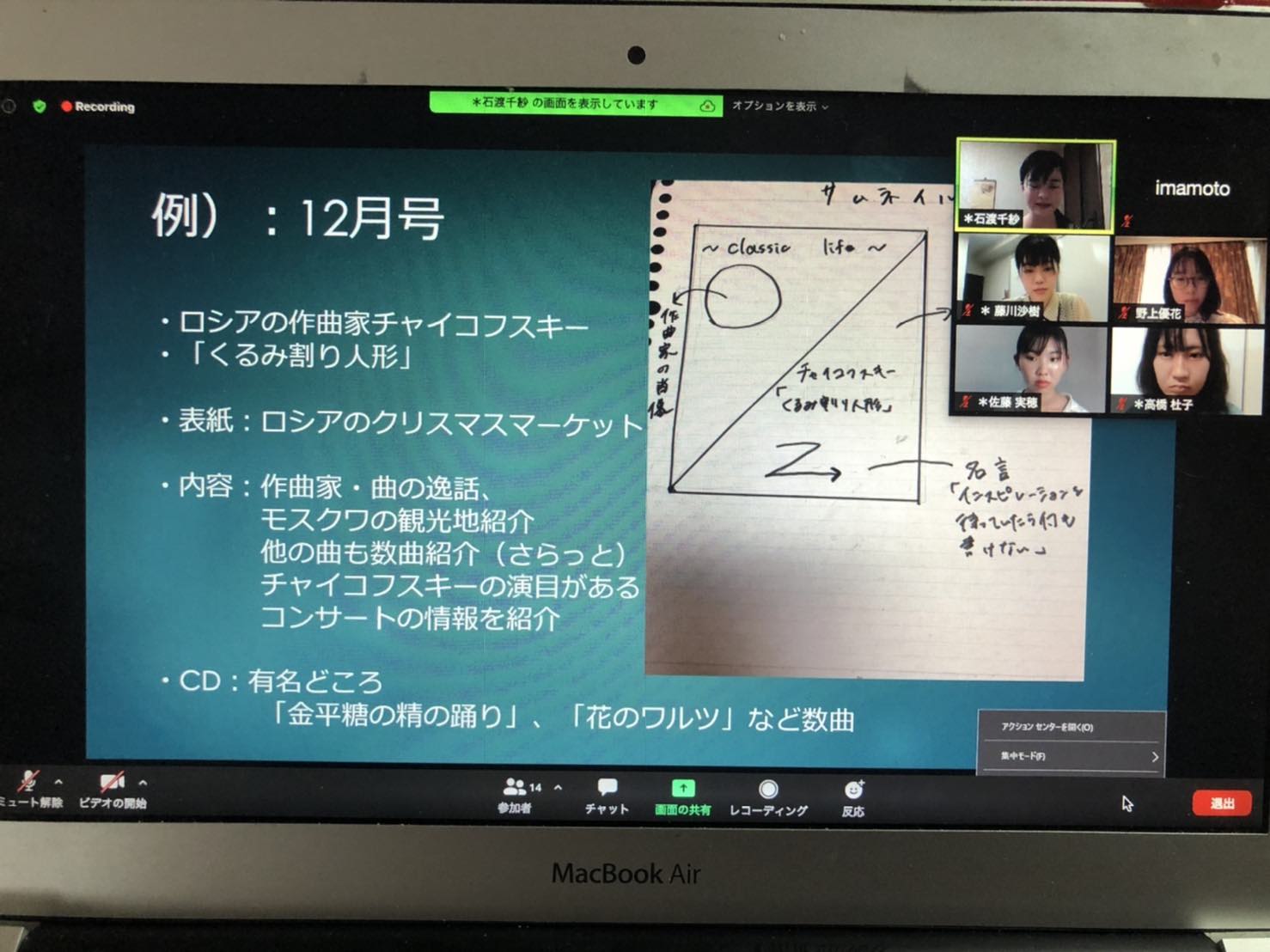
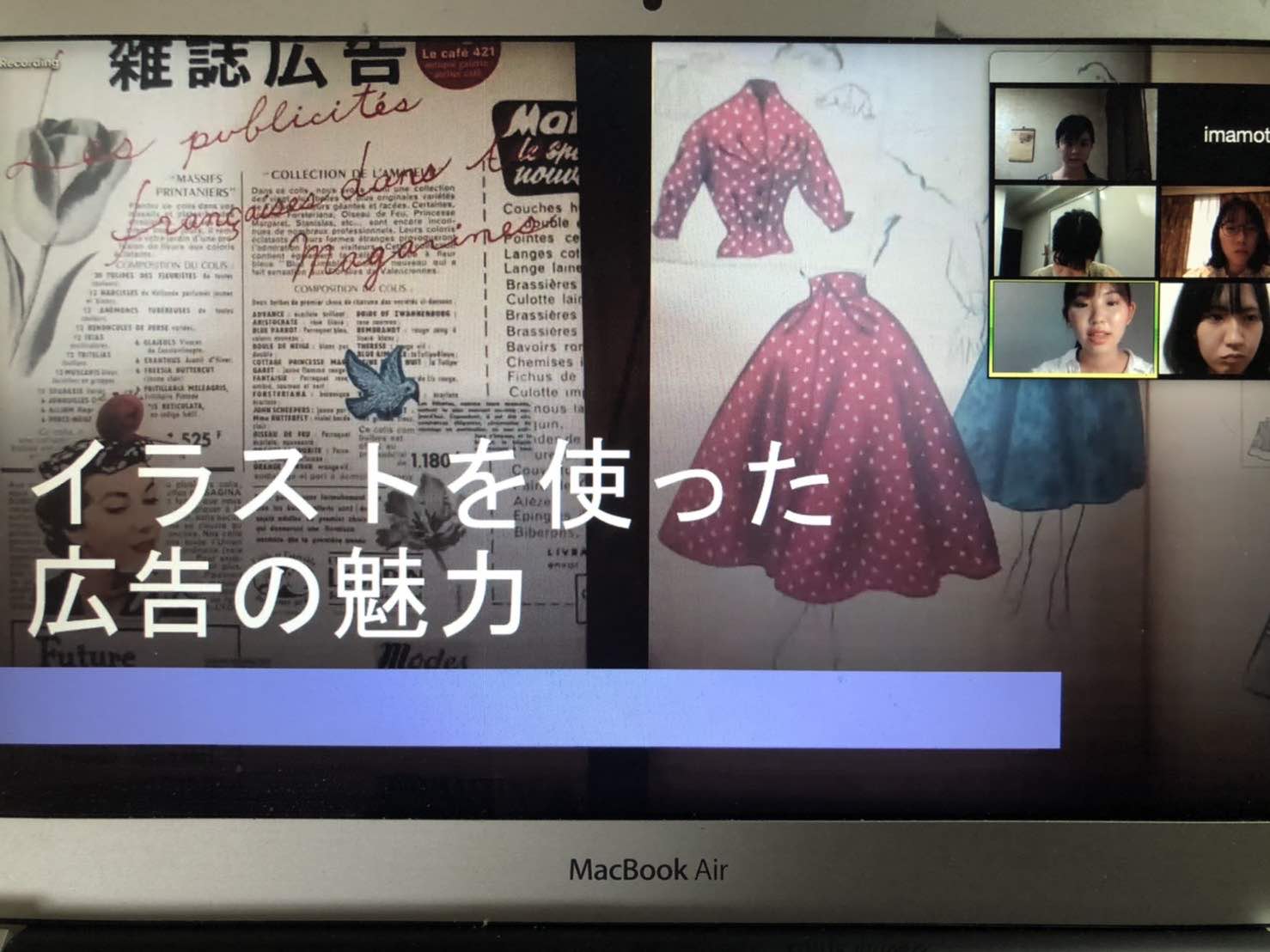
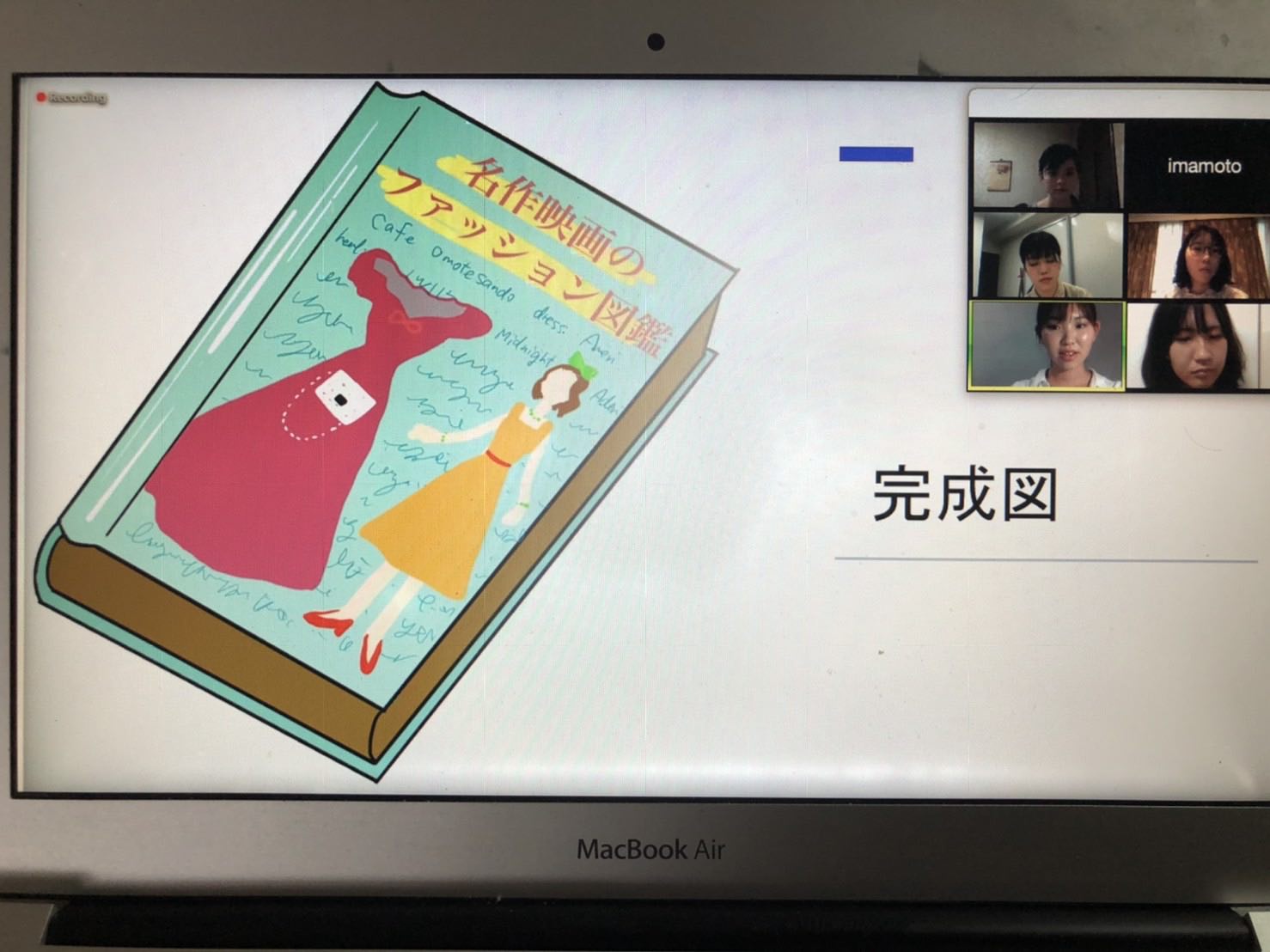

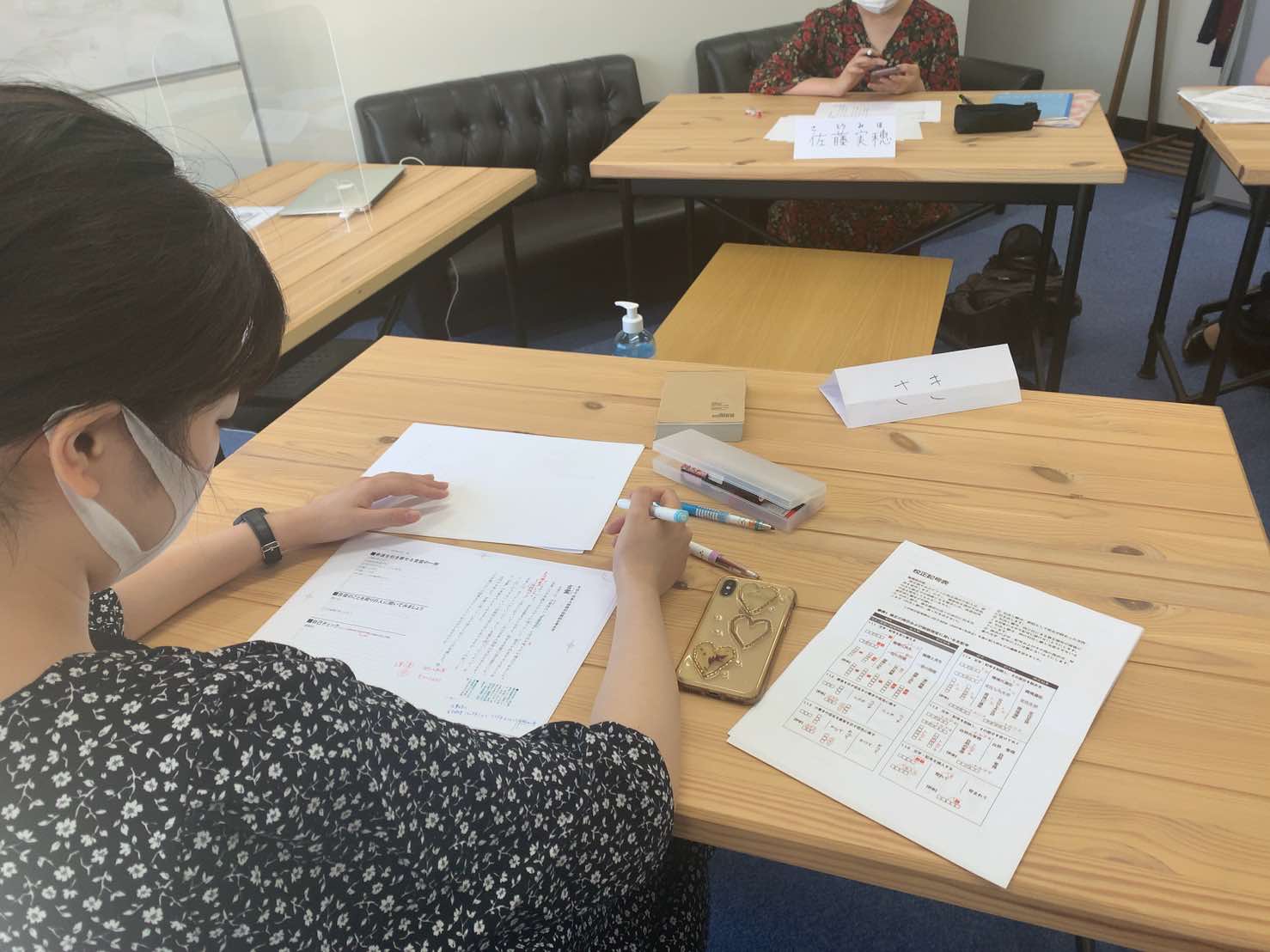
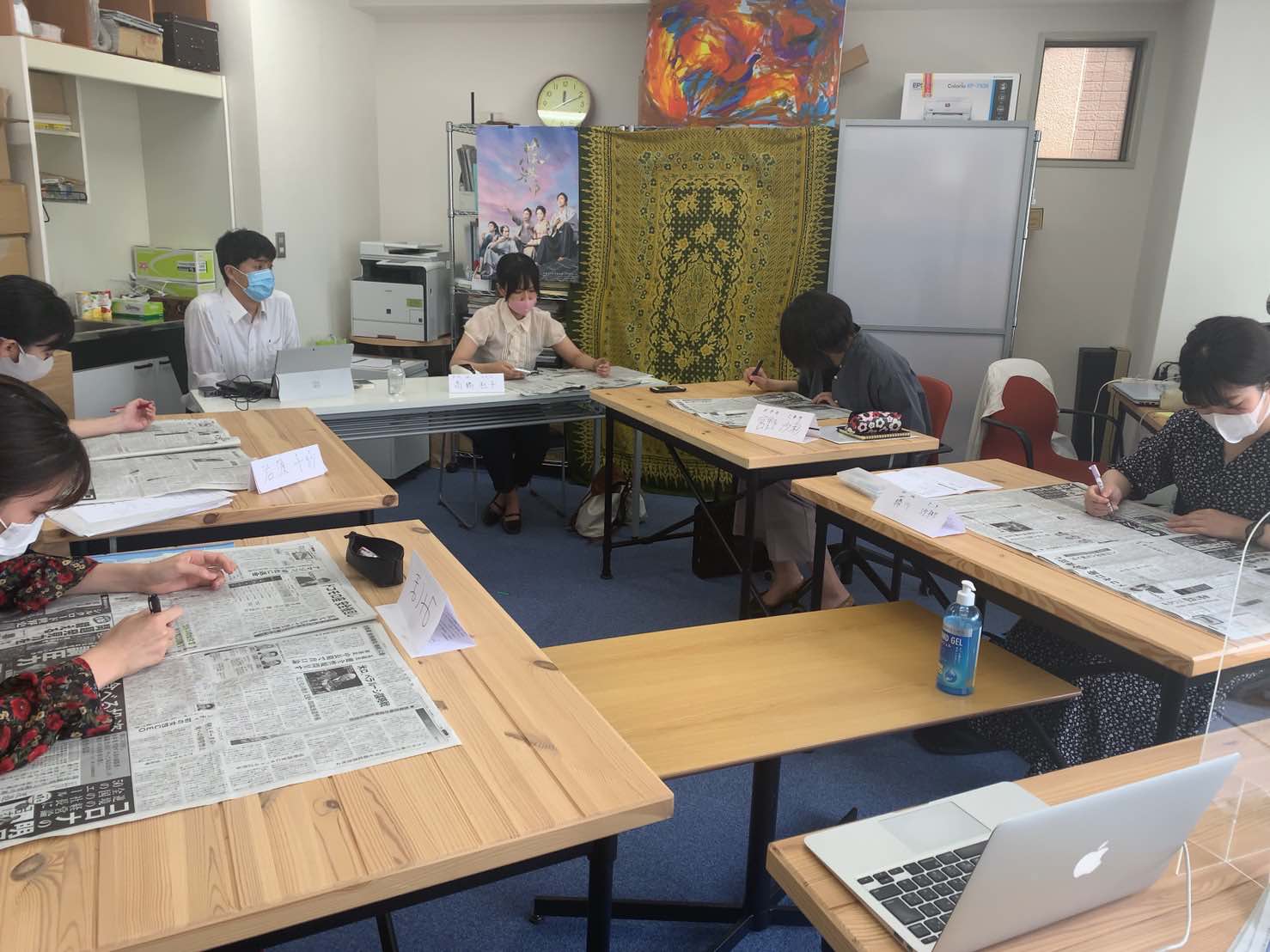
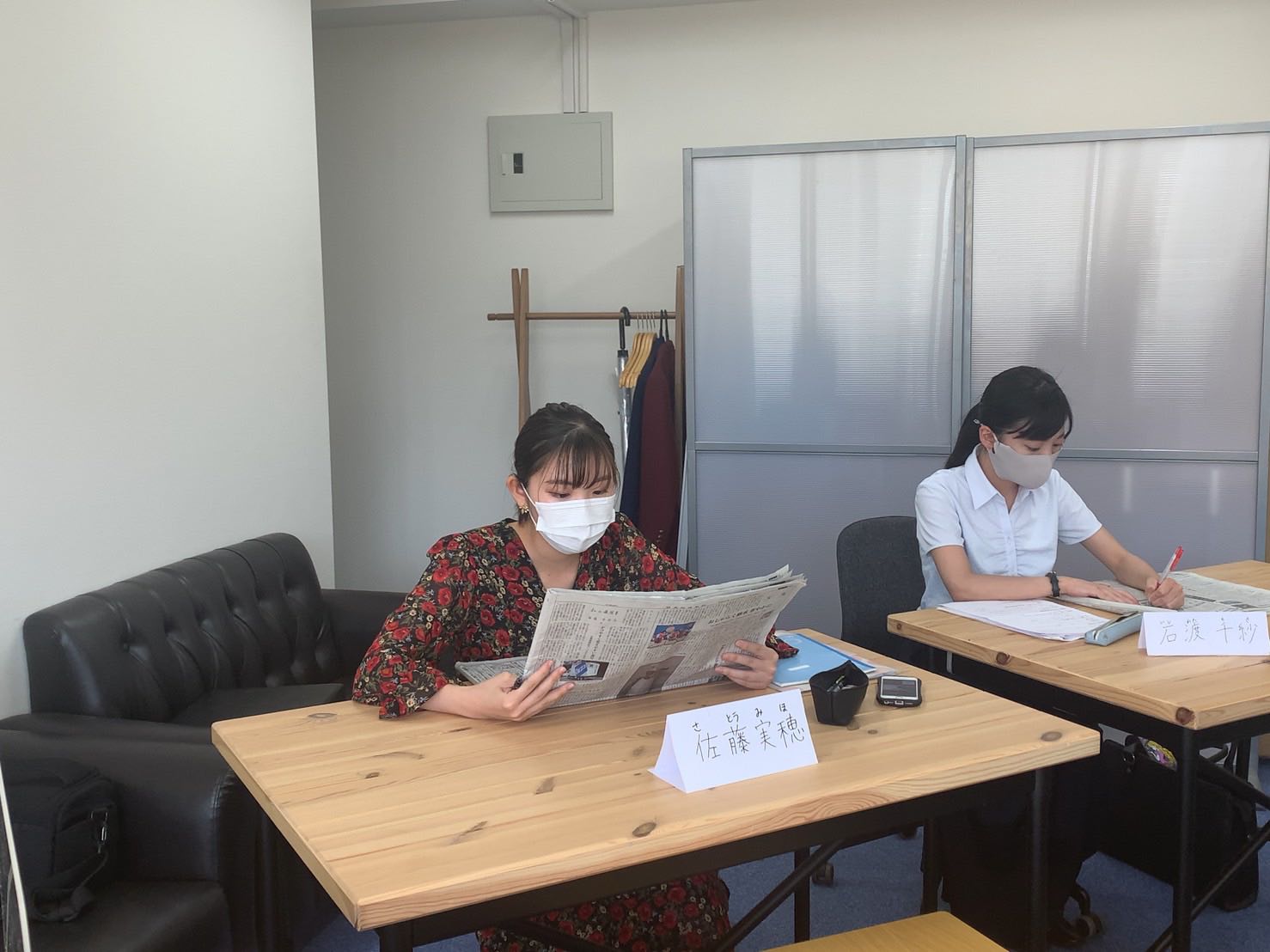

 RSS 2.0
RSS 2.0












