東京校の講義レポート
平成26年(2014)【11月1日(土)】 映像学「人を惹きつける動画の撮り方」/岩尾勝先生(映像ディレクター)
2014/11/01
コメント (0)
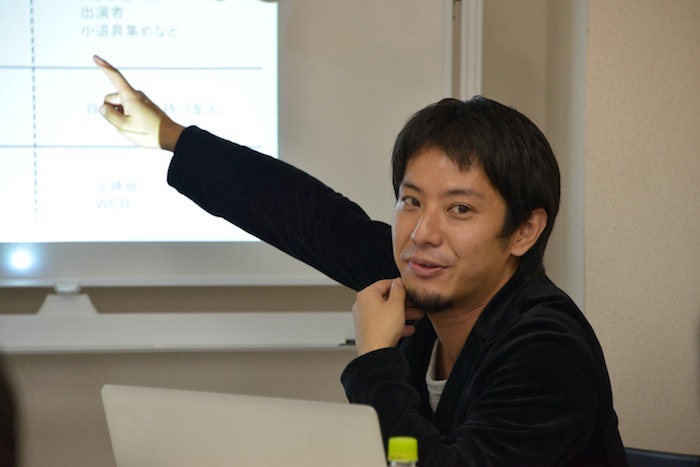 ●映画学『長州ファイブ』
●映画学『長州ファイブ』素直な感想として「長州ファイブを正面から取り上げた最近の映画が
存在していたのか…」という軽い驚きを感じた。
主人公に据えられたのも、伊藤博文や井上馨に比べて取り上げられることの少ない
山尾庸三である。
この人物に関して知るには、歴史の勉強という面において、とてもよい機会だったと思う。
山尾は寡黙な人物として描かれ、聾唖の女性との出会いのエピソードも語られるが、
山尾の魅力は俳優の松田龍平個人の醸し出すものによるところが大きいようにも感じた。
また、作中で長州ファイブが薩摩からの留学生一行と遭遇する場面も描かれる。
出発時期、長州と薩摩の藩論、滞在期間、そして密航者と藩公認留学生という
立場の違いなど、いくつもの相違点が重なってくる。
そうして2つの日本人集団が諍いを起こすところに、興味をそそられた。
彼らそれぞれが、何のために英国へ来ているのか、藩あるいは日本そのものが
危機に立たされている状況で何をすべきなのか、思い悩む様子が表現されている。
ここで、彼らは藩よりも大きな「日本」という存在のために学び、
闘うことをはっきり意識するようになっていくのである。
国民意識の覚醒という近代の重要なテーマを、異国の地で表現するのはとても分かりやすいと感じた。
今元局長によると、歴史の映画は、色々なことを詰め込み過ぎて
教科書的になってしまっているきらいがあるという。
「歴史の勉強」ではなく、エンターテインメントとして「続きが気になる!」と
観客に言わせるためには、テーマを絞って余計なものを徹底的にそぎ落とさねばならない。
伝えたいことを伝えきること、そして観客を惹きつけ楽しませることの2つを、
同時に満たさなければならないところに、映画を含めた芸術作品の難しさが
あるということを少し理解できた。
そういった視点から映画を観ると、さらに面白い発見があるに違いない。
●岩尾勝先生の講義「人を惹きつける動画の撮り方」
映像ディレクターである岩尾さんは、LUSHやPeach JohnなどのCMを手掛ける超一流の人物である。
しかしながら、そういう大物然としたところは全く見せず、
気さくで自然体な雰囲気で私たちに接して下さったのが嬉しかった。
スマホやタブレットの普及により、写真や動画を気軽に撮れるようになった今、
何でもかんでも撮ろうとする向きもある。
そうやってとにかく撮ってみる姿勢も大切だが、同時に「良いもの」に触れ、
まず自分の目で観て体で感じること、インプットすることも忘れてはならないという。
岩尾さんが手がけた作品や、OK GOのMVなどを見ていると、色々なアイデアが
存在することを知り、ワクワクできる。
そのワクワクした体験から、自分でも同じ感覚を共有できるものを作っていくことが
必要なのではないか、と感じた。
私個人に関わるところでは、駄作が出来てしまうことを怖がらずに
どんどん動画を撮ってみるとよい、ということであった。
ここでもやはり、インプットとアウトプットのバランスをとっていくことが大切なのだ、と再確認できた。
また、岩尾さんがたびたび口にされていたのが、「ピース」でありたいという言葉である。
例えば、ピースな人と仕事をしたい、ということだ。
その真意を正確に理解できたわけではないが、根本的な部分で自分が
楽しんでできる仕事を、同様に仕事を楽しんでいる人とともにやりたい、
ということではないだろうか。
実際の作品を見ても、厳しいスケジュールでもきっと楽しみながら
作り上げていったんだろう、と感じられた。
芸術的な仕事をしようということではないが、岩尾さんのように自分の感性を磨いて、
心から仕事を楽しめる生き方をしていきたい。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
 ●「生きたる機械」
●「生きたる機械」山尾庸三の言ったセリフである。
国禁を犯して、エゲレスへ向かう5人の若者の有志を心の底から尊敬した。
私は、この映画を観て、国の為に何かしなければと思い、
奮いたった若者が羨ましいと素直に感じた。
そして、自分はどんなふうに日本へ恩を返せば良いのだろう。
私には、まだ早いような気がする。
もっと自分を、人を、世界を知らないといけないと思う。
さらに、彼らがこのようなことも言っていた。。
「なぜ、生きるのかより、生きる為にどうすればよいかを考えることが
必要である」と。
私もその言葉に共感をした。確かに、現代では、生きる為に何をするのかが
最も必要なことと思える。
それを理解したうえで、自分の目標を達成するための方法を
自分の手で見つけていきたいと思えるようになった。
●映像学
・世界観を壊したくない
この言葉は、岩尾先生が仰っていたものである。
どういうことなのかというと、岩尾先生は映像をつくる時
クライアントの要望に応えながらも、あまりいじることなどはしないという。
岩尾先生の経験とセンスなのだと思う。凡人の私には到底理解できないことである。
しかし、そのような感性は必要なのでないかと思う。
ならば、今回、教えて頂いた、「Snap Movie」という動画撮影アプリを使って、
動画を撮るという行為をまずは、やってみることから始めていく。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
---------------------------------------------------------
●映画學 『長州ファイブ』
幕末の時代に5人の長州藩の有志達が新しい学問や技術を学ぶために
イギリス留学するという内容の映画です。
その5人の長州藩の有志達というのは井上馨、伊藤博文、遠藤謹助、
井上勝、山尾庸三の5人の事で、いずれも後の明治の時代に活躍した人物達でした。
彼らは村田兵蔵の『技術を学べば現実を変えられる』という助言を受けて、
当時、海外密航は幕府から処刑される程の重罪にも関わらず、命がけで
日本を変えるためにイギリス留学をしました。
そのため、藩からまともな援助が受けられず、自分達で資金を集め、
更に断髪して武士であることも辞める程の命がけの覚悟で海外密航をしたのでした。
この映画で特に印象に残った場面は留学先のイギリスで出会った
薩摩藩の留学生との出会いでした。
彼らは藩の庇護を受けてイギリスに留学したのに対し、
長州藩の有志達は藩からまともな援助を受けずに留学しました。
薩摩藩の留学生は藩のためだけを想い留学したのに対し、
長州藩の有志達は藩だけではなく、国のため日本のためを想う意識の違いが
この場面に表れていると感じました。
これは今の学生である私達にも言えることで、今の学生達のほとんどが
薩摩藩のような意識なのに対し、長州藩の有志達のような意識を持つ学生は少ないのが現状です。
そのため、松陰先生の志を受け継ぐ私達、ベン大生がこの『長州ファイブ』のような
意識を持つためにもっと精進していかなければならないと感じました。
●人をPEACEにする動画
岩尾先生はフリーランスの映像ディレクターで主にPVやショートフィルム、
テレビCMなどを手がけている方です。
映像ディレクターには2種類のタイプの人がいて、映像に興味がなくて
仕事に就いた人と昔から映像が好きで仕事に就いた人の2種類のタイプがいる。
岩尾さんは後者のタイプで、映像ディレクターになった方です。
その事が講義中の映像の説明を楽しそうにご説明されている事から
映像が好きであるのだという事が伺えました。
また、岩尾さんに『映像を撮る上で観る人のどのような点を意識して
作っているのですか』という私の質問に対して、岩尾さんは
『1つ1つのコマにそれぞれ意味づけをしている』というお答えを頂いた。
今まで映像ディレクターの方々は自分の感性で映像を作っている人が
ほとんどだと思っていましたが、岩尾さんのように1つ1つのコマに
それぞれ意味づけをする方法もあるのだと知りました。
そして、岩尾さんは『人をPEACEにする、笑顔にさせる動画を作ることを
意識している』と仰っていました。
そのためには『日頃から色々な良い物を目で見たり、写真に撮ったり
する事が必要』だというアドバイスをして頂いた。
私も少しでも、良い写真や動画を撮るために、もっと日頃から色々な良い物を見たり
撮ったりする事から始めていきます。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
------------------------------------------------------
平成26年(2014)【10月31日(金)】 個人面談/鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表) 演劇『ちはやぶる神の国』鑑賞
2014/10/31
コメント (0)
-------------------------------------------------
●1日の流れ
9:00 東戸塚駅へ移動
9:30 個人面談/鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)
・柳澤、嘉形、須藤、鈴木
12:10 個人面談終了
13:40 新宿御苑前駅集合
13:50 演劇『ちはやぶる神の国』を鑑賞
〜異聞、本能寺の変
-------------------------------------------------
●鳥越先生の個人面談
事業創造の今後の方向性や、自分自身の強みについて話し合った。
もっとも重要なことは、肚を決めて取り組むことであるが、
なかなかそれが出来ていないことを指摘された。
確かに慎重であることは私の良いところである、と認めて頂いた。
しかし、起業家としては思い切りよく、自分がこれだと思うことに
とことん取り組まなければならない。
そこで、期限を切って、自分を追い込むことがどうしても必要だ。
仕事に時間を割り当てるのではなく、先に時間を決めて、その中で仕事をやりきるのである。
そして、行動という形でアウトプットしていかなければ、インプットの意味がなくなってしまう。
目の前の課題に忙殺されるばかりではなく、事業を創造する能力をもっと磨いていきたい。
●『ちはやぶる神の国』
信長と光秀の、一世一代の大芝居である。
その筋書き、黒幕の真相の意外性に衝撃を受けるとともに、
この物語が史実だったらよかったのに、という感慨深い終わり方だった。
歴史上の人物たち一人ひとりから、人間味を感じることが出来たのは、
彼らの間の愛憎が余すところなく表現されていたからだろう。
特に、信長の小姓たちの存在は物語のキーとなっている。
彼らがどれだけ信長を愛しているか、ということがクライマックスの本能寺の変でも表される。
しかし、今一つ分からないのは、なぜ小姓たち、特に蘭丸が信長を、死を共にするまでに愛したのか?
前提知識がないので仕方がないが、蘭丸と信長が初めて出会う時のことが知りたい、と感じた。
演劇は滅多に観ることがないので、今回の機会は自分の感性を磨く意味でも貴重であった。
目の前の生身の人間が直接語りかけてくる、という点が映画とは違う迫力、説得力を持たせている。
それぞれの俳優さんのことをよく知るようになれば、さらに深い影響力を持って
響いてくるのではないかと思う。
ARCHEさんとは何度か会わせて頂いていることもあり、
彼が演じる利休の言葉は実際に、本当に信長の心、そして観客の心を動かしているように感じられた。
演劇をより楽しむためには、もっと何度も足を運んで観る必要があるのだろう。
そうして、自分自身もまた人の心を動かす存在になるために学びを得たい。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●1日の流れ
9:00 東戸塚駅へ移動
9:30 個人面談/鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)
・柳澤、嘉形、須藤、鈴木
12:10 個人面談終了
13:40 新宿御苑前駅集合
13:50 演劇『ちはやぶる神の国』を鑑賞
〜異聞、本能寺の変
-------------------------------------------------
●鳥越先生の個人面談
事業創造の今後の方向性や、自分自身の強みについて話し合った。
もっとも重要なことは、肚を決めて取り組むことであるが、
なかなかそれが出来ていないことを指摘された。
確かに慎重であることは私の良いところである、と認めて頂いた。
しかし、起業家としては思い切りよく、自分がこれだと思うことに
とことん取り組まなければならない。
そこで、期限を切って、自分を追い込むことがどうしても必要だ。
仕事に時間を割り当てるのではなく、先に時間を決めて、その中で仕事をやりきるのである。
そして、行動という形でアウトプットしていかなければ、インプットの意味がなくなってしまう。
目の前の課題に忙殺されるばかりではなく、事業を創造する能力をもっと磨いていきたい。
●『ちはやぶる神の国』
信長と光秀の、一世一代の大芝居である。
その筋書き、黒幕の真相の意外性に衝撃を受けるとともに、
この物語が史実だったらよかったのに、という感慨深い終わり方だった。
歴史上の人物たち一人ひとりから、人間味を感じることが出来たのは、
彼らの間の愛憎が余すところなく表現されていたからだろう。
特に、信長の小姓たちの存在は物語のキーとなっている。
彼らがどれだけ信長を愛しているか、ということがクライマックスの本能寺の変でも表される。
しかし、今一つ分からないのは、なぜ小姓たち、特に蘭丸が信長を、死を共にするまでに愛したのか?
前提知識がないので仕方がないが、蘭丸と信長が初めて出会う時のことが知りたい、と感じた。
演劇は滅多に観ることがないので、今回の機会は自分の感性を磨く意味でも貴重であった。
目の前の生身の人間が直接語りかけてくる、という点が映画とは違う迫力、説得力を持たせている。
それぞれの俳優さんのことをよく知るようになれば、さらに深い影響力を持って
響いてくるのではないかと思う。
ARCHEさんとは何度か会わせて頂いていることもあり、
彼が演じる利休の言葉は実際に、本当に信長の心、そして観客の心を動かしているように感じられた。
演劇をより楽しむためには、もっと何度も足を運んで観る必要があるのだろう。
そうして、自分自身もまた人の心を動かす存在になるために学びを得たい。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●個人面談(鳥越先生)
・現地、現場、現物
私に足りていない所である。
事業創造を考える上でも、その場の雰囲気や
現地の方のヒアリングなどの聞き込み調査は必須である。
また現物を買うことで、そこに行ったという証になる。
まずは、行動で示していけるよう取組んでいく。
・仮説をつくる
つまりは、結果(目標)を見据えて考えることが必要である。
現在、私が取組んでいる、「着物」や「鯉」は本当に事業として
やっていけるのかと考えた時に、スケールが大きいのではないかと感じる。
さらに、本当に、その事業がしたいのかと思うと、どうなのだろうと
疑問に思えてしまう。
よって、自分の気持ちに踏ん切りをつける為にも徹底して
調べつくして行くことが大切であると思う。
●『ちはやぶる神の国』
・歴史はロマン
今回、人生で初めての演劇を鑑賞させて頂いた。
主題は、「本能寺の変」であり、信長の命が短いと
わかるや、光秀に「私(信長)を殺すように」と命令したことが
演劇のあらすじである。
そして、「信長が両刀使いであったこと」、「信長の家来に黒人がいたこと」など、
歴史の多くはいろんな諸説が存在をしていることを学ばせて頂いた。
●感想
アーチェさんが演じた「千利休」は、謙虚でありながらも、出てくる度に
存在感を放っていた印象を抱いた。
また、今回は森蘭丸などを中心とした小姓衆の視点からの本能寺の変を
紐解いた演劇であったが、今後は違った視点から紐解いた本能寺の変も観たくなりました。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
---------------------------------------------------------
・現地、現場、現物
私に足りていない所である。
事業創造を考える上でも、その場の雰囲気や
現地の方のヒアリングなどの聞き込み調査は必須である。
また現物を買うことで、そこに行ったという証になる。
まずは、行動で示していけるよう取組んでいく。
・仮説をつくる
つまりは、結果(目標)を見据えて考えることが必要である。
現在、私が取組んでいる、「着物」や「鯉」は本当に事業として
やっていけるのかと考えた時に、スケールが大きいのではないかと感じる。
さらに、本当に、その事業がしたいのかと思うと、どうなのだろうと
疑問に思えてしまう。
よって、自分の気持ちに踏ん切りをつける為にも徹底して
調べつくして行くことが大切であると思う。
●『ちはやぶる神の国』
・歴史はロマン
今回、人生で初めての演劇を鑑賞させて頂いた。
主題は、「本能寺の変」であり、信長の命が短いと
わかるや、光秀に「私(信長)を殺すように」と命令したことが
演劇のあらすじである。
そして、「信長が両刀使いであったこと」、「信長の家来に黒人がいたこと」など、
歴史の多くはいろんな諸説が存在をしていることを学ばせて頂いた。
●感想
アーチェさんが演じた「千利休」は、謙虚でありながらも、出てくる度に
存在感を放っていた印象を抱いた。
また、今回は森蘭丸などを中心とした小姓衆の視点からの本能寺の変を
紐解いた演劇であったが、今後は違った視点から紐解いた本能寺の変も観たくなりました。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
---------------------------------------------------------
●自分の強みとは
まず、1つ目に事業創造に必要なことは、日本ベンチャー大學の理念である
「志の明確化」から受けた「志の具体化」である。
「志の明確化」は立派なものではなく、1人が賛同してくれるような志で良いということである。
しかし「志の具体化」が弱いと、世間から評価されない、共感を得ることは出来ない。
そのため、志を達成するための熱意、そして、誰に何と言われようと
自分の事業に自信を持つことが最も大切なことである。
2つ目に必要なことは、日本ベンチャー大學の伝統を守るためにその根幹に関わる
事業創造を中途半端にしたり、未完成のまま、終わることはしてはいけないこと。
3つ目に必要なことは、自分の強みに気づいた上で、その自分の強みを生かし、
ビジネスプランのカスタマーバリューやビジネスチャンスの分析をするということである。
鳥越先生からは私の強みは感性が豊かなことであり、それを磨くために
色々な物や芸術などを楽しむ気持ちが必要だというアドバイスを頂いた。
4つ目がどんなことにもすべて前向きで、受け身の姿勢は取らないということである。
そして、5つ目が言い訳をしない、した約束は必ず守るということである。
以上の5つが今回、事業創造に取り組む上での基本的なことであり、
これら5つのどれが欠けても、しっかりと完成した事業創造は出来ない。
私の事業創造も鳥越先生や他の6期生のアドバイスのおかげでようやく、
アウトプット出来る段階まで来た後はそれを具体化していくことが必要である。
●『ちはやぶる 神の国〜異聞•本能寺の変〜』
織田信長をお付きの小姓の立場から描いた演劇を鑑賞させて頂いた。
内容は、織田信長を中心に荒木正重の裏切りから本能寺の変までの出来事を描いている。
他の人物にも焦点を当てていて、特に印象に残ったのがお市の方の回想である。
死んだ夫の浅井長政への切ない想いが伝わってきて感動しました。
他にも剣劇の凄さもさることながら、特に凄かったのが脚本でした。
本能寺の変までの過程は同じですが、織田信長が不治の病にかかっているという設定で
最期を迎える前にイエス•キリストのように自身が神になることを画策して
本能寺の変を起こしたというシナリオでした。
明智光秀は織田信長の命で謀反を起こしたということで、裏切り者という
悪いイメージを私の中で覆し、明智光秀がかっこ良く見えました。
演劇に出演していたアーチさんが仰っていたように戦国武将も人であり、
その生き様は何百年経った今でも私達の心に響くものがあると感じました。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
------------------------------------------------------
まず、1つ目に事業創造に必要なことは、日本ベンチャー大學の理念である
「志の明確化」から受けた「志の具体化」である。
「志の明確化」は立派なものではなく、1人が賛同してくれるような志で良いということである。
しかし「志の具体化」が弱いと、世間から評価されない、共感を得ることは出来ない。
そのため、志を達成するための熱意、そして、誰に何と言われようと
自分の事業に自信を持つことが最も大切なことである。
2つ目に必要なことは、日本ベンチャー大學の伝統を守るためにその根幹に関わる
事業創造を中途半端にしたり、未完成のまま、終わることはしてはいけないこと。
3つ目に必要なことは、自分の強みに気づいた上で、その自分の強みを生かし、
ビジネスプランのカスタマーバリューやビジネスチャンスの分析をするということである。
鳥越先生からは私の強みは感性が豊かなことであり、それを磨くために
色々な物や芸術などを楽しむ気持ちが必要だというアドバイスを頂いた。
4つ目がどんなことにもすべて前向きで、受け身の姿勢は取らないということである。
そして、5つ目が言い訳をしない、した約束は必ず守るということである。
以上の5つが今回、事業創造に取り組む上での基本的なことであり、
これら5つのどれが欠けても、しっかりと完成した事業創造は出来ない。
私の事業創造も鳥越先生や他の6期生のアドバイスのおかげでようやく、
アウトプット出来る段階まで来た後はそれを具体化していくことが必要である。
●『ちはやぶる 神の国〜異聞•本能寺の変〜』
織田信長をお付きの小姓の立場から描いた演劇を鑑賞させて頂いた。
内容は、織田信長を中心に荒木正重の裏切りから本能寺の変までの出来事を描いている。
他の人物にも焦点を当てていて、特に印象に残ったのがお市の方の回想である。
死んだ夫の浅井長政への切ない想いが伝わってきて感動しました。
他にも剣劇の凄さもさることながら、特に凄かったのが脚本でした。
本能寺の変までの過程は同じですが、織田信長が不治の病にかかっているという設定で
最期を迎える前にイエス•キリストのように自身が神になることを画策して
本能寺の変を起こしたというシナリオでした。
明智光秀は織田信長の命で謀反を起こしたということで、裏切り者という
悪いイメージを私の中で覆し、明智光秀がかっこ良く見えました。
演劇に出演していたアーチさんが仰っていたように戦国武将も人であり、
その生き様は何百年経った今でも私達の心に響くものがあると感じました。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
------------------------------------------------------
平成26年(2014)【10月25日(土)】 ブランディング学/浅井弘敏先生(株式会社ケイズグループ 人材開発室室長) 「ブランディング概念、セルフブランディング、ブランドの活用術」「華麗なる転身 vol.1」 幕末維新祭り 1日目
2014/10/25
コメント (0)
平成26年(2014)【10月23日(木)】 鞄持ちができる人の心得/山近理事長代行(本學) リアル経営学/黒松高弘先生(株式会社インデン 代表取締役社長)
2014/10/23
コメント (0)
平成26年(2014)【10月21日(火)】 事業創造/鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)
2014/10/21
コメント (0)
-------------------------------------------------
●1日の流れ
9:35 新聞アウトプット
9面「豪から東南アへ 小麦輸出合戦」
・日本の今後の動き。
・東南アはどう変わっていくのか?
6面「ゲイツ氏からザッカ―バーグ氏へ」
・米のIT世代交代で世界はどう変わっていくのか。
・日本はどう学ぶか。
10:45 鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)
による「事業創造 第7講」
・5年倍増計画
・インプット→アウトプット→ゴール
・気力からひねりへ
・「ホック」の新商品
11:45 昼休憩
12:45 事業創造
・アイデア出し&発表
14:40 休憩
14:50 事業創造 再開
・アイデア出し&発表
-------------------------------------------------
●ひねりを生み出す気力
どうやって売り上げを伸ばせばいいのか?
その方法は4通りしかない。
すなわち、新規顧客拡大、リピーター拡大、新商品販売、そして新規事業(多角化)である。
これらを達成するためには、今までと同じやり方ではなく、人・方法・仕組みを
変えて新しい活動に取り組まなければならない。
私たちにとって一番不足しているのは、インプットをどうやってアウトプットへ
つなげるか、という部分である。
そのためには、何とかして「ひねり」を生み出さなければならない。同時に、
ひねり出すための気力も必須である。
鳥越先生が紹介して下さったホックの画期的新製品の例も、ひねりを生み出すために
長い試行錯誤を必要とした。
何か役に立つアイデアはないか?と
日常的に探し出す姿勢が必要なのだと思う。
私は今回の発表で、久松農園の久松さんにお話を聞いたこと、それを元に
久松農園のビジネス内容をまとめたことなどを報告した。
久松さんが農業の現在の課題についていくつか指摘していたので、
そこからプランを考えていくのが良いだろうと思った。
また、子供に本当の野菜のおいしさを伝えることや、久松農園流の土壌環境の作り方を
パッケージ化することなど、メンバーからも面白いアイデアをもらうことが出来た。
あえて価格を高く設定されている商品をどうやって売るのかという点でも、
久松農園に学ぶべきところは大きい。
計画的にヒアリングや調査に取り組みながら、突破口を見出していきたい。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●1日の流れ
9:35 新聞アウトプット
9面「豪から東南アへ 小麦輸出合戦」
・日本の今後の動き。
・東南アはどう変わっていくのか?
6面「ゲイツ氏からザッカ―バーグ氏へ」
・米のIT世代交代で世界はどう変わっていくのか。
・日本はどう学ぶか。
10:45 鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)
による「事業創造 第7講」
・5年倍増計画
・インプット→アウトプット→ゴール
・気力からひねりへ
・「ホック」の新商品
11:45 昼休憩
12:45 事業創造
・アイデア出し&発表
14:40 休憩
14:50 事業創造 再開
・アイデア出し&発表
-------------------------------------------------
●ひねりを生み出す気力
どうやって売り上げを伸ばせばいいのか?
その方法は4通りしかない。
すなわち、新規顧客拡大、リピーター拡大、新商品販売、そして新規事業(多角化)である。
これらを達成するためには、今までと同じやり方ではなく、人・方法・仕組みを
変えて新しい活動に取り組まなければならない。
私たちにとって一番不足しているのは、インプットをどうやってアウトプットへ
つなげるか、という部分である。
そのためには、何とかして「ひねり」を生み出さなければならない。同時に、
ひねり出すための気力も必須である。
鳥越先生が紹介して下さったホックの画期的新製品の例も、ひねりを生み出すために
長い試行錯誤を必要とした。
何か役に立つアイデアはないか?と
日常的に探し出す姿勢が必要なのだと思う。
私は今回の発表で、久松農園の久松さんにお話を聞いたこと、それを元に
久松農園のビジネス内容をまとめたことなどを報告した。
久松さんが農業の現在の課題についていくつか指摘していたので、
そこからプランを考えていくのが良いだろうと思った。
また、子供に本当の野菜のおいしさを伝えることや、久松農園流の土壌環境の作り方を
パッケージ化することなど、メンバーからも面白いアイデアをもらうことが出来た。
あえて価格を高く設定されている商品をどうやって売るのかという点でも、
久松農園に学ぶべきところは大きい。
計画的にヒアリングや調査に取り組みながら、突破口を見出していきたい。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●アウトプットに必要なものは気力とひねり
鳥越先生は株式会社武蔵野さんの『5年倍増計画』
のお話について話された。
この『5年倍増計画』は、5年間で売上を倍増させる計画で、
方針や仕組み、人を変えるなど、やり方を変えないと達成出来ない。
とにかく、新たな事業を始めるには、
まずはデタラメでもいいから仮説を立てることが重要である。
マーケティングの基本は4つのアンゾフの市場開発戦略がある。
1つ目が新規客拡大、
2つ目がリピーター拡大、
3つ目が新商品、
4つ目が新規事業(多角化)です。
これら4つの要素が揃うことで市場開発競争で生き残ることが出来る。
鳥越先生からは日本ベンチャー大學での授業方針では知識(インプット)より
知恵(アウトプット)が重要だというアドバイスを頂いた。
いくら知識(インプット)ばかり身に付けても、気力とひねりが足りなければ、
良い知恵(アウトプット)、ビジネスプランは生まれないということである。
また、私の事業創造に関しては皆さんから貴重なアドバイスを頂いた。
そのアドバイスを参考にして、これからやる事として、まずは自分の事業と類似した
スクーやマナビーの教育や教材を研究すること。
そして、現場に行く(ヒヤリング)をすることで自分のビジネスプランが
より具体性のある迫力のあるプランになると学びました。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
------------------------------------------------------
鳥越先生は株式会社武蔵野さんの『5年倍増計画』
のお話について話された。
この『5年倍増計画』は、5年間で売上を倍増させる計画で、
方針や仕組み、人を変えるなど、やり方を変えないと達成出来ない。
とにかく、新たな事業を始めるには、
まずはデタラメでもいいから仮説を立てることが重要である。
マーケティングの基本は4つのアンゾフの市場開発戦略がある。
1つ目が新規客拡大、
2つ目がリピーター拡大、
3つ目が新商品、
4つ目が新規事業(多角化)です。
これら4つの要素が揃うことで市場開発競争で生き残ることが出来る。
鳥越先生からは日本ベンチャー大學での授業方針では知識(インプット)より
知恵(アウトプット)が重要だというアドバイスを頂いた。
いくら知識(インプット)ばかり身に付けても、気力とひねりが足りなければ、
良い知恵(アウトプット)、ビジネスプランは生まれないということである。
また、私の事業創造に関しては皆さんから貴重なアドバイスを頂いた。
そのアドバイスを参考にして、これからやる事として、まずは自分の事業と類似した
スクーやマナビーの教育や教材を研究すること。
そして、現場に行く(ヒヤリング)をすることで自分のビジネスプランが
より具体性のある迫力のあるプランになると学びました。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
------------------------------------------------------
●事業創造
・アンブフの市場開発戦略
これは、マーケティングの一種であり、
①新規顧客拡大、②リピーター拡大③新商品、④新規事業(多角化)の4つである。
この4つを意識した新しい活動をすると、売上高が増加するということを学んだ。
実際に、「武蔵野」さんが、"5年倍増計画"という経営方針に活かされている。
そして、この経営方針をした事によって、500社中、2割の企業が、
売上高が増加したことも教えて頂いた。
これらを教わったり、学んだりすることは、自分の事業創造に非常に刺激になる。
しかしながら、私の事業創造は、まだまだ完成まで辿りつけていない。
そのために、初歩段階として事業計画を詰めていくことから始めていきます。
・インプット~アウトプット
事業創造では、「インプット」は"情報"
「アウトプット」は"活用"と呼ぶ。
それを踏まえて、私の事業創造は活用まで辿りつけていないことを知った。
「なぜ」「どうして」と悩んだが、それは、内容に具体性やイメージできない、
さらには迫力不足であることが、大きな要因である。つまりは、
具体的な数字やグラフなど視覚の情報がないからであるという。
では今後の事業創造は、その課題である「数字」や「グラフ」などの
視覚の情報を活用することをしていく。そうすれば、相手も意見が言いやすくなり、
自分自身も分かりやすく、伝えることができると思う。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
---------------------------------------------------------
・アンブフの市場開発戦略
これは、マーケティングの一種であり、
①新規顧客拡大、②リピーター拡大③新商品、④新規事業(多角化)の4つである。
この4つを意識した新しい活動をすると、売上高が増加するということを学んだ。
実際に、「武蔵野」さんが、"5年倍増計画"という経営方針に活かされている。
そして、この経営方針をした事によって、500社中、2割の企業が、
売上高が増加したことも教えて頂いた。
これらを教わったり、学んだりすることは、自分の事業創造に非常に刺激になる。
しかしながら、私の事業創造は、まだまだ完成まで辿りつけていない。
そのために、初歩段階として事業計画を詰めていくことから始めていきます。
・インプット~アウトプット
事業創造では、「インプット」は"情報"
「アウトプット」は"活用"と呼ぶ。
それを踏まえて、私の事業創造は活用まで辿りつけていないことを知った。
「なぜ」「どうして」と悩んだが、それは、内容に具体性やイメージできない、
さらには迫力不足であることが、大きな要因である。つまりは、
具体的な数字やグラフなど視覚の情報がないからであるという。
では今後の事業創造は、その課題である「数字」や「グラフ」などの
視覚の情報を活用することをしていく。そうすれば、相手も意見が言いやすくなり、
自分自身も分かりやすく、伝えることができると思う。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
---------------------------------------------------------

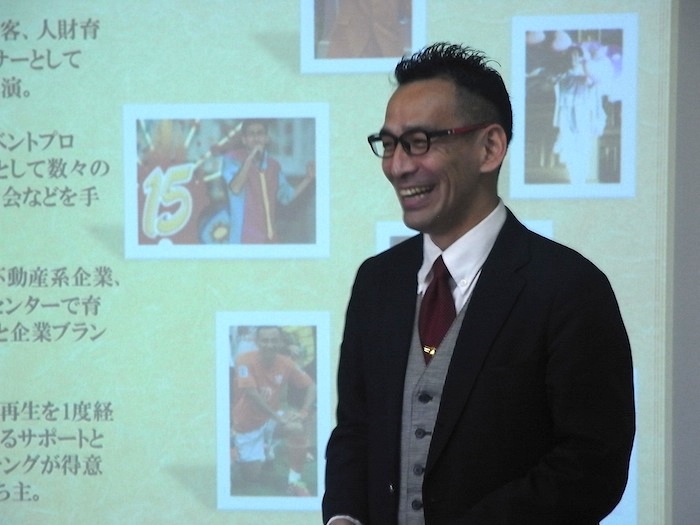
















 RSS 2.0
RSS 2.0












