東京校の講義レポート
平成26年(2014)【1月26日(日)】 李秀賢さん追悼(新大久保駅)
2014/01/26
コメント (0)
 ●李さん追悼
●李さん追悼 2001年の1月26日に新大久保駅構内で人命救助の犠牲で亡くなられた
李さんを追悼する。
この事故で亡くなったのは
線路に落ちた人とその人を助けようとした
韓国人の李さんと日本人の関根さんの3名である。
この日は運よく李さんの両親が
実際に新大久保駅で追悼されている場面に
遭遇することができた。
勇敢な行動だと感じるが
現在の日韓関係を考えると
国同士の友好につながっていないのが残念だ。
大切なのはこういった事故があったことを忘れないことであり
勇敢な姿に少しでも近づく努力をすることではないかと感じた。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
●李さんの追悼
新大久保駅で線路に落ちた男性を助けようとして亡くなられた
李さんの追悼をした。
この事件の影響で線路のホームの下の空間に逃げ込めるスペースが出来たり、
この事件を題材にした映画が出来たり、
日本からお見舞い金をお送りし、ご両親が受け取ることは
できないからと留学生促進の団体に寄付するなど
日本と韓国の良い意味での国際問題に発展したりと大きな影響を世界に与えた。
人一人の勇気で世界が変わったんだな、と思うと胸が熱くなる。
自分だったら打算も何もなく飛び込めるかと思った時、
ホームで様子を見ていたという他の方と同じだったのではないかと思う。
また、同時にカメラマンの方も飛び込まれたそうだが、
あまり騒がないでくれ、とご両親がいわれたのもあり、
あまりそちらには注目されなかったそうだ。
だが、この事件には確かに二人の命を落とすかもということを
忘れるほどの気持ちで人を助けようとした変わることのない
優しさがあったのは確かだ。
私もそんな勇気の持てる大人になっていく。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
●李秀賢さんという留学生が居た事
自分はこのように思ってくれる人がいる中で、
日本にいて胸を張った行動が出来ているのか
先ずその事を恥じました。
また、今回の事が無ければ
きっと詳しくはこの事件の事を知ろうとしなかった事もあり、
とっさにこういった行動が出来る勇気や、
この時は亡くなってしまったが、
しかし、これがきっかけとなり、
線路のそばに逃げる場所が出来たり、
落ちない為のガードが設置されたりと、
様々なきっかけとなっているのでは無いかと
山近社長から教えていただいた。
今でも線路に落ちてしまった人を助けている人は大勢いる、
自分がそういった所に遭遇したときに、
とっさに動けるような勇気を持ちたいと
今回の事を知り強く感じた。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
---------------------------------------------------------
●李秀賢さんが教えてくださること
山近理事長はご自身の個人的な事故がきっかけで
この機会を作ったといおっしゃっていたが、
この日の追悼がきっかけで学べたことは多かった。
一口に留学生と言っても、日本への外国人留学生は、
大学等に通う留学生と、日本語学校に通う就学生に分かれるという。
就学生には定期の学割制度が適用されないなど、
留学生との差ができている。
李さんは当時、日本に来ていた就学生だった。
事件がきっかけで祖国の家族の元に見舞金が集まり、
それから就学生への奨学金が生まれたという。
アルバイトをするとき、この事故が起きた新大久保を
通り過ぎたとき、日本にも多くの留学・就学生が学んでいることを実感する。
例えば日本と韓国。
外交で揉めている問題はあるが、こうして日本に学びに
来ている方には心からの、一人の人間としての関わりをしなければならない。
李さんは教えてくださった。
この日に、学び、考えることができた人はどれだけいるのだろう。
忘れてはならない日だと思った。
●勉強会
山近理事長が勉強会の時間を作ってくださった。
ベンチャー大學で学んだことを振り返る機会となり、
株式会社ミウさんの入社一年目の三人の、社会人経験談も
聞くことができた。
もう卒業、社会に出る準備の時期だ。
そのこと、整理し、考えるきっかけとなった。
学ばせていただいた講義を振り返り、今後に活かす。
必ずこれからに結びつけなくてはならない。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
-------------------------------------------------------------------------
平成26年(2014)【1月25日(土)】 日本のかたち/ 小田村四郎先生(松陰先生の妹の曾孫、元拓殖大学総長)
2014/01/25
コメント (0)
 --------------------------------
--------------------------------●1日の流れ
9:00 朝礼
9:15 会場セッティング、掃除
10:00 山近義幸理事長による挨拶
・学生にポストカードのプレゼント
・皇居内見学について
・小田村四郎先生についての紹介
10:15 小田村四郎先生「日本のかたち」
自己紹介
・ご自身の血筋について
・講義の概要
①ご自身の歩んできた人生
戦時中の体験談
・支那事変から
・出陣賦
・軍隊に行くのを喜ぶ人はいない
・大学で勉強することとの葛藤
・軍人勅諭の暗記
・教育勅語の暗記
・四書五経の暗記
→年を経るごとに価値が増してくる。戦前の教育法に、改めて向き合うべき。
拓殖大学、総長時代
・学校の歴史、伝統を復活させたかった。
・教授会をどうすべきか
②吉田松陰先生について
ご自身と吉田松陰先生の血筋
・松陰先生の妹、寿子の曾孫
松陰先生の人生
・松陰先生の生涯
・松陰先生の書き記したもの
→士規七則の時代、松陰先生の教育がもっとも充実していた。
・松陰先生は正直
・父と兄に捧げた詩が立派
・松陰先生の文章は原文で読むべき
→迫力が違う
③現代の世界情勢
アメリカ、中国との関係
・尖閣諸島問題
・安部首相の靖国参拝は、あくまで国内問題
・内政干渉をすべきではないと、日本は世界にはっきり言うべき
・個別自衛権と集団的自衛権がバラけているのは日本だけ
・教科書検定について
12:30 昼食、小田村四郎先生への質問タイム
・吉田松陰先生の血を引く者としての人生
・拓殖大学総長時代のお話
・台湾との関わり
・李登輝友の会について
・中條高徳学長との交友
13:30 今元局長による総括
・質問力を磨くこと
・今後の新たな事業について
14:15 掃除、終礼
--------------------------------
●小田村四郎先生
経歴と血筋のすごさから、一体どんな人なのか?と
思っていましたが、とても物静かな上に、謙虚な方で驚いた。
目標が無いまま進んだ、とおっしゃられていたが、
大学の総長になられた時は、
おかしな教授ばかりだったので、
まともな人に入れ替えようと動かれていた話や、
教育勅語や四書五経等を意味も
分からないまでも良いからとにかく暗記し、
それらが、後から血肉となって生きてくると言うお話をしてくださった。
昭和の世代の方々からは、
為になる書物の素読や暗記をするようにとよく聞く。
今の若者に必要な事だと教えてくださっているのだと知り、
温故知新の大切さを感じた。
●松陰先生の妹の曾孫
すごすぎる方を先祖にもった、とご自身が言われ、
その略歴をお話しくださいましたが、
やはり思い入れがあるのが分かる
熱の入ったしゃべり方をされていた。
話している間の表情や、しゃべり方も
あった事は無いですが、
松陰先生もこういった分だったのではないか?と感じ、
具体的に松陰先生に近づけたと実感しました。
また、文章を是非原文で読んでほしいと
おっしゃられていたのが印象的だった。
自分たちは特に、原文に触れやすい環境に
今居るので、改めて読み迫力を感じたいと思った。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
---------------------------------------------------------
 ●小田村四郎先生
●小田村四郎先生とにかく謙虚な方でした。
ご自身、昔は目標がなかったと、私たちの前でも謙遜されていた。
控えめな先生であるだけに、華やかな履歴を見れば
どれだけ周囲に慕われる立派な方なのかがわかる。
ご自身の、戦争を通した人生のお話をしていただいた。
やはり戦争は、経験者の方からのメッセージが一番伝わってくる。
当時の背景や声が想像できるからだ。
それだけでも貴重な経験をさせていただいた。
昔は軍人勅諭、教育勅語、四書五経などを、意味のわからない
小さな頃から暗記させられたという。
しかし四書五経など、始めはわからなくても歳を重ねる毎に意味が
身に染みてきて、血肉となっていったというお話があった。
そのような教育も、改めて考え直すべきだとも、おっしゃっていた。
戦争体験者の方は、揃って教育勅語、四書五経などを勉強すべきと
おっしゃっているように感じる。
私も読んでみなければならない。
先生は拓殖大学の総長にもなり、学校の昔からの素晴らしい伝統を
復活させようとなさった。
過去の素晴らしいものを再考し、必要ならば生き返らせる。
人生の大先輩のお話には、現代社会にとっての、宝のようなヒントが
眠っているのだと思った。
●吉田松陰先生ご実家の家系
小田村先生は吉田松陰先生の妹さんの曾孫にあたる。
松陰先生の歩んだ道のお話もしていただいたが、血を引く方の
お話という意味が大きかったと思う。
子孫としての気概を感じた。
吉田松陰先生はとにかく正直だった、約束を果たす義理人情に厚い方
だったなど、先生の性質をわかりやすく話してくださり、
具体的人物像に近づくことができる内容だった。
また、松陰先生についての最後のメッセージが非常に印象に残った。
先生の残した文章は、ぜひ原文で読んで欲しいという。
迫力が違うのだ、と熱意を奮って語ってくださった。
ご子孫だからこその、伝えたいことなのだと感じた。
必ず原文でも読み、これからも吉田松陰先生については深く勉強していく。
●日本と世界の今
元官僚の小田村先生は、現在の日本と世界の情勢、政治や外交に関しても
しっかりとしたご自身の意見を持っていらっしゃる。
日本、アメリカ、中国、韓国。
尖閣諸島や靖国神社の参拝問題。
過去の歴史や現在の動きまで総括した上での、確固たる意見のように思えた。
例えば中国はかつては尖閣諸島を日本の領土だと認めていたという。
現在の軍人の考えが旧代以前のものなのではとおっしゃっていた。
安部首相の靖国神社参拝問題も、それはあくまで国内問題。
外国はそもそも口を出すべきでなく、それをしてしまったら独立国では
なくなるということだった。
凄い。
私は正直、内容に最後まではついていくことができなかった。
今、改めて勉強していく必要があることを実感させられた。
過去や現在のことを、未来を見通すために一層取り込んでいく。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
 ●山近社長挨拶
●山近社長挨拶 小田村先生の講義の前に山近社長が
学生に向けてお話をしてくださった。
富山県高岡市で日本の二宮金次郎の銅像の8割が作られているということ、
皇居に3つの門あり中に入ることができるということなど
お話ししてくださった。
お忙しい中でも現地に行くということを実践なさっている。
そしてお忙しい中で学生のために時間を作って
お話をしてくださっている。
今の自分のできていないことなどを思い返すと
恥ずかしくなった。
やるべきことをきちんとやろう。
●小田村先生講義
まずは先生の人生に沿ってお話をしてくださった。
印象的だったのは若者の戦争への覚悟として
自分たちだけ勉強してはいられない、
という気持ちがあったようだ。
同じ国の人間が戦争をしている中で
自分だけが安全な場所で勉強をしていることへのもどかしさ、
自分が何もできないことにもどかしさを感じることは今の時代でもあるが
当時の日本国民としての意識の高さは今は失ってしまったものかもしれない。
また拓殖大学での総長として今の教育への問題意識もお話ししていただき
今の大学の教授会は改革をすべきであり
教えるべきでない人間が教授をしているとのことだった。
松陰先生についてのお話もしていただき
講孟余話や士規七則などを復習できた。
小田村先生は「松陰先生の原文に触れてこそ松陰先生を知れる」
とおっしゃっていたのがとても大切なことだと感じた。
現在の対外情勢についても
尖閣問題や慰安婦問題、竹島問題など
もっと積極的に考え解決に導く
旧態依然の体質から脱却した行動が必要なようだ。
歴史について勉強し、現在の国際情勢を知り
問題意識を持って解決に向けて取り組むことが必要だと感じた。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
 ●小田村先生の講義
●小田村先生の講義初めにご自分の経歴を淡々と話されていたが、内容が戦争へ行ったことで
学徒出陣の出陣前に歌う出陣賦があったと言うお話や、
その後大蔵省へ入ってご活躍され、防衛庁へも出向されたり、
拓殖大学の総長になられたお話など、とんでもなく濃かった。
目標がないままたまたま入れたところへ進んだ、とおっしゃっていたが、
おそらくたくさんの目標を持って、こつこつ達成されてきたのではないかと感じた。
拓殖大学の総長をされていた時に教育を変えようとされたお話も、
教授会が大きな権限を持っていて、そこを動かさなければどうにもならないと
おっしゃられていて、そこまで言われるにはどれだけやりあったのだろうか。
冷静でありながらも、内には熱を持っている方だと感じた。
国内情勢についてもお話頂き、靖国問題は国内の問題であり、中韓国が
文句を言うのは内政干渉だと言われた。
また、集団的自衛権についても国家固有の本質的な権利であるということで、
この部分の知識が浅かったので、
そうだったのか!と思い、勉強になった。
多少は知っているつもりだったが、まだまだ知らないことばかり学ばせて
頂いた。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
--------------------------------------------------------------------
平成26年(2014)【1月24日(金)】 コミュニケーション学/大西恵子先生(大西恵子事務所代表)
2014/01/24
コメント (0)
--------------------------------
●1日の流れ
09:00 朝礼、掃除
09:30 新聞アウトプット
1面「国民年金滞納者 差し押さえ」
どうすれば年金を払う人を増やすことができるかを議論
5面「ワイン手頃に」
関税が撤廃されるということで日本への影響を議論
10:00 大西恵子先生の講義
・クレームを直訳すると主張。
・昔は苦情と呼んでいた。クレームは対応する姿勢が大切なので呼び名が最近変わってきた。
・モノクレームは対応がしやすいが、サービスに対するクレームは対応しにくい。
・クレームはしっかり話を聞いて、出来ることと出来ないことを分けることが大事。
・クレームはどんなに頑張ってもゼロにはならない。
・クレームを聴く時は相手の調子や言い方、過去の経験にとらわれずに
何を一番主張したいのかを聞くことが大事。
・エゴグラムというクレーム対応時自分がどういうタイプか調べる質問に答える。
・タイプ別にクレーム対応の時の注意点を見る。
・おわびと謝罪は違う。おわびは相手の気持ちが波立っていることへの気遣い、
謝罪はこちらに落ち度がある時。
・「ありがとう」は3回以上、「ごめんなさい」は5回以上でなければ相手に伝わらない。
・最近、クレームが以前と性質が変わってきた。
13:10 お昼休憩
14:00 終礼
14:30 ポスティングのビラ折り、解散
--------------------------------
●クレームとは
クレームは捉え方次第で反応が変わってくる。
苦情とらえれば、処理となり、
主張と捉えれば、対応となる。
常に誠実な対応を取るためには、
相手の主張を聴き、相手に訊くことで、
より良いものにしていける。
そこを忘れないようにして対応していきます。
●クレーム対応
クレームの対応をするときに
5つのタイプ分けをする事で、
応対のやりやすさが簡単になる事を
教えていただいた。
また、自分がどういった傾向にある
人格なのかが、少し明確に分かり、
これからの他者への振る舞い等
気をつけるべき点が分かった。
とてもすんなりと胸に入って行った。
これらの事は、これからの職務上の
対人関係を進めて行く上で、
とても有用なものだと感じたので、
教わった事に注意し、少しずつでも
実際の行動に移しコミュニケーション力を上げて行きます。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
---------------------------------------------------------
●1日の流れ
09:00 朝礼、掃除
09:30 新聞アウトプット
1面「国民年金滞納者 差し押さえ」
どうすれば年金を払う人を増やすことができるかを議論
5面「ワイン手頃に」
関税が撤廃されるということで日本への影響を議論
10:00 大西恵子先生の講義
・クレームを直訳すると主張。
・昔は苦情と呼んでいた。クレームは対応する姿勢が大切なので呼び名が最近変わってきた。
・モノクレームは対応がしやすいが、サービスに対するクレームは対応しにくい。
・クレームはしっかり話を聞いて、出来ることと出来ないことを分けることが大事。
・クレームはどんなに頑張ってもゼロにはならない。
・クレームを聴く時は相手の調子や言い方、過去の経験にとらわれずに
何を一番主張したいのかを聞くことが大事。
・エゴグラムというクレーム対応時自分がどういうタイプか調べる質問に答える。
・タイプ別にクレーム対応の時の注意点を見る。
・おわびと謝罪は違う。おわびは相手の気持ちが波立っていることへの気遣い、
謝罪はこちらに落ち度がある時。
・「ありがとう」は3回以上、「ごめんなさい」は5回以上でなければ相手に伝わらない。
・最近、クレームが以前と性質が変わってきた。
13:10 お昼休憩
14:00 終礼
14:30 ポスティングのビラ折り、解散
--------------------------------
●クレームとは
クレームは捉え方次第で反応が変わってくる。
苦情とらえれば、処理となり、
主張と捉えれば、対応となる。
常に誠実な対応を取るためには、
相手の主張を聴き、相手に訊くことで、
より良いものにしていける。
そこを忘れないようにして対応していきます。
●クレーム対応
クレームの対応をするときに
5つのタイプ分けをする事で、
応対のやりやすさが簡単になる事を
教えていただいた。
また、自分がどういった傾向にある
人格なのかが、少し明確に分かり、
これからの他者への振る舞い等
気をつけるべき点が分かった。
とてもすんなりと胸に入って行った。
これらの事は、これからの職務上の
対人関係を進めて行く上で、
とても有用なものだと感じたので、
教わった事に注意し、少しずつでも
実際の行動に移しコミュニケーション力を上げて行きます。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
---------------------------------------------------------
●クレームは主張である
クレームとは。
クレームの直訳は「苦情」ではなく、「主張」。
その認識に尽きるのではないか。
まずはクレームをどう捉えるかの大切さを教えていただいた。
クレームにも様々な種類があり、サービスに関するクレームは
潜在化しやすいため、それを発言していただいた場合は
感謝すべきである。
またその表明には、常としてストレスが伴う。
クレームをどう考えるかによって、それはピンチでなく、
むしろチャンスに変わる。
具体的な対応方法も教えていただいた。
メラビアンの法則によって、人の印象は見た目に左右される。
しかしクレーム対応の場合は内容に注視するべきだという。
また、情報を多く仕入れないと適切な対応ができないため、
相手に話し切ってもらうことも重要なことだという。
聞く力の大切さも実感した。
クレームは、受ける方、表明する方
共に苦痛が伴うため、今まではきちんと向き合うことが
できていなかった。
しかしこの日のように細かく教えていただくと、
その感情面での負荷も減り、対処がしやすくなると思う。
今回の講義で学ぶことができたことはとても多い。
すぐには使いこなすことができないだろうが、それらは
実生活でも実践可能だと思う。
経験によって身につけていく。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
クレームとは。
クレームの直訳は「苦情」ではなく、「主張」。
その認識に尽きるのではないか。
まずはクレームをどう捉えるかの大切さを教えていただいた。
クレームにも様々な種類があり、サービスに関するクレームは
潜在化しやすいため、それを発言していただいた場合は
感謝すべきである。
またその表明には、常としてストレスが伴う。
クレームをどう考えるかによって、それはピンチでなく、
むしろチャンスに変わる。
具体的な対応方法も教えていただいた。
メラビアンの法則によって、人の印象は見た目に左右される。
しかしクレーム対応の場合は内容に注視するべきだという。
また、情報を多く仕入れないと適切な対応ができないため、
相手に話し切ってもらうことも重要なことだという。
聞く力の大切さも実感した。
クレームは、受ける方、表明する方
共に苦痛が伴うため、今まではきちんと向き合うことが
できていなかった。
しかしこの日のように細かく教えていただくと、
その感情面での負荷も減り、対処がしやすくなると思う。
今回の講義で学ぶことができたことはとても多い。
すぐには使いこなすことができないだろうが、それらは
実生活でも実践可能だと思う。
経験によって身につけていく。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
●気付き
「クレーム」というのは「主張」という意味であり
決して苦情という意味ではない。
そこには相手の伝えたいメッセージがあり
そこで正しい対応ができると
相手の「納得」や「良い評判」につながる。
しかしそこで悪い対応をすれば
「反発」や「悪い評判」につながってしまう。
大切なのはいかに肝心の情報を得られるかである。
メラビアンの法則では第一印象は「見た目」と「話し方」で
その93%が決まるが、クレーム対応においては
この93%に影響を受けないように気を付け、
残り7%の「内容」を正確に聴きとらなければ
ただペコペコ謝るだけの"苦情"の"処理"になってしまう。
冷静に内容を受け止め、クレームの対応をしなくてはいけない。
対応をするうえで大切なのは
最初の印象、相手のクレームの聴き方、結論へ向けての
自分の話し方、という3ステップを意識しながら
相手のクレームの中の
謝ってほしい、原因や理由を説明してほしい、対応策を提示してほしい、
という欲求の移り変わり把握することである。
こういった対応が信頼関係を生み出し
「理解」や「納得」からより良い関係が作れることが
クレーム対応の価値のある点だと感じた。
しかし勘違いしてはいけないのは
クレーム対応がチャンスと考えるのは大切だが
優先順位としてクレームの事前の防止が8割で対応は2割と
いうことを心掛けないと、いつまでもクレームが絶えなくなってしまう。
きちんと日頃の心がけの上に正しい対応技術を築かなくてはいけない。
今回一番学びになったのは
クレームの対応において肝心なのは情報であり
その情報を集めるために話を掘り下げる3つのきき方である。
「聴く」=listen to、相手の話を深く聞き出す、
「訊く」=ask、確認や質問など話の展開のかじ取り、
「聞く」=hear、必要のないことは聞き流す、
という3つの聴き方を駆使することで
相手の感情的なクレームから
ストレスをためることなく情報を集めることができる。
いずれにしてもクレーム対応では冷静さを保つことが大切であり
それは日頃から人と話す時の心がけから
培っていけるだろうと感じた。
クレームといえないような日頃の小さな会話でも
今回学んだことを生かし、積み重ねていく。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
「クレーム」というのは「主張」という意味であり
決して苦情という意味ではない。
そこには相手の伝えたいメッセージがあり
そこで正しい対応ができると
相手の「納得」や「良い評判」につながる。
しかしそこで悪い対応をすれば
「反発」や「悪い評判」につながってしまう。
大切なのはいかに肝心の情報を得られるかである。
メラビアンの法則では第一印象は「見た目」と「話し方」で
その93%が決まるが、クレーム対応においては
この93%に影響を受けないように気を付け、
残り7%の「内容」を正確に聴きとらなければ
ただペコペコ謝るだけの"苦情"の"処理"になってしまう。
冷静に内容を受け止め、クレームの対応をしなくてはいけない。
対応をするうえで大切なのは
最初の印象、相手のクレームの聴き方、結論へ向けての
自分の話し方、という3ステップを意識しながら
相手のクレームの中の
謝ってほしい、原因や理由を説明してほしい、対応策を提示してほしい、
という欲求の移り変わり把握することである。
こういった対応が信頼関係を生み出し
「理解」や「納得」からより良い関係が作れることが
クレーム対応の価値のある点だと感じた。
しかし勘違いしてはいけないのは
クレーム対応がチャンスと考えるのは大切だが
優先順位としてクレームの事前の防止が8割で対応は2割と
いうことを心掛けないと、いつまでもクレームが絶えなくなってしまう。
きちんと日頃の心がけの上に正しい対応技術を築かなくてはいけない。
今回一番学びになったのは
クレームの対応において肝心なのは情報であり
その情報を集めるために話を掘り下げる3つのきき方である。
「聴く」=listen to、相手の話を深く聞き出す、
「訊く」=ask、確認や質問など話の展開のかじ取り、
「聞く」=hear、必要のないことは聞き流す、
という3つの聴き方を駆使することで
相手の感情的なクレームから
ストレスをためることなく情報を集めることができる。
いずれにしてもクレーム対応では冷静さを保つことが大切であり
それは日頃から人と話す時の心がけから
培っていけるだろうと感じた。
クレームといえないような日頃の小さな会話でも
今回学んだことを生かし、積み重ねていく。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
●学び
クレームという言葉の意味が「主張」だというところに一番驚いた。
言葉の意味がわかっただけでもこれまでの捉え方、対応の仕方が
間違っていたことが分かった。
不満を持たれてクレームという主張をしているのだと考え、対応するようにする。
自分はクレームを頂いたときに、つい謝って場を収めようとする。
実際アルバイト先で怒った調子で何か言われると、何が一番
ご不満なのかを掴む前に
とりあえず「すみません」と言ってしまう。
それでは進歩がない。
何に対して不満なのか聞く、訊く、聴くという3つのきき方で
質問して掴み、相手の意に沿うように対応する。
それが一番誠意的だ。
また、同じようなことでクレームを言われたとしても、相手次第で
主張したい点が異なるということを頭に入れて
「前回こうだったからこうすればいい」などと思わず、お客様にしっかり向き合う。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
クレームという言葉の意味が「主張」だというところに一番驚いた。
言葉の意味がわかっただけでもこれまでの捉え方、対応の仕方が
間違っていたことが分かった。
不満を持たれてクレームという主張をしているのだと考え、対応するようにする。
自分はクレームを頂いたときに、つい謝って場を収めようとする。
実際アルバイト先で怒った調子で何か言われると、何が一番
ご不満なのかを掴む前に
とりあえず「すみません」と言ってしまう。
それでは進歩がない。
何に対して不満なのか聞く、訊く、聴くという3つのきき方で
質問して掴み、相手の意に沿うように対応する。
それが一番誠意的だ。
また、同じようなことでクレームを言われたとしても、相手次第で
主張したい点が異なるということを頭に入れて
「前回こうだったからこうすればいい」などと思わず、お客様にしっかり向き合う。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
●クレーム対応の3段階ステップ
クレーム対応のステップは、3段階に分かれる。
こちらが、相手の話を受け入れる良い「印象付け」をし、
言っている事をわかってあげようとする「聴き方」をしたら、
相手が納得のいく結論を「話す」。
良い「印象付け」をすると、うまくいけば相手の怒りを
鎮められる。具体的に、目線(相手の目をちゃんと見る)、
笑顔(で受け入れる)を気を付ければ、うまくいけば相手の怒りを
鎮められると大西先生はおっしゃっていた。
聴き方のコツは、相手に「最後まで話し切ってもらう」事。
相手が困っている事を最後まで聞かないと、
正しい情報を得られず、対策も間違えて更なるトラブルになるので
重要だ。
正しく聴き取って、最後は納得のいく結論を話す。
「相手は、自分の言ったことについてしか耳を傾けない」そうだ。
相手の言った事を、繰り返し言うことが重要。
「今、おっしゃったこの部分に対して・・・」と
聴き取った事を復唱していけば、相手は自分のクレームへ対策を
してくれたと感じる。
良い印象付けをし自分を信用をしてもらって、
次のステップの聴き取りができる。
最初から最後まで、クレーム対応で3つとも重要だと
学んだ。実践する。
●やはり「傾聴力」
クレーム対応で「きく」には、3種類ある。
相手の言っている事を正しく「聞く」事が重要で、
「それって○○という事ですか?」と確認事項を「訊く」事。
そして、話し合いに必要のない誹謗中傷などは「聴き」流す事。
これらを使い分けることにより、難しい対応も、ストレスを
溜めずに乗り切れる。
クレームを「きく」際は、この3つを思い出し、使い分けを行う。
大西先生、本当に有難うございました。
From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)
------------------------------------------------------------------------------------------
クレーム対応のステップは、3段階に分かれる。
こちらが、相手の話を受け入れる良い「印象付け」をし、
言っている事をわかってあげようとする「聴き方」をしたら、
相手が納得のいく結論を「話す」。
良い「印象付け」をすると、うまくいけば相手の怒りを
鎮められる。具体的に、目線(相手の目をちゃんと見る)、
笑顔(で受け入れる)を気を付ければ、うまくいけば相手の怒りを
鎮められると大西先生はおっしゃっていた。
聴き方のコツは、相手に「最後まで話し切ってもらう」事。
相手が困っている事を最後まで聞かないと、
正しい情報を得られず、対策も間違えて更なるトラブルになるので
重要だ。
正しく聴き取って、最後は納得のいく結論を話す。
「相手は、自分の言ったことについてしか耳を傾けない」そうだ。
相手の言った事を、繰り返し言うことが重要。
「今、おっしゃったこの部分に対して・・・」と
聴き取った事を復唱していけば、相手は自分のクレームへ対策を
してくれたと感じる。
良い印象付けをし自分を信用をしてもらって、
次のステップの聴き取りができる。
最初から最後まで、クレーム対応で3つとも重要だと
学んだ。実践する。
●やはり「傾聴力」
クレーム対応で「きく」には、3種類ある。
相手の言っている事を正しく「聞く」事が重要で、
「それって○○という事ですか?」と確認事項を「訊く」事。
そして、話し合いに必要のない誹謗中傷などは「聴き」流す事。
これらを使い分けることにより、難しい対応も、ストレスを
溜めずに乗り切れる。
クレームを「きく」際は、この3つを思い出し、使い分けを行う。
大西先生、本当に有難うございました。
From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)
------------------------------------------------------------------------------------------
平成26年(2014)【1月23日(木)】 サクラスタジオ掃除
2014/01/23
コメント (0)
 --------------------------------
--------------------------------●1日の流れ
9:00 サクラスタジオ集合、朝礼
9:15 新聞アウトプット
・1面 シニアが拓く
・11面 ネットと融合 成長維持
・6面 韓国 クレジット情報大量流出
10:30 サクラスタジオ掃除開始
12:30 終礼
--------------------------------
●サクラスタジオの掃除
普段からきれいにしてあり、
あまり目立った汚れは無かったが、
壁や細かい汚れ等出来るだけ掃除をさせていただいた。
2時間ほどだったが、予想よりも遥かに汚れがあり、
目には見えにくくとも
こうして徹底的に行なう事で見えてくる事もある。
毎年使わせていただいているので、
先輩達がやってくれたように、
自分も次の世代に向けての行動に
もう少しで卒業だということを意識しました。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
---------------------------------------------------------
 ●いま再びの感謝の掃除
●いま再びの感謝の掃除前回掃除していただいたのは4月だった。
入学まもない頃にサクラスタジオ感謝の掃除をさせてただいたが、
この日にも久しぶりに掃除をさせていただいた。
綺麗なスタジオだったが、窓の隙間など、汚れはまた見つかった。
前回も同じ場所をやった記憶がある。
時間が経つと埃がたまる。
塵はつもる。
汚れはできる。
それらはしっかり掃除をしていても、たとえばその、窓の隙間の
奥まったところなどにそのまま蓄積されていく。
気づかないところではない。
だからこそ私たちの掃除の価値があるのだろう。
感謝していただけるだろうか。
感謝していただけるまで、やる必要があると思う。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
 ●サクラスタジオ掃除
●サクラスタジオ掃除 先日講義をさせていただいたお礼に
サクラスタジオの掃除を行う。
そもそもがとてもきれいなスタジオなので
そこまで大それた掃除は必要ないが
窓枠の汚れやよく見ると床にも汚れがあり
雑巾がけを行う。
奇麗に見えてもよく目を凝らせば
磨いて落ちる汚れは意外とあった。
残り1時間くらいを残し
もう掃除するところもないだろうと思ったが
そこでやめてはお礼にならないと感じ、
さらに掃除すべきところを探すと
壁に汚れがあることに気付いた。
なんとなく落ちない汚れのように見え
見て見ぬふりをしていたが
磨いてみると落ちる汚れであることが分かった。
自分で勝手に終了を決めるのではなく
終了の時間までは何が何でも掃除する、
というような気持ちを持つことで
普段では気づかない部分や
行き届かないところまで
掃除ができるのだと感じた。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
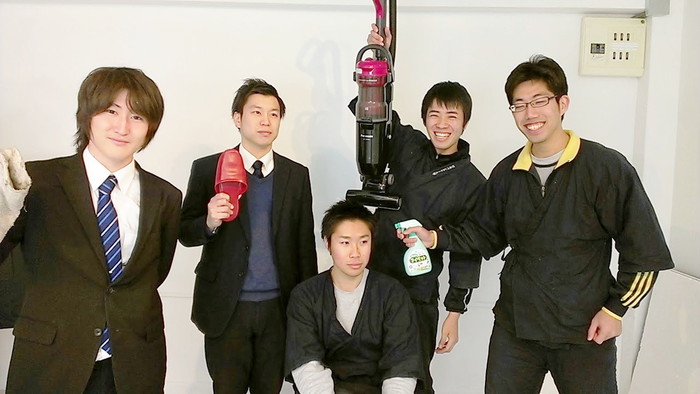 ●気付き
●気付き・新聞アウトプット
シニアについての記事を議論した際に海外で活躍されている
シニアの方による技術流出が問題になっていることを知った。
定年後の方が自己実現などをするために海外へ出て行き、
現地をよくすると言う話はたびたび聞いていたが、
それが技術流出になっているとは微塵も思っていなかった。
ただ良いことしているな、くらいしか思っていなかった。
もっと多面的に物事を見なければならない。
新聞を読む時、実際に 書かれている一面以外にどんな面があるのか考える。
・サクラスタジオ清掃
先日講義で使わせていただいたサクラスタジオを清掃した。
数日またいででも感謝の気持ちを形で表す実践をした。
サクラスタジオは見たところすごく綺麗で、掃除のしがいも
あまりないと思っていた。
掃除を実際に行ってみると、見えないところで汚れているところがあった。
普通にすごして掃除する分には気にもかけないような電気の上や、
壁などまでやってみると想像以上に時間がかかり、
結局2時間ほど掃除をしていた。
やるところがあまりないなど決めつけずに一生懸命やることを探すと、
思った以上に見つかるものだと感じた。
とにかく何か手をつけること、そしてそこからやれることを探すこと、
これは掃除以外にも応用できそうだ。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
平成26年(2014)【1月22日(水)】 HR(事業創造ブラッシュアップ、発送学)
2014/01/22
コメント (0)
----------------------------------------------
●1日の流れ
09:00 朝礼
09:10 松陰神社参拝
9:25 掃除
09:30 新聞アウトプット
「電子マネー」今後の展開
「理系人材、産学で育成」理系の人材育成が進む
「ゲーム大手中南米攻略」娯楽がこれから需要が増えて行くのではないか
10:50 昼休憩
12:00 事務局田中さんによる事業創造のブラッシュアップ
●8分間のプレゼン
・高岸「放置自転車ビジネス」
→なぜやりたいか、社会でどう役に立つか?などをもう少し考える。
・牛島「ワークショット」→どんな形にするかを決める。
松本さんに頼み実際に撮影してみる。
・佐藤「芸術家向けシェアハウス」→廃校などを見に行き、資金が溜まれば、すぐにでもできるように準備する。
クラウドファインディングも視野に含める。
・大森「塾の経営」→とんがった経営方針を考える。
14:00 発送作業サポート
15:00 掃除、終礼
------------------------------------------------------------------
●進む方向
事業創造のアドバイスを田中さんに頂き、進めていく方向が定まった。
やりたいことは決まっているのだが、どのように良くしたらいいか
分からず、行き詰まっていた。
その様なときに田中さんに、状況打開のご指導をいただいた。
自分がどれだけ堅い頭で考えていたかがわかる。
もっと広い視野を持たなければならない。
まずはアドバイスをいただいた通りに進めていく。
その上で、機会ある度に、色々な人に意見を聞いてみる。
事業創造を常に頭の隅に置いておく必要があるだろう。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
●1日の流れ
09:00 朝礼
09:10 松陰神社参拝
9:25 掃除
09:30 新聞アウトプット
「電子マネー」今後の展開
「理系人材、産学で育成」理系の人材育成が進む
「ゲーム大手中南米攻略」娯楽がこれから需要が増えて行くのではないか
10:50 昼休憩
12:00 事務局田中さんによる事業創造のブラッシュアップ
●8分間のプレゼン
・高岸「放置自転車ビジネス」
→なぜやりたいか、社会でどう役に立つか?などをもう少し考える。
・牛島「ワークショット」→どんな形にするかを決める。
松本さんに頼み実際に撮影してみる。
・佐藤「芸術家向けシェアハウス」→廃校などを見に行き、資金が溜まれば、すぐにでもできるように準備する。
クラウドファインディングも視野に含める。
・大森「塾の経営」→とんがった経営方針を考える。
14:00 発送作業サポート
15:00 掃除、終礼
------------------------------------------------------------------
●進む方向
事業創造のアドバイスを田中さんに頂き、進めていく方向が定まった。
やりたいことは決まっているのだが、どのように良くしたらいいか
分からず、行き詰まっていた。
その様なときに田中さんに、状況打開のご指導をいただいた。
自分がどれだけ堅い頭で考えていたかがわかる。
もっと広い視野を持たなければならない。
まずはアドバイスをいただいた通りに進めていく。
その上で、機会ある度に、色々な人に意見を聞いてみる。
事業創造を常に頭の隅に置いておく必要があるだろう。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
●事業創造by田中さん
今まで事業創造の講義では
鳥越先生のアドバイスが主だったが
講義としての時間をとって田中さんからご指摘をいただけたことは、
違った視点や違った意見があり勉強になった。
今までの事業創造で当たり前のように受け入れていたことも
田中さんから新しく質問や指摘をされることで
実現するのが難しいことや非現実的なことに
気づかされる部分も多かった。
色々な人からの意見を聴くことが
いかに効果的かよくわかった。
自分の事業創造についても
鳥越先生以上にはっきりとダメ出しをして頂いたので
自分の事業創造がいかにダメかを自覚することができた。
改めて時間を作り、頂いたアドバイスをもとに
事業創造を見直して卒業に向けて取り組む。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
●事業創造のブラシュアップ
何ヶ月も続けて来た事業計画のブラッシュアップは
何度も聞いている人より、初めて聞く人に話す事で、
よりどこが足りていないかが明確になった。
何のために、なぜこれをやるのか?という
思いの部分が自分はしっかりと描けていなかった事が
ぼんやりとした物になってしまっている一因だと
ご指摘を頂きました。その部分を今月中に詰めて行きます。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
---------------------------------------------------------
今まで事業創造の講義では
鳥越先生のアドバイスが主だったが
講義としての時間をとって田中さんからご指摘をいただけたことは、
違った視点や違った意見があり勉強になった。
今までの事業創造で当たり前のように受け入れていたことも
田中さんから新しく質問や指摘をされることで
実現するのが難しいことや非現実的なことに
気づかされる部分も多かった。
色々な人からの意見を聴くことが
いかに効果的かよくわかった。
自分の事業創造についても
鳥越先生以上にはっきりとダメ出しをして頂いたので
自分の事業創造がいかにダメかを自覚することができた。
改めて時間を作り、頂いたアドバイスをもとに
事業創造を見直して卒業に向けて取り組む。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
●事業創造のブラシュアップ
何ヶ月も続けて来た事業計画のブラッシュアップは
何度も聞いている人より、初めて聞く人に話す事で、
よりどこが足りていないかが明確になった。
何のために、なぜこれをやるのか?という
思いの部分が自分はしっかりと描けていなかった事が
ぼんやりとした物になってしまっている一因だと
ご指摘を頂きました。その部分を今月中に詰めて行きます。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
---------------------------------------------------------
●新聞アウトプット
電子マネーについての記事で、WAONやnanacoが、想像以上に
利用されていて驚いた。
小銭がいらず、普通の買い物でポイントがたまるという面で
お得で便利だが、ここまで広がっているとは思っておらず、
今の社会についていけていないのだなと感じた。
これからビジネスの世界に身を置くので、身の回りをもっと
しっかり見て、感覚を掴む。
また、電子マネーの決済が日本独自ということも初めて知った。
これから アジア展開等も考えられるということだが、
治安が整ってからしか普及はしないのかなと思う。
改めて何も知らないことを知ったので、もっと勉強する。
●田中さんの事業創造
自分の事業を発表し、ほぼ初めて内容を聴いた田中さんにアドバイスを頂いた。
これまで私は、初めて自分の案を聞いて貰う人の前では
満足に紹介できたことがなかったので難しかった。
自分が考えた事業を人に話す機会はこれからも多々あると思うので、
改めて初めて話す人に理解していただくために
伝えなくてはならないポイントを整理する。
今回「自分がサービスを受ける側になって考えろ」というアドバイスを頂いた。
実際、サービスを受ける側になって考えると大きな欠点があった。
そのポイントを改善する策を考え、より良い事業計画を立てる。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
電子マネーについての記事で、WAONやnanacoが、想像以上に
利用されていて驚いた。
小銭がいらず、普通の買い物でポイントがたまるという面で
お得で便利だが、ここまで広がっているとは思っておらず、
今の社会についていけていないのだなと感じた。
これからビジネスの世界に身を置くので、身の回りをもっと
しっかり見て、感覚を掴む。
また、電子マネーの決済が日本独自ということも初めて知った。
これから アジア展開等も考えられるということだが、
治安が整ってからしか普及はしないのかなと思う。
改めて何も知らないことを知ったので、もっと勉強する。
●田中さんの事業創造
自分の事業を発表し、ほぼ初めて内容を聴いた田中さんにアドバイスを頂いた。
これまで私は、初めて自分の案を聞いて貰う人の前では
満足に紹介できたことがなかったので難しかった。
自分が考えた事業を人に話す機会はこれからも多々あると思うので、
改めて初めて話す人に理解していただくために
伝えなくてはならないポイントを整理する。
今回「自分がサービスを受ける側になって考えろ」というアドバイスを頂いた。
実際、サービスを受ける側になって考えると大きな欠点があった。
そのポイントを改善する策を考え、より良い事業計画を立てる。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------

 RSS 2.0
RSS 2.0












