東京校の講義レポート
【平成25年2月16(土)】 『卒業生による講義』 陳 韋仁くん(日本ベンチャー大學1期生、旭酒造株式会社)
2013/02/16
コメント (0)
 ●議事録
●議事録9:00 朝礼
9:20 掃除
9:45 新聞アウトプット
『1面・放棄地減らし農に活力』
『1面・開拓の道、一つじゃない』
『7面・閣僚の資産公開』
『11面・米グーグルCFOに聞く。社会の難問解決に投資』
11:00 昼休憩
12:00 日本ベンチャー大學1期生陳韋仁さんのお話
・陳さんの経歴
デザイナー⇒3000人の会社の秘書⇒軍曹(徴兵制のため)、島根大学生⇒
日本ベンチャー大學1期生⇒蔵人
・現在、旭酒造株式会社に勤務。
旭酒造の取り扱い商品は、日本酒の獺祭のみ。
大吟醸の分野ではNo.1のシェア。会社は年130%成長。
・米には2種類あり、食用米と酒米がある。
旭酒造さんは、酒米の山田錦を使用。
・大吟醸とは、米を50%以上削ったもの。
日本酒のランクでは最上位。
・獺祭の海外輸出国No.1はアメリカ。次いで、中国。
アメリカがNo.1の理由は、日本食ブームの為。
・日本酒は、月桂冠によって広く海外で知られるようになったが、
質にこだわったものではなかった為、日本酒へのイメージはいいものではなかった。
・海外の方は、良い日本酒を作れば評価してくれる。
・洋風料理の前菜と日本酒、中華料理と日本酒という組み合わせで、
今海外で日本酒が飲まれている。
・労働力の問題で日本酒はなかなか広まらないのが難点。
日本酒作りは重労働。
15:00 掃除
15:10 終礼、解散
 《思いが伝わる》
《思いが伝わる》本日は、旭酒造株式会社の陳さんに、講義をしていただきました。
陳さんは台湾の大学を卒業、徴兵で軍隊に入り、日系企業で勤務されました。
その後日本に留学し、旭酒造に入社され、現在は世界中で活躍されています。
日本ベンチャー大學1期生でもあります。
陳さんが旭酒造に入社したいと思った切っ掛けは、
旭酒造の唯一の商品である日本酒「獺祭」を飲み、
その美味しさに感動したためでした。
陳さんには、製法、歴史、海外での現状など、
獺祭と日本酒全般について、分かりやすい講義をしていただきました。
私が陳さんのお話から感じたことは、陳さんが単に知識が豊富というだけでなく、
本当に獺祭に惚れ込んでいるということと、
獺祭がナンバーワンの日本酒だという事実からくる自信です。
この2点に、親しみを感じられる陳さんの人柄、話し方が合わさり、
とても大きな説得力が生み出されて、伝わってきます。
私も陳さんを見習わせていただき、まずは自分の個性・人柄の特徴を掴み、
そして、自分の心からの思いを大切にし、伝えられるような人間になります。
《本当の質》
私は日本酒の香りは苦手でしたが、本日飲ませていただいた獺祭の香りは、
他の日本酒とは全く異なっていました。
陳さんのお話では、獺祭の製法は、教科書通りの一般的なものですが、
極力機械に頼らず、細部まで人の手により、
徹底したこだわりを持ってつくられています。
また、海外での日本酒事情についても、お話をしていただきました。
欧米では日本酒の人気は高まっており、
獺祭も、こだわりを持つお店を中心に扱われています。
一方台湾では、大手の会社が質が低い日本酒を輸出したため、
日本酒そのものが避けられるようになってしまいました。
そんな台湾の人でも、陳さんが獺祭を出して飲んでもらったところ、
他の日本酒とは全く違うという評判を得ることができたそうです。
食に関してはでは特にそうですが、感動を呼び起こすほどに質が高い商品は、
一度試してもらえば、長く深く愛されて残っていくということ、
そのためには、
細部まで手を抜かずに徹底してこだわっていく事が大切だと学びました。
From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生
『日本No.1の日本酒を造っておられる素敵な台湾人』
今回は、日本ベンチャー大學1期生の陳さんに、
これまで御経験された事を話して頂きました。
陳さんは現在、旭酒造株式会社で営業のお仕事をされています。
扱っている商品は日本酒『獺祭』のみ。
取り扱い商品は1点ですが、大吟醸で作られたお酒の市場ではダントツNo.1で、
年130%の成長を続ける『化け物』会社です。
自分は、日本酒について無知なので、お酒の種類である
大吟醸という単語の意味から教えて頂きました。
大吟醸とは、米を50%以下まで削ったものだそうです。
削ることで、米の真ん中にあるおいしい部分だけをお酒に使うことができます。
獺祭を試飲させて頂きましたが、すごく美味しいなと感じました。
今までの日本酒のイメージとはまるっきり違う味です。
陳さんもその味に惚れ込んで、入社を決意されたそうです。
今、旭酒造さんは、日本酒を海外に売り出していこうとされています。
現在の海外売上は10%のようですが、50%にあげていくと意気込まれています。
輸出先の第一候補はアメリカ。理由は、日本食がブームだから。
潜在的な需要があるようです!
日本の文化である日本酒を海外の方が飲んで喜んでくれると思うと、
僕も嬉しいです。飲むお酒の種類が増えることは、
楽しみも増えるということですので、陳さんのお仕事はすごく価値のあるものだと思います。
陳さんの出身は台湾です。日本歴史や民族性が好きで、
日本に来られました。
凄く勉強熱心な方で、そして、肩の力の抜けた親しみやすい方です。
陳さんを見ていて、海外に行って、
陳さんのように皆から愛されながら、そして仕事でも成果をあげるためには、
受け入れることと、自分の立ち位置・居場所を定めることだと感じました。
●今からやること。
→自分にやってくる出来事を、受け入れて、自己成長に繋げる。
From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生
今回は、日本ベンチャー大學1期生の陳さんに、
これまで御経験された事を話して頂きました。
陳さんは現在、旭酒造株式会社で営業のお仕事をされています。
扱っている商品は日本酒『獺祭』のみ。
取り扱い商品は1点ですが、大吟醸で作られたお酒の市場ではダントツNo.1で、
年130%の成長を続ける『化け物』会社です。
自分は、日本酒について無知なので、お酒の種類である
大吟醸という単語の意味から教えて頂きました。
大吟醸とは、米を50%以下まで削ったものだそうです。
削ることで、米の真ん中にあるおいしい部分だけをお酒に使うことができます。
獺祭を試飲させて頂きましたが、すごく美味しいなと感じました。
今までの日本酒のイメージとはまるっきり違う味です。
陳さんもその味に惚れ込んで、入社を決意されたそうです。
今、旭酒造さんは、日本酒を海外に売り出していこうとされています。
現在の海外売上は10%のようですが、50%にあげていくと意気込まれています。
輸出先の第一候補はアメリカ。理由は、日本食がブームだから。
潜在的な需要があるようです!
日本の文化である日本酒を海外の方が飲んで喜んでくれると思うと、
僕も嬉しいです。飲むお酒の種類が増えることは、
楽しみも増えるということですので、陳さんのお仕事はすごく価値のあるものだと思います。
陳さんの出身は台湾です。日本歴史や民族性が好きで、
日本に来られました。
凄く勉強熱心な方で、そして、肩の力の抜けた親しみやすい方です。
陳さんを見ていて、海外に行って、
陳さんのように皆から愛されながら、そして仕事でも成果をあげるためには、
受け入れることと、自分の立ち位置・居場所を定めることだと感じました。
●今からやること。
→自分にやってくる出来事を、受け入れて、自己成長に繋げる。
From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生
【平成25年2月15(金)】 『コミュニケーション学』 大西恵子先生(大西恵子事務所 代表)
2013/02/15
コメント (0)
 ●議事録
●議事録9:00 朝礼、掃除
9:50 新聞アウトプット
社説 政治家の円相場に対する発言
1面 アジア跳ぶ マネー逆流 欧米のむ
13面 ネット選挙ビジネス着々
3面 学生、再び大手志向
12:00 大西恵子先生「コミュニケーション学」
今回のテーマ「自発的なホウレンソウのためには?」
ホウレンソウ(報告・連絡・相談)とは?
報告…上司に仕事の結果や過程(過去のこと)を伝える。
連絡…自分の仕事の現状(現在のこと)を、上司に把握するために常に伝える。
相談…問題が起きたときや起きる前に、指示を仰ぐ(未来のこと)。
こんな対応をしていないか?
・締め切りが過ぎてからの連絡・報告
・悪い情報が後回しになってしまう、など。
…私情や人間関係が弊害になる→割り切りが必要
13:20 休憩
13:30 再開
報連相は4種類の仕事で変える必要がある。
A. 繰り返しの仕事…繰り返しに見えても状況は絶えず変化するので、
変化に気付き中間報告や確認をする。
B. スポット的に任される仕事…急に「○○の仕事を今日中にやってほしい」など指示される仕事。
力のある人に追加業務が集まるので、その人は自分の仕事と比べ優先順位の確認をして報連相が必要。
C. 上司の承認を得て取り組む仕事…他の仕事を考慮し、
自分から仕事を提案し上司の承認を得て取り組む。
D. 突発的なトラブルで出てきた仕事…躊躇せずに報告を。
原因分析や対策はその後にする。
14:25 ロールプレイング開始
1案件の書類を取引先に渡すよう自社の社長から受けたとき
2 案件の書類を相手先の社長に直接渡たす
3 クレームのお詫びに行く シチュエーション
・社会人になってメモは基本…正しく聞き取る、正しく伝える
・書類を渡すとき、公文書は相手に中身を確認して貰う
・相手先に行ったときクロージング?など挨拶などは全て自分から切り出す
・状況は想定通りとはいかない事がある。急ぎの書類を渡しに行っても相手が居ない場合でも、
すぐ電話で判断を仰ぐなど、状況を自分で判断し行動する。
仕事が出来る人のコミュニケーションとは?…3つの視点を持っている
(目的、相手、自己)
目的を押さえる、相手の状況を理解する、自己(伝える内容を正しく理解しているか、
伝え方の手順を理解しているか)
3つを押さえ状況判断し、臨機応変に報連相をする。
15:05 講義終了
15:20 終礼、終了
 《優先順位》
《優先順位》本日は、大西恵子先生に最終講義をしていただきました。
本日は、まず社会人と学生の違いについてワークショップをした後、
「報連相」について学び、
実際の会社での様々な場を想定してワークショップを行いました。
私もワークショップをしてみましたが、頭では分かっていたつもりでも、
その場で予想外の状況に置かれると、思うような行動は出来ませんでした。
相手がいることなので、全てが予定通りにいくわけではないと実感しました。
とっさの対応をするためには、相手が何を求めていて、自分が何をするべきか、
それぞれについて常に優先順位を設定しておくことが大切です。
まずはメモを活用して、何かある度に、しなければならないことを書き出し、
各項目ごとに相手と自分の目的を考えて、優先順位を決めていきます。
《コミュニケーション》
円滑なコミュニケーションをするために、
相手を理解し、思いやることはとても大切です。
ただ、それだけではコミュニケーションはできません。
報連相については、上司が忙しそうにしている時でも、今必要な用件なら、
私も大切なことをしているのだという気持ちで
声を出していかなければならないということを、本日学びました。
勇気がいることではありますが、
どのような伝え方をすれば正確で角がたたないのかという面で、
思いやりの気持ちも併用していきます。
相手のことを正確に理解し、
自分のことを正しく伝えるというコミュニケーションの基本目的は、
どのような場面でも必要だということと、
人生の様々な場面で実際に応用していくことができるということを、
これまでの大西先生の講義で学びました。
自分なりの応用も試しながら、活用していきます。
From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生
 『学生と社会人の違いについて』
『学生と社会人の違いについて』講義の中で、学生と社会人の違いについて考える時間がありました。
ベン大生同士、3人1組になって、話し合いました。話し合う項目は、
目的・経済・必要能力・評価・人間関係です。
大西先生に教えて頂いた答えと、自分達が考えたものは、
大部分は一致していました。
目的から順に先生の解答を書くと、
「分かる・できる」「援助・自律」「記憶力・実行力」「点数・実績」「選べる・選べない」です。
社会人の目的は、できる事。
知識があったり、頭で理解しているだけではなく、体を使って実行して、
実績を残すことが求められる。
学生とは雲泥の差があります。
4月に向け、学生モードから社会人モードに切り替えていきます。
『報告・連絡・相談とは』
今回、報告・連絡・相談の意味を初めて知りました。今まであやふやに理解しておりました。
報告とは、結果報告のこと。
連絡とは、現状報告のこと。
相談とは、問題が起きた時や起きる前に指示を求めること。
会社内で飛び交う言葉の本当の意味を理解することは、
仕事の成果をあげますし、コミュニケーションもよくなります。
今回学べて良かったです。今後、わからない言葉は調べる癖をつけます。
講義の中で、ついついやってしまう駄目なホウレンソウについて教えて頂きました。
「連絡するように言われていても、直接催促されるまで連絡するを取らないことがある」
「○日までに連絡する、と言っておきながら、連絡を忘れることがある」
「悪い情報の報告が、ついつい後回しになってしまう」
どれも心当たりがあることばかりでした…。
一人でも自分と一緒に仕事をする人がいれば、
上に書いたような事をしていてはいい仕事もいい関係も築けませしできません。
ホウレンソウの基本のチェックリストを先生から頂いたので、
逐次チェックして自分の振る舞いを改めていきます!
『自発的なホウレンソウを行うポイント』
ホウレンソウは、チームワークの強化に欠かせません。
先生から、チームワーク強化のために必要なホウレンソウのポイントを教えて頂きました。
まず、聞かれる前に自分から報告を行うこと。
そして、面倒がらず小まめに行うこと。
どんなに小さなことであっても密に行い、疑問があれば、
放置せず必ず質問・相談をする。
これが、ポイントです。これが、相手がして欲しい対応です。
普段、今元局長や事務局の方々と様々なやり取りをさせて頂いていますが、
今回、ホウレンソウのポイントを伺い、自分は求められている事が
あまりにできていなかったと感じました。
講義を通して、ホウレンソウの型を教えて頂いたので、後はやるのみです。
●実践すること
→ホウレンソウを小まめに行う!
From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生
【平成25年2月14(木)】 『事業創造』 鳥越昇一郎先生(マーケティングウイング鳥越事務所 代表)
2013/02/14
コメント (0)
 ●議事録
●議事録9:00 朝礼、掃除
9:50 新聞アウトプット
クレジットカードについて企業のメリット
ips細胞について
10:30 講義開始 講師:鳥越先生 事業創造
11:30 昼食
12:30 各事業創造の発表
16:00 講義終了
 【先に進む】
【先に進む】残すところ、後2回となった。
にも関わらず、私は事業創造を大きく変更した。
前回の鳥越先生の個人面談のアドバイスから、
オズボーンのチェックリストを参考にさせていただいた。
ここ二ヶ月ほど頭打ちになっていたのがなんとか解消できた。
本日の発表では、みんなからの反応も悪くなかった。
今回の経験を経て、とりあえず先に進む大切さを学んだ。
立ち止まって考えることももちろん大切であるが、少し戻って道を変えてみることも大切。
前回のままで卒業を迎えると、とってつけたような事業創造になっていただろう。
【パワーをもらう】
鳥越先生の最大の魅力は周りの方々を元気にし、やる気をださせることだと感じた。
現に今元さんもおっしゃっていたとおり、
鳥越先生はいつも前向きでネガティブな発言はあまりしない。
それが周りを元気にさせている。
この一年、鳥越先生からいただくパワーなしではここまでの事業創造は難しかっただろう。
あと二ヶ月を切ったが、最後まで前向きに楽しくやる。
From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生
最初に今元さんに[何でも屋さんはこれからの時代儲かる]という話をして頂いた。
「こんなビジネス良いだろう」と理想ばかり掲げず、
今の世の中で困っている事に対応する事業が1番だと言われ、
確かにおっしゃる通りだと感じた。
そして私の事業創造は「孫カフェ」という、若者である孫が
お年寄りのお話をお聞きし、接する場を設けたいと考えていた。
だが個人面談で鳥越先生に「DNAが繋がっていない孫を
代わりに可愛がるか」という事を言われ、
おっしゃる通りだと感じた。
お年寄り(お客様)の生きがいややりがいになるビジネスの方がいいと感じて、
この時期にビジネスプランを以前考えていたものに切り替えた。
とはいいつつも、第11講にして大幅に切り替えたので、
コツコツ事業プランを進めないと今の他の人の完成度の高い
ビジネスプランに追いつかない。
私の変えた事業はまだ「ビジネスの全体像が不明確」であったり
マーケティング(聞き込み)に徹する部分、ビジネスとして
事業化させる(収支を立てる)事が出来ていない。
事業の見直しを重ね、中身がまだ出来ていない部分を詰めて
急いで動かなければならない。
From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生
「こんなビジネス良いだろう」と理想ばかり掲げず、
今の世の中で困っている事に対応する事業が1番だと言われ、
確かにおっしゃる通りだと感じた。
そして私の事業創造は「孫カフェ」という、若者である孫が
お年寄りのお話をお聞きし、接する場を設けたいと考えていた。
だが個人面談で鳥越先生に「DNAが繋がっていない孫を
代わりに可愛がるか」という事を言われ、
おっしゃる通りだと感じた。
お年寄り(お客様)の生きがいややりがいになるビジネスの方がいいと感じて、
この時期にビジネスプランを以前考えていたものに切り替えた。
とはいいつつも、第11講にして大幅に切り替えたので、
コツコツ事業プランを進めないと今の他の人の完成度の高い
ビジネスプランに追いつかない。
私の変えた事業はまだ「ビジネスの全体像が不明確」であったり
マーケティング(聞き込み)に徹する部分、ビジネスとして
事業化させる(収支を立てる)事が出来ていない。
事業の見直しを重ね、中身がまだ出来ていない部分を詰めて
急いで動かなければならない。
From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生
『新聞アウトプット』今回は、新聞アウトプットに今元さんが来て下さいました。
今元さんは、僕たちが現象に惑わされず、本質を掴める人間になれるように、
新聞記事を使って講義してくださいます。
今回のテーマは、クレジットカード。
企業側は、なぜ消費者のクレジットカード決済を望むのか。
企業側にとってクレジットカードは、カード会社に手数料を払ったり、
消費者から直接現金でお金を頂けないなどデメリットがあります
なのになぜ企業はクレジットカードを導入するのか。
クレジットカードの本質はなにかを考えました。
今の時代は、企業が消費者の通帳から引き落としをかけても、
残高不足などでなかなか引き落とせないそうです。
これが一件だけならまだしも、それが積み重なったら、
莫大な未収が発生し、企業を圧迫します。(NHKの受信料がいい例です。)
それをクレジットカードは解消してくれるのです。
これがクレジットカードの本質です。
クレジットカードは、企業側の『未収の恐怖』という困りごとを解消する力があります。
困っている人を助ける事はビジネスになると教えて頂きました。
『事業創造』
事業には自分が反映されます。自分=事業です。なので、事業プランを考える作業は、
自分と向き合う作業になります。
ものすごい大変な作業ですが、そうしている時間はすごく濃い時間です。
そういった時間を過ごさせて頂けて本当に幸せです。
僕は、今回、事業プランを提出出来ないのではないかと思いました。
しかし、鳥越先生との面談で、それまでどうしていいのかわからなかった事や
もんもんとしていたものが一気に晴れました。
僕は、一人で考える癖があり、悩んでも相談せず、一人で苦しんでいました。
今回の面談で、初めて、人に相談することの大きさを体験しました。大きな気付きです!
今回、講義では、自分の事業プランを発表したのですが、重大な課題に気付きました。
それは、動くこと。自分の事業に関する生の情報を足で手で、
ネットで、インタビューを通してなど、ありとあらゆる方法を使って掻き集めること。
鳥越先生も仰られましたが、考えることも大事だが、暴れろ!
僕みたいな凡人は動くことだけが、ライバルに張り合える唯一の武器にも関わらず、
動きが全く足らない。
●卒業までに身につける能力→即動く!即!動く!
From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生
今元さんは、僕たちが現象に惑わされず、本質を掴める人間になれるように、
新聞記事を使って講義してくださいます。
今回のテーマは、クレジットカード。
企業側は、なぜ消費者のクレジットカード決済を望むのか。
企業側にとってクレジットカードは、カード会社に手数料を払ったり、
消費者から直接現金でお金を頂けないなどデメリットがあります
なのになぜ企業はクレジットカードを導入するのか。
クレジットカードの本質はなにかを考えました。
今の時代は、企業が消費者の通帳から引き落としをかけても、
残高不足などでなかなか引き落とせないそうです。
これが一件だけならまだしも、それが積み重なったら、
莫大な未収が発生し、企業を圧迫します。(NHKの受信料がいい例です。)
それをクレジットカードは解消してくれるのです。
これがクレジットカードの本質です。
クレジットカードは、企業側の『未収の恐怖』という困りごとを解消する力があります。
困っている人を助ける事はビジネスになると教えて頂きました。
『事業創造』
事業には自分が反映されます。自分=事業です。なので、事業プランを考える作業は、
自分と向き合う作業になります。
ものすごい大変な作業ですが、そうしている時間はすごく濃い時間です。
そういった時間を過ごさせて頂けて本当に幸せです。
僕は、今回、事業プランを提出出来ないのではないかと思いました。
しかし、鳥越先生との面談で、それまでどうしていいのかわからなかった事や
もんもんとしていたものが一気に晴れました。
僕は、一人で考える癖があり、悩んでも相談せず、一人で苦しんでいました。
今回の面談で、初めて、人に相談することの大きさを体験しました。大きな気付きです!
今回、講義では、自分の事業プランを発表したのですが、重大な課題に気付きました。
それは、動くこと。自分の事業に関する生の情報を足で手で、
ネットで、インタビューを通してなど、ありとあらゆる方法を使って掻き集めること。
鳥越先生も仰られましたが、考えることも大事だが、暴れろ!
僕みたいな凡人は動くことだけが、ライバルに張り合える唯一の武器にも関わらず、
動きが全く足らない。
●卒業までに身につける能力→即動く!即!動く!
From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生
【平成25年2月13(水)】 『本質思考』 坂本善博先生(株式会社資産工学研究所 代表取締役社長)
2013/02/13
コメント (0)
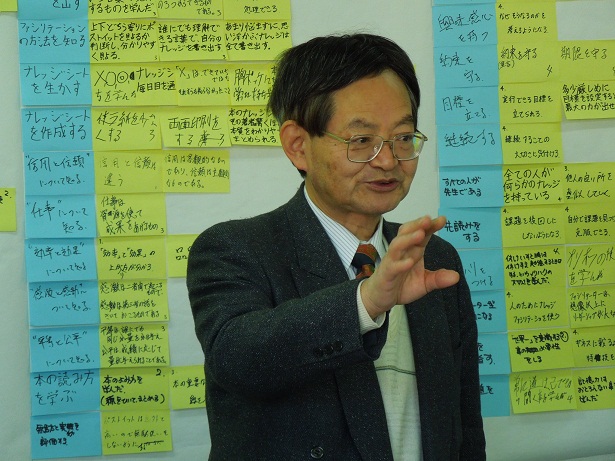 ●議事録
●議事録9:00 朝礼、掃除
10:00 講義
坂本 善博先生「ナレッジファシリテーション」
◎学生によるナレッジファシリテーションと坂本先生の解説
テーマ「坂本先生の講義で学んだこと」
1.マインド
・今が全て。
2.スキル
・書籍を読んだら、その全てを自分の血肉にする。
・物事を決める優先順位は、自分がやりたいことを基準にして決める。
・優先順位には、緊急度と重要度がある。
→ほとんどの人は、緊急に振り回されて重要をやらない。
・継続=目標を決め、シナリオを作り、方法論と技法を身につけることめできる。
・何年、何ヵ月、何日、何時間、何分、何秒と、残りの人生を数字にして、確認する。
1日、1秒を大切にできるようになる。
・何でもいいから、世界一になる。
3.ナレッジ
・立派な人は少なく、真似することも難しいが、ダメな人を反面教師として学ぶことはできる。
・世界一の人はどれだけ出来るのだろうかと想像してみる。
→複数人で出したナレッジは、世界一の人を超えることがある。
・人は、名刺、人脈、個人の中身で信頼される。今すぐできることは、中身を磨くこと。
・実効で判断する。
4.人間力
・人を見る目は、永遠のテーマ。
・「ファシリテーター」型のリーダーは、何をしろと指示しなくても部下が動いてくれる。
◎ナレッジシートを活用する。
・みんな1度はやるが、2回目をやるかで差がつく。
・身の丈に合ったものを、まずは身に付ける。本質はどれも同じ。
・自分で書き直し、付け足す。
・携帯しやすいように工夫する。
・達成状況を工夫しながら記録する。
・他己評価をしてもらう。シートを交換してつける。
→相手を磨き、自分を磨く。
・ナレッジシートがあれば、1人でもナレッジファシリテーションができる。
→この場合は、通常とは逆に、原理原則から連想していく。
・関係なさそうな現象のシートでも、普遍的な本質は他のことに適用できる。
・ファシリテーションの時間以外でも、学んだことはすぐに書き出す。
・与えられるままではなく、自分で改良する。
・後ではなく、途中で考える。
・卒業してからも、少なくとも3年は続けてほしい。
13:30 休憩
14:20 新聞アウトプット
・1面ほか「北朝鮮の核実験」
・4面「企業の農業参入1000件超」
15:00 掃除、終礼、解散
 《継続すること》
《継続すること》本日は坂本先生に、最終講義をしていただきました。
学生が最後のナレッジファシリテーションを行い、
それを元に、坂本先生に解説をしていただきました。
坂本先生の講義のなかで、自分の残りの人生がどれくらいなのかを、
何年、何ヵ月、何日、何時間、何秒と、細かく換算していくことを行いました。
この瞬間ごとに、残された時間は減っていきます。
漫然と過ごしても、この速さは変わりません。
本日、坂本先生から、継続することの大切さを学びました。
その中で、誰でも1度はできるが、2度目をやるかやらないかで、
差が出るというお言葉がありました。
2度目をやらない人は、継続することもできません。
私自身、継続することは常にできてはいません。
学んだことは、まず1度、そして2度目をやることで、
継続し、本当に身に付けられるようにしていきます。
《相手を磨き、自分を磨く》
ナレッジファシリテーションで作成したナレッジシートは、
作るだけでは意味がなく、自分のために役立てていかなければなりません。
そのために、ナレッジシートの項目ごとに
自分で様々に工夫をしながら達成状況を記録しますが、
本日はそれに加えて、
他の人から達成状況を評価してもらうということも行いました。
他の人から評価をしてもらうことで、
ナレッジシートを活用して自分が身に付けたことを、
実際に発揮できているかが客観的に分かります。
自分では体得したと思っていることが、他の人から見るとまだまだだったり、
逆に意外なことが達成できていた、ということがありました。
お互いに評価をし合うことで、やる気を保ちやすくもなります。
また、この延長として、他の人をこちらから一方的に評価することもできます。
今後は、坂本先生から講義で学んだことを元に、
ナレッジシートを複数作成し、他の人ともやり取りして、
情報を共有しながら活用していきます。
From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生
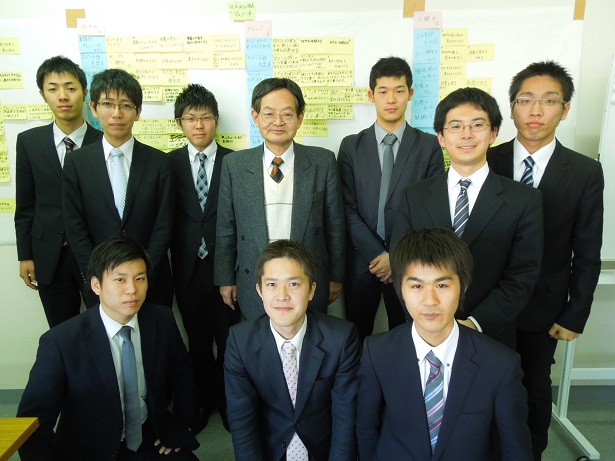 『結局は、自分の為』
『結局は、自分の為』これまで坂本先生から
ナレッジファシリテーションだけではなく、様々なマインドを教えてもらっている。
講義で教えていただいていたのだが、
ナレッジファシリテーションを実行するように指導をするのも、
結局は自分自身のためだと教えていただいた。
実際に言われてからやるのと
私から進んで習慣化するのでは大きく差が開く。
例えば、以前に行った読書ナレッジだが、
私は数日前に自主的にやってみた。
やってみた後の感じが全然違う。
坂本先生からのお褒めの言葉もあったが、それ以上に達成感が大きい。
様々な先生からも何々をやれと指導をいただくこともあるが、
すべては自分の為だということを忘れないようにし、
自己成長につなげていく。
『続ける』
ナレッジシート作成は、1回目は簡単であるが、
2回目、3回目と繰り返すのは難しい。
これを続けられるかどうかで社会に出てからが変わってくる。
実際に社会に出て大きく変われるのは3年目だといわれている。
その中で3年間続けることができれば
このノウハウを知らなかった人に比べて結果に差がついてくる。
坂本先生も誰にも負けないと太鼓判を押していた。
ナレッジファシリテーションで話したことは基本的に社会で活かすことができる。
マメにチェックすることを忘れず、仕事で成果を残せる人になる。
From:安齋義仁(福島県出身、いわき明星大学卒)JVU院生
【平成25年2月12(火)】 『神社プレゼン』
2013/02/12
コメント (0)
★ホームルーム
※日経新聞休刊日
9:00~朝礼、掃除
9:45~1分間スピーチ
ベン大で学んだこと
最近気になるニュース
恋愛について
上記のテーマで一人ずつ1分間スピーチを行う。
学生一人一ポイントと事務局の点数、時間をもとに評価点数を出した。
11:30~昼休憩
12:30~神社プレゼン
地元の神社
都内の神社
上記の神社を12分間でプレゼンを行う。
午前中の1分間スピーチと比べ、時間が余る学生がほとんどであった。
内容が内容なだけに相手に興味を持たせるのが難しい。
いかに相手にいってみたいと思わせるかがポイントである。
15:00~終礼
※日経新聞休刊日
9:00~朝礼、掃除
9:45~1分間スピーチ
ベン大で学んだこと
最近気になるニュース
恋愛について
上記のテーマで一人ずつ1分間スピーチを行う。
学生一人一ポイントと事務局の点数、時間をもとに評価点数を出した。
11:30~昼休憩
12:30~神社プレゼン
地元の神社
都内の神社
上記の神社を12分間でプレゼンを行う。
午前中の1分間スピーチと比べ、時間が余る学生がほとんどであった。
内容が内容なだけに相手に興味を持たせるのが難しい。
いかに相手にいってみたいと思わせるかがポイントである。
15:00~終礼
午前の前半は、「ベンチャー大學で学んだ事」、「最近気になったニュース」、
「最近の恋愛事情」のテーマで1分間のプレゼンを行う。
プレゼンを客観的に見て貰い、私のプレゼンではインパクトが
足りないと指摘を受ける。
間をうまく使ったり、変化をさせる事で相手の受ける印象は
変わるかもしれいないと感じて、今後の私のプレゼンの課題になった。
午後の後半は神社プレゼンとし、12分間の中で年末・週末に行った
神社についてプレゼンを行った。
扱うテーマによってプレゼンの難しさも全然違ってくると感じた。
扱う話題は「歴史や神社」が中心となる。
ベン大生なら少しは興味を持つが、一般人なら
すぐ聞いて飽きるのではないだろうか?ただ神社の歴史を伝えたり、
webだけでの知識を伝えるだけでは聞いている方は飽きてしまう。
自分で現地を歩いた独自の視点を持ったり、
自分の話のペースに持っていく事が大事なプレゼンになる。
物語を伝えたり、今風の噛み砕いた話題にしたり、
時には笑いを持って来たりと、皆さんのプレゼンを見させて頂いて
面白く聞けて工夫したプレゼンを考える上で大変良い勉強となった。
ただ1番大切だと思う事は、真心で話す事。
プレゼンにも奥深さがあると感じた。
人の心を動かすプレゼンは私達がビジネス面で営業職や
経営者になっても、自分の話を有利に進める為に大切だ。
テーマの難しさも頭に入れて行う事も大事だ。
今回それぞれが1分間ないし12分間スピーチで課題を持ち
帰ったので、学生のうちに今の自分に何が足りないか意識
して実践、改善してゆく事が大切だと感じた。
From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生
「最近の恋愛事情」のテーマで1分間のプレゼンを行う。
プレゼンを客観的に見て貰い、私のプレゼンではインパクトが
足りないと指摘を受ける。
間をうまく使ったり、変化をさせる事で相手の受ける印象は
変わるかもしれいないと感じて、今後の私のプレゼンの課題になった。
午後の後半は神社プレゼンとし、12分間の中で年末・週末に行った
神社についてプレゼンを行った。
扱うテーマによってプレゼンの難しさも全然違ってくると感じた。
扱う話題は「歴史や神社」が中心となる。
ベン大生なら少しは興味を持つが、一般人なら
すぐ聞いて飽きるのではないだろうか?ただ神社の歴史を伝えたり、
webだけでの知識を伝えるだけでは聞いている方は飽きてしまう。
自分で現地を歩いた独自の視点を持ったり、
自分の話のペースに持っていく事が大事なプレゼンになる。
物語を伝えたり、今風の噛み砕いた話題にしたり、
時には笑いを持って来たりと、皆さんのプレゼンを見させて頂いて
面白く聞けて工夫したプレゼンを考える上で大変良い勉強となった。
ただ1番大切だと思う事は、真心で話す事。
プレゼンにも奥深さがあると感じた。
人の心を動かすプレゼンは私達がビジネス面で営業職や
経営者になっても、自分の話を有利に進める為に大切だ。
テーマの難しさも頭に入れて行う事も大事だ。
今回それぞれが1分間ないし12分間スピーチで課題を持ち
帰ったので、学生のうちに今の自分に何が足りないか意識
して実践、改善してゆく事が大切だと感じた。
From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生
・1分間スピーチ練習
午前中は1分間スピーチの練習を行った。
普段の朝礼に行う1分間スピーチでは、私は1分をオーバーしてしまうことが多々あった。
なので、本日の練習では、いつもより早く終らせること、
体感で45秒を目安に行った。
すると、3回行ったうち、3回とも約57秒程だった。
体感で1分間がわかっていたわけではないが、
本日の練習で、
1分間の目安がなんとなく掴めた。
この感覚を忘れずに、朝礼での1分間スピーチも、今まで以上に、
気をいれて行っていく。
・神社アウトプット
午後は初詣に参った神社、先週の神社巡りのアウトプットを行った。
このスピーチで苦労したのが、12分間のスピーチという時間の長さだ。
どういう話をしようかということは予め考えていたのだが、
実際に話してみると、だらだらとしたスピーチになってしまった。
1分間という短いスピーチなら、勢いでいけることもあるが、
12分間という長い時間だと、しっかり話の構成を考えていないと、
だらだらとした話になってしまい、聞き手を退屈にさせてしまう。
話をするのが慣れている人はいけるのかもしれないが、
私のような慣れていない人は、しっかりと下準備をしなければならなかった。
From:松田崇義(千葉県出身、慶應義塾大学卒)JVU4期生
午前中は1分間スピーチの練習を行った。
普段の朝礼に行う1分間スピーチでは、私は1分をオーバーしてしまうことが多々あった。
なので、本日の練習では、いつもより早く終らせること、
体感で45秒を目安に行った。
すると、3回行ったうち、3回とも約57秒程だった。
体感で1分間がわかっていたわけではないが、
本日の練習で、
1分間の目安がなんとなく掴めた。
この感覚を忘れずに、朝礼での1分間スピーチも、今まで以上に、
気をいれて行っていく。
・神社アウトプット
午後は初詣に参った神社、先週の神社巡りのアウトプットを行った。
このスピーチで苦労したのが、12分間のスピーチという時間の長さだ。
どういう話をしようかということは予め考えていたのだが、
実際に話してみると、だらだらとしたスピーチになってしまった。
1分間という短いスピーチなら、勢いでいけることもあるが、
12分間という長い時間だと、しっかり話の構成を考えていないと、
だらだらとした話になってしまい、聞き手を退屈にさせてしまう。
話をするのが慣れている人はいけるのかもしれないが、
私のような慣れていない人は、しっかりと下準備をしなければならなかった。
From:松田崇義(千葉県出身、慶應義塾大学卒)JVU4期生

 RSS 2.0
RSS 2.0












