東京校の講義レポート
令和3年(2021)【8月4日(水)】夏の出版編集トレーニング4日目 5期生1組
2021/11/05 21:52:08
コメント (0)
令和3年(2021)【8月5日(木)】
夏の出版編集トレーニング4日目
5期生1組
「最初の一文で引き込め」ESもプレゼンも、最初の一文が大切だと感じました。読みたくなるような引き込み方ができるか、いかにうまくキャッチコピーを考えられるかなど、発想力が試されます。特にESは、今回内容を捻り出すのに必死になりましたが、読む側の視点をもっと意識し、文の組み立てまでしっかり気をまわせるようにする力が必要だとわかりました。
「文を担う責任」
校閲をする人は最初の読者だ、というお話をしていたのをきいて、納得しました。文を生かすか殺すかがかかっていると考えると、地味だけれどとても責任ある大切な仕事だと気が付けました。
「知識量は発想力に直結する」
新聞アウトプットの際、どうしても知識不足を感じます。記事そのものの理解はもちろんのこと、周辺知識、関連づけられそうなものを発想できる力を手に入れるためには、継続したニュースへの意識が必要になると痛感しました。
K.H@専修大学
--------------------------------------------------------
「バックグラウンドを活かしたディスカッション」
今日の新聞アウトプットでは、自分の国籍、家族事情、知識などそれぞれの人のバックグラウンドを活かしたディスカッションができたように感じ、とても充実していました。新聞アウトプット3回目になりますが、回を追うごとに皆さんと成長出来ている実感があります。
「誤字の重大さ、校正校閲の大切さ」
今日は初めて校正校閲を体験しました。「固有名詞の誤字は一番見逃してはいけない」とおっしゃっていたのが印象的でした。私も名前の漢字をよく間違えられ、不快に感じることがあります。固有名詞の間違いはその人、その地名のアイデンティティを傷つけるものであり、一番やってはいけないことだと感じました。
I.C@獨協大学
--------------------------------------------------------
「引き出しとおもちゃ箱」
引き出しを増やすことも大切ですが、興味を持ったものを何でも投げ入れるおもちゃ箱を作ることが、新たな発想を得るきっかけになるのではないかと気が付きました。自分の中の引き出しは整理された記憶と言うイメージがあり、多ければ多いほどネタが増えますが、敢えて何でも投げ入れるおもちゃ箱として自分の中で整理せずにしておくことで組み合わさって新しいものが思いつくと考えました。本日は自分の体験や聞いた話を沢山したので、話しやすかったと感じ、これからも色々なものを取り込めるようにします。
「進んで戻る」
2、3歩進んだ発想で相手を惹きつけ、その後少し戻って今と過去の事から根拠を示す流れは、ESだけでなく、雑誌や書籍の作りでも同じなのだと分かりました。
新聞のアウトプットの際も、その記事が今後どういう流れへ変わるのか推測し、今何ができるのか考えるので、今後のアウトプットでも意識して記事を読みます。
「長時間の1回より短時間の10回」
長い時間かけて一度だけ校正するよりも、短時間で気分転換をしつつ何回も読み直す方が正確に仕上がるのだと気が付きました。集中力や直した情報の正確さが求められるので、一度で全てやろうとすると目が疲れていたり、集中できていない状態で行うことになり、時間をかけることが必ずしもいいことではないと分かりました。
K.C@和洋女子大学
--------------------------------------------------------
「校閲は細かく見過ぎない」
編集の仕事の一つである校閲を本日やりました。少し歴史と関わるところもあるので、細かく見ていきました。話を聞いたところ、校閲は印刷するまで、10回以上もやるので、細かく見すぎると時間をかかりすぎるかもしれないので、一回一回細かく見過ぎないように気づいたところや疑問点などを一旦保留して、校閲を行うようにしていきたいです。
「一歩、二歩先を考える」
ESの課題、今後流行ると思うビジネスコンテンツなどの設問では、まず、既に出ているものは出さずに、それより一歩先、または二歩先のコンテンツを考えて書いた方が、より印象が深く付けられます。
G.K@駒沢大学
--------------------------------------------------------
「視野を広く持て」
編集の作業である校閲を体験させて頂きました。
歴史の偉人のファイルをさせて頂きましたが、どこを修正するかしっかりと文を読んでいた為、すべてのファイルを時間内で見ることが出来ませんでした。一度に細かく見過ぎず、作業を効率化していくことがこの作業で必要だと理解できました。今後もこのような細かく見る作業を行う時、いかに時間を短縮し全体を見ることが出来るかを意識して取り組んでいきたいです。
「先を見据える視点を持て、既存ばかりを求めるな」
ESの3つ目の課題で、今後流行ると思うビジネスコンテンツを考えた際、既に出ているものを取り組んでしまった事が反省点です。この既存のコンテンツをどこまで先を見据えて自身でアイデアを捻れるかが必要な作業だと気づくことが出来ました。
T.K@桃山学院大学
令和3年(2021)【8月4日(水)】夏の出版編集トレーニング3日目 5期生1組
2021/11/05 21:40:53
コメント (0)
令和3年(2021)【8月4日(水)】
夏の出版編集トレーニング3日目
5期生1組
「クリエイティブな人は物知り」今日、新聞アウトプットでは初めてディスカッションを行いました。ただ発表するだけでなく、議論することで記事に対する理解を深めることができました。アイデアマンと言われて、画期的な意見を次々出せる人の多くは、自分でゼロから考えているのではなく、異業種のニュースにも目を向け、いろいろなところにアンテナを張っているからこそだと思います。私も新聞を通してアンテナをどこにでも伸ばせるように訓練します。
「日本市場は1.2億、中国はその10倍」
コンテンツを作るとき、まずは1.2億人の日本人に向けて作りますが、中国は日本の十倍の人口がいると思うと、マーケットの規模が全然違うことを改めて感じました。日本のアーティストだと、YouTubeの再生回数1億回行けばニュースになりますが、海外アーティストだと30,50億回再生をよく見かけるのを思い出しました。
I.C@獨協大学
--------------------------------------------------------
「わかるよりわからない、メリットよりデメリット」
わからないを調べて終わりにせず、他の人と共有する方がよいと気づきました。自分の記憶にも残るし、分からないこと を調べる中で繋がっている分かると思った言葉も実は説明できていないと気付けました。また、自分たちにメリットがある 記事を探すことも大切ですが、デメリットも見つけ、それをどう解決できるか探るのはもっと大切だと分かりました。
「お前のものは俺の物俺の物は俺の物」
意見交換をすることで自分が思いつかないようなアイディアを得られますが、それを自分の物にする気持ちを持って臨む方が話の頭への入り方が違うなと気付きました。サムネイル作成の文庫では、私は物語の舞台が見た目で分かるようにデザインしましたが、内容を予感させるようにデザインしている方もいて、同じ題でも着眼点が違うなと思いました。これからは、お前の物は俺の物俺の物は俺の物というジャイアンマインドを持ちます。
K.C@和洋女子大学
--------------------------------------------------------
「貪欲に知識を求めよ」
今回の新聞アウトプットで、あまり触れてこなかった分野に挑戦しましたが、理解するのも難しかったです。知らない単語は調べる、疑問な文を見逃さず向き合って考えてみることを、少しずつ積み重ねて自分の知識の引き出しを増やしていきます。
「前提を疑え」
日本とアメリカの水深の差、日本とアメリカの人口の差など、同じ事業を進めようと思っても、そもそも前提条件が違うことによる問題や壁がたくさんあると気づかされました。
国、地域、個人の差など、常に比較の意識を持って得た知識を応用したいと感じました。
K.H@専修大学
--------------------------------------------------------
「週半ばは経済が動く」
新聞の記事は基本前日のできことです。月曜の記事はだいたい日曜日のできことですので、経済活動はあまりしていないことです。週の半ば(水・木・金)では経済活動が動いていることで、その分の内容も充実してきます。今日でも、オリンピックより、円高を重視していることが見えます。
「スマートフォンの普及」
中国のゲームやアップリなどは日本風なイラストで、日本に人気あったことが本日の記事にありました。そもそも、中国では人口が多いことで、ゲームやアプリのサービス範囲も広いです。ついでにという感じで、日本や韓国などにもサービス対象として出していることになっています。中国もスマートフォンの普及率が高いです。本日の記事のもあったTikTokも中国のアップリです。よく田舎を背景として、動画をしてきた人もいます。中国のTikTokにはよく見れる何百万人、何千万人のフォロワーが見えることで、ユーザー数もそれ以上にあります。また、田舎などでは、パソコンより、スマートフォンの方が使うことが多いと感じています。
G.K@駒沢大学
令和3年(2021)【8月3日(火)】 夏の出版編集トレーニング2日目 5期生1組
2021/11/05 21:34:03
コメント (0)
令和3年(2021)【8月3日(火)】
夏の出版編集トレーニング2日目
5期生1組
「アウトプットは恐ろしく難しい」今日は初めて、新聞アウトプットを行いました。私は、普段暇なときに日経新聞を読むことはありましたが、それを自分に落とし込んで考え、発表するという経験は初めてでした。やってみると何度も言葉に詰まり、言いたい概念が説明できず、正直ボロクソな発表になってしまいました。この原因はやはり、新聞をただ読んでいるだけでは、インプットしかできず、アウトプットをする場がないからだと思います。しかし、他人の脳みそは観察できないので、その人が幅広い知識を持っているかどうかは、アウトプットによってしか分かりえません。アウトプットの重要性と難しさと痛感させられました。
「6人の評価を聞けば、収穫も6倍」
自分のES の回答の評価を頂いただけでなく、他5人のESについても評価を聞くことができました。まず、内容が6人6色だったので、「こんな切り口もあったか」と、参考になる部分が多くありました。また、他5人のESと、その評価を自分が頂いた評価のように考えられたので、学びが6倍になりました。「人のふり見て我が身直せ」という言葉があるように、今後のESではほかの方が指摘されたポイントも意識して、自分のESをさらにブラッシュアップさせたいです。
I.C@獨協大学
--------------------------------------------------------
「日経新聞はストーリー仕立て」
経済は、経世済民と言う言葉の略で、世の中を良くして民を豊かにするという意味だと初めて知りました。そして、そのためにはまずルールである法律を作る事が必要だから、政治が必要と言った風にジャンルの流れストーリーのようになっていると気が付きました。また、新聞は各新聞社によって書き方が違うので、1紙ばかり読まずバランスよく知識を得ることが大切だと思いました。
「センスは量」
エントリーシートは企業が知らないようなことを書くのが大切だと気付きました。競争率の激しい中で一番になるより、オンリーワンになれるように、情報量を増やすことを意識したいです。そして、センスは量であるというのに驚きました。どれだけ量をこなしたかによってセンスが身に付いていくと知り、就活のためでなくとも活用したいと思います。
K.C@和洋女子大学
--------------------------------------------------------
「ネガティブこそビジネスチャンス」
新聞アウトプットについての講義で印象に残りました。
意見を考える上では、どうしてもメリットを探してポジティブに繋げるように考えてしまいがちです。
しかし、そこをあえてデメリットというネガティブな部分に目を向け、いかにポジティブにビジネスへ繋げていくかが重要だと理解しました。
「自分の土俵へ相手を連れ出せ」
相手の興味を惹き、なおかつ相手のペースに持ち込まれないためには、自分の土俵で戦う工夫をする事が必要と知りました。
枠にとらわれず、自分がいきいきと語れる自由な発想が求められるのだと気がつきました。
K.H@専修大学
--------------------------------------------------------
「質より量」
エントリーシートを書くとき、出てくる設問は全て、自己アピール箇所です。単なる質のアピールより、具体的な量(数字)を入れて入れて、質をアピールことが大事です。エントリーシートを見る側では、真っ先に目に映る文章の中のワードは数字ですので、数字をうまく使うとアピール効果も増します。
「経済は世を知る、民をよくすること」
経済曰く「世ヲ経メ、民ヲ済フ」とのことです。経済というワードの意味をここまで、細かく考えたことがありませんでした。授業では、経済活動の解釈は、よりシンプルでした。お金のやり取りというのは一番シンプルで、一番よくある経済活動です。簡単というと、経済は企業のイメージが強くなっていますが、実際のところ、普通な家計でも経済活動と言えます。今後は政治・金融・国際などのことをよく新聞から確認してから経済を理解していきたいです。
G.K@駒沢大学
--------------------------------------------------------
「甘く見るなアウトプット」
このキャッチコピーが思い起こすほど、アウトプットを甘く見ていたことが今回の実習で分かりました。興味があるトピックだったので、言いたい疑問などは浮かぶだろうと考えていましたが、いざ自分の番に発表となると言いたいことが纏まらず、疑問点を説明できたかが曖昧でした。ひとつだけではなく、多く視野を持ち、書籍や新聞を読むことが重要だと再確認出来ました。
「質ではない量だ」、「土俵を超えてからが勝負」
自己アピールは企業側の土俵ではなく、自分自身に置き換えるかが重要です。在り来りで、予想しやすいことばかりを書けば企業に読まれる間もなく飽きられてしまう。企業に読んでもらうためにどのように文章を書くか、発想力が求められる事を教わりました。
T.K@桃山学院大学
--------------------------------------------------------
「経済とは経世済民のこと」
人にものを伝えるには、その言葉の意味をわかりやすく伝える必要があり、そのためにはその語源、本質をつかみなさいという趣旨のお話でした。そのことが経世済民の意味と合わせて理解できました。
「相手の土俵で戦うな」
たしかに、既に行っている事業の知識では就活生は企業の方に太刀打ちできないので、その企業の知らないネタ、もしくは一見畑違いのネタで勝負するということは理にかなっていると感じました。またその勝負の土台に立つためにも、周りの就活生よりも情報感度を高める必要性を感じました。
T.K@広島大学
令和3年(2021)【8月2日(月)】夏の出版編集トレーニング1日目 5期生1組
2021/08/02
コメント (0)
令和3年(2021)【8月2日(月)】
夏の出版編集トレーニング1日目
5期生1組
「本は幕の内弁当」今回の書籍紹介で、もしこれが特定の層に勧めるという課題であった場合、対象者によって、推すポイントを変える必要があると気が付きました。
今回は自分の好きな本を紹介するという事で、自分の興味に絡めたり、本の内容メインで話したりと人それぞれの紹介の仕方でした。しかし、もし人に勧めるということであれば、その人が食いつきそうな部分を探し、そこをメインとして話を作ると思います。色々なことが書いてある中で、その人が興味のあるポイント、幕の内弁当で言えばその人の好きな具材をインパクト・コンパクト・コンセプトを意識してプレゼンすることが大切だなと考えました。誰に向けているのかを意識したいです。
「鰹節は削ったところを使う、文章は残ったところを使う」
文章は、先にアイディアをたくさん出して、そこから削っていった方がよいということに気が付きました。私は文章を書くときに、書きたいことを出したら、そこから膨らませて、増やして文章を書いていました。しかし、そのやり方では書くことが思いつかなくなった時に、行き詰ってしまうことも多くありました。削る方式で書くことにより、書きやすく、よりわかりやすい文章が書けるのではないのかなと思いました。
「新聞を読んで時流を読む」
新聞を読むことで、今社会で何が起こっているか知るだけでなく、そこから考えを広げることが大切だと気づきました。これから新聞を読むときはただ活字を追うだけでなく、どういうメリット・デメリットがあるのか、今後どういう流れになるのか、自分はこうなった良いと思うなど、考えるようにします。記憶にも残るし、世の中の流れも知ることができるし、思考力を養うこともできて、一石何鳥にもなるのだなと思いました。また、社会の出来事を何も知らなくても生きてはいけますが、社会の一員として、社会について知ることはある種義務ではないのかなと考えました。
「隙にはぬか漬けの野菜より漬け込め」
遠慮をせずにもっと積極的に挙手をした方が良いと気づきました。これまでは、他の人が挙げそうな雰囲気の時には上げないようにしたり、ようやく挙げられたと思ったら他の人と被ってしまったりすることが多くありました。しかし、今回のオリエンテーションでお話を聞いて、他の人が戸惑っている隙に迷わず手を挙げてしまうことも大切なスキルなのではないかと考えました。選ばれなくても、印象に残してもらえるのではないかなと思っています。また、自分が積極的に参加することで、他の人が発言しやすい雰囲気を作れたらなと思います。
K.C@和洋女子大学
--------------------------------------------------------
「キャッチ×コンパクト」
どのトピックでも、コンパクトを意識しなければならないことを学べました。プレゼンをする際にはどれだけ伝えたいことを凝縮し、人を惹きつけられるキャッチコピーを考えるられるのかが重要だと理解しました。
特に、初めに印象的な言葉を示したり、筋道をはっきりさせてプレゼンしていた人ほど記憶に残ったので、今後自分のプレゼンでも意識していきます。
「好奇心を最大の武器へ」
新聞アウトプットの解説を聞く中で、自分の知らない事実や言葉に多く触れることは、今後自分の武器になることが分かりました。その武器を増やすための第一歩が好奇心なのだと感じました。
K.H@専修大学
--------------------------------------------------------
「日経は内容勝負、日経以外は見出し勝負」
講義の中で、日本経済新聞の一面の見出しを見て、「よし!定期購読しよう!」と思う人はほとんどいない、というお話がありました。日本経済新聞は、人を惹きつける見出しで勝負するのではなく、情報の質で勝負しているのだと思います。そういった点で、他の出版物と一線を画していることに気づきました。
「ESは問題文の精読から」
K社のESに、「こだわり」と言う言葉が何を指すのかを考えた時、自分の中で「エンタメって何だろう」「洞察力って何だろう」とさまざまな疑問が湧きました。ESを書く際には、当たり前に知っている言葉も一度辞書で確認し、認識のずれがないようにします。
I.C@獨協大学
--------------------------------------------------------
「物事の紹介は短く」
本の紹介も自己紹介もそうであり、短い文章で伝えたい内容を伝える力をつけることを学びました。大学のレポートや論文とは違い、いらない言葉を加えずに、文章をいかに短くするかを考えることが今後の課題です。
「歴史の考え方で新聞を読む」
私の歴史への考え方は「比較」です。学者のその時代の考えを比べながら考えることです。個人の意見はとある方向に偏ることになりますので、私が気づいていない点も必ずあります。他の方の意見も聞き、視野を広げることがこの一週間でやることです。
G.K@駒沢大学
--------------------------------------------------------
「考えるだけじゃなく、行動に」
新聞は家でとっているものを簡単な所しか読んでいなかったので、日経新聞のように活字だらけの新聞はあまり読んで来なかったと今回明確に知る事が出来ました。
今回日経新聞やほか参加者の書籍発表を聞いて考えついたキャッチコピーは「人間は本を読まないと猿だ」というものです。
文字の価値は人の知力を身に着けるうえで重要となってくるものなので、この1週間を濃厚にするために視野を広げていきたいです。
T.K@桃山学院大学
新刊「原点回帰の経営」校了!!
2021/01/21 17:23:09
コメント (0)

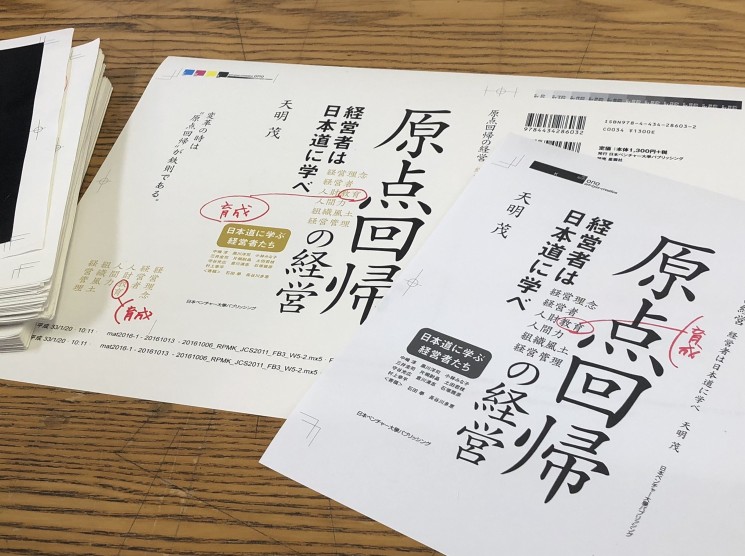
 RSS 2.0
RSS 2.0












