東京校の講義レポート
【平成25年1月8日(火)】 『松下村塾合宿2日目』
2013/01/08
コメント (0)
 《吉田松陰先生》
《吉田松陰先生》合宿では、今も松下村塾の建物が残されている松陰神社を中心に、
吉田松陰先生と松下村塾について学びました。
実際に現地で学び、梅地和幸さんや松蔭神社の宮司さんから、
お話をしていただきました。
松陰先生については、これまで本などで学び、どのような方だったのか
ある程度はイメージができているつもりでしたが、
今回の合宿で自分の体験としての学びを得て、
それがより新しく、明確になりました。
私が松陰先生について学んで最も強く感じているることは、
松陰先生が本当に純粋な人だったということです。
先生は、親族や塾生といった自らに近い人々から、
藩や日本という大きなことまで、強い関心を持っておられました。
そして、それらをより良くするために何が必要なのかを考え、
相手が人であれば対等な目線から語り合い、
社会の仕組みであれば自らが行動されました。
また、おかしいと思ったことに対しては意義を唱え、
しなければならないと感じたことについては確実に行動に移す。
社会的な地位や名誉にはこだわらず、物事の道理を重視されました。
本当の優しさと、意志の強さを持ち、
しかも自分の利得を考えず、筋の通ったことを実行できる。
松陰先生のような人には、なろうと思ってなれるものではありませんが、
世の中が変わっていく源流となる人とはどのような人なのか、
松陰先生の事を学び、知ることができました。
今後も、松陰先生・松下村塾とその時代について学び続け、
社会の中で自分が何を成し遂げることができるのか、
そのような人になるために何を体得するべきか、考え続けていきます。
《松下村塾の塾生》
今回の合宿では、松下村塾の塾生たちの家やその跡地をまわり、
彼らについても学び、考えました。
塾生の中には、親の反対を受けても通い続けた人や、
吉田松陰先生に数日接しただけで入塾した人もいます。
後世に生きる私は、松陰先生や松下村塾に集まった塾生がどのような人々で、
何を成し遂げたのかを知っています。
後世の視点から考えると、松下村塾に出会った人々が松下村塾で学ぶことは、
その人々のためにも当然の選択だと思えます。
しかし、松下村塾を開いていた当時の吉田松陰先生は、
公的には藩の罪人という立場でした。
それでも、塾生は松陰先生の元で学びました。
松陰先生の人柄や塾の方針に惚れ込んだことが
塾生にとっての最大の理由だと思いますが、
社会的な地位にこだわらずに
自分が良いと感じた人や事を受け入れることは、簡単なことではありません。
学び、自分のするべきことを見つけ、それを実現したい。
そのためであれば、偏見を取り払うことができる。
そのような意欲のある塾生が集まったことも、
松下村塾が明治維新の源流となった理由の1つだったのではないかと感じました。
社会的な地位や権威、世の中の常識とされることにとらわれずに、
本当に自分にとって価値のあるものを求める姿勢が、
時代の転換期きは求められていることを学びました。
常に求め、そこからの出会いを大切にし、
自分の信念に基いて自分のものとしていきます。
《松下村塾の方針》
吉田松陰先生の松下村塾で、塾生たちがどのように学んでいたのか、
今回の合宿で学びました。
松陰先生は、自分が塾生たちに指導をするという立場に立たず、
塾生が学びたいこと、やりたいことを中心として、
自らも塾生たちと共に学んでいくという方針をとられていました。
この方針は、松陰先生が藩の牢獄に入れられていた時に、
希望のない囚人たちを元気づけるために、
囚人が得意とするものを他の囚人に教え合うようにした
ということがルーツになっています。
自分の得意な分野を人に教えることで、自分自身の存在価値を感じることができ、
それぞれの長所を活かすことで、
学ぶ人が、自分のするべきことを見つけられるようになります。
松陰先生も、最初から決まった方針を持っていたわけではなく、
ご自身の実体験から学び、試行錯誤の中で方針を考えられたために、
その結果として松下村塾が大きな意義のある場所になったことが分かりました。
他の人に何かを教えたり、学ぶということは今後も多くありますが、
松陰先生が松下村塾で実践されたことを手本とし、
自分で目標を定めて学び続け実行してみること、
一方通行ではなく共に学ぶという姿勢を大切にし、
自分で自分の道を見つけられるようにしていきます。
《歴史の行間を感じる》
今回の合宿では梅地和幸さんに、
吉田松陰先生と松下村塾について、詳しく解説をしていただきました。
梅地さんが仰ったことに、
「短い期間に開かれていたに過ぎない松下村塾で学んだ人々が、
なぜ維新という大きな歴史の流れの中で活躍することができたのか」
というものがあり、印象的でした。
その理由は、単に歴史上の事実を調べただけでは分かりません。
私は、今回の合宿を通して、
松陰先生の人柄と、教育についての方針を学びました。
松陰先生は本当に純粋な人であり、それが塾生にも伝わったであろうということ、
塾生が先生に頼り切りにならず自分で学び、
互いに高めあうことができる松下村塾の方針、
肩書きや立場にとらわれず、本当に価値のあるものを求めた塾生の意志。
これらが組み合わされたために、激動の時代の中で、
松陰先生の遺志を継いで世の中を変えたいと決意し、
そのために何をなすべきかを求め続け、行動していった人々が輩出されました。
私はこのことが、松下村塾が世の中を大転換する源流になった理由だと感じます。
推測ではありますが、現地に行き、実体験をすることで、この結論に至りました。
これは私が思ったことに過ぎず、歴史を学んだ一人ひとりが、それぞれ異なった体験をし、
異なった思いを持ち、異なった結論に達することが当然だと思います。
それでも、歴史的な事実を元に、自分の体験や思いを加えて、歴史の流れを想像し、
人一人ひとりが、自分なりの結論を出すことができるという
歴史を学ぶ新たな面白さを、今回の合宿で学ばせていただきました。
またこれは、歴史に限ったことではないと感じます。
物事の事実関係を正確に把握することは大切ですが、それだけではなく、
事実と事実の間にどのような作用が生じたのか、
体験し、当事者のことを思い、自分なりの結論を出すことが、
物事をほんとうに理解するために必要だということを意識し、今後学んでいきます。
From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

梅地さんと今元さんによる塾生の生家めぐりや野山獄の案内と、
松陰神社の宮司さんによる松下村塾内での講義により、今回はより先生の人物像に迫る濃い合宿となった。
梅地さんは、『そもそもこの萩の小さな小屋である松下村塾で
なぜあれほど多くの逸材を輩出出来たのか?』を常に考えていると言う。
この小さな萩は特殊な地である。徳川家によって京都からも
江戸からも遠い地という理由で毛利慶親が萩に封じ込められたと
いう歴史があり、その幕府に対する恨みや不満が民衆や志士にも
積もりに積もった結果だとも梅地さんは言われている。
しかし1番の逸材を生んだ要因は、若者に今の身分制度や幕府に疑問を持たせ
問題提起をし、とにかく知行合一が大事だと行動を奮起させた松陰先生に功績がある事は間違いない。
松陰先生の人物像や松下村塾の姿を学ばせて頂いた。逸材を育てた環境要因で、
1つは
・先生自身の人間的魅力(平等に接する、誰からも学ぶ)
2つ目は
・成長のための人を育てる仕組み(個人尊重、教え合い、自分達で結論を出す)
3つ目は
・どんな環境に置かれても行動する姿を見せる事
と感じた。
松陰先生の人間的魅力の1つは、誰に対してでも平等な事だと梅地さんは言われる。
例として、先生が外国船に乗り込むとき重之輔から弟子にして下さいと頼まれたが
「自分はその様な身分ではない。一緒に学ぼう」と言われている。
また松下村塾の学習スタイルは、先生が塾生に一方的に教えるのではなく、
お互いの知っている事や良い能力を教え合う事である。
実際先生が松下村塾で座って教えていた位置も、教壇からもっと端側にある。
松陰先生の功績は、松下村塾を作って身分制度を壊した事だという話も松陰神社の案内人から聞いた。
実際、萩城寄りは上級武士の生家が固まっており、そこに明倫館などの藩塾も多数ある。
しかし奇兵隊を作った高杉晋作も明倫館では本当の教育を受けれず困っていたとき、
歩いて40分程もかかる松下村塾を見付け夜こっそりと通っている。
生まれも育ちも関係なく、下級武士も魚屋の子供も、
上級武士も集まれる塾は松下村塾ただ一つだった。
そこで塾生は好きな時間に行き、夜な夜な日本の将来について議論したという。
人を身分や立場で決して差別せず、自分は偉いと思わず、塾生と一緒に学んでいく
という先生の姿勢が、自然と若者を集めたのではないだろうか。
年下だからとか立場の違いで人を判断せず、どんな方も先生となって貰い自分の糧
にする事を私も意識したい。
2つ目の成長のための人を育てる仕組みが整ってた事も大きな要因だ。
私は長州藩士が、自分達が世の中の役割を見つけ実行する事が出来て、その為の
教育が松下村塾で出来ていたと思った。
松下村塾で先生は"個人尊重し、一人一人の個性を伸ばす教育"を重んじられていた。
塾では会読や対独が中心で、各人に対し言葉や書簡・名字説を与える事で、自覚を
高めている。
"学ぶ事は自分で見つける"という教育も先生はやられている。
松陰先生は塾生にこれをやれと言わない。
塾生が「何を学んだらいいですか?」と聞いたら、先生は「君は何を学びたいのですか」と言った。
そこで聞いたらそれについて書かれた本を教えてくれた。という話も聞く。
"教え合い、自分達で結論を出す"やり方も尊重する。松下村塾では教師と塾生という立場はない。
各々塾生が得意な所があり、教え合って足りない所を補い合っている。
今の教育では親や教師は、子が世の中の役割を見つけさけようとしていない気がする。
学校では学生達に何を学ぶか選択させず、1人1人は世の中で新しい事をしようと情熱を持って通えない。
そして親は自分の子を褒めない。個性を見付け、それを伸ばしてあげない。
子供の自信を失わせてはしないか。
今は周囲の大人が子の長所をしっかり気付いてあげ、子に自信を持たせ自身の役割を
世の中で見付けられる支援が必要だ。同時に議論させ答えを自分で考えさせる事が必要と感じる。
3つ目は、先生が自分の成したい事はどんな環境に置かれても行動する姿を見せた事だ。
渡米に失敗し野山獄跡に収監されてからも、牢に入る囚人にすら先生は教育をし、
世の中に向け行動を起こしている。 そのどんな状況に置かれても情熱を持って行動する
姿に、塾生は突き動かされただろう。
何処ででもどの身分でも、世の中に対し行動は起こせると自信を持たせてくれる。
今後も萩での2日間で学んだ事を、ベンチャー大學の中で自分に掲げて行動に起こしてゆく。
From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生

松下村塾では、決まった教科書というのはなかった。
塾生が自分は何を学びたいのかということを考え、それを松下村塾で学んだ。
なので、吉田松陰先生も、必ずしも生徒が学びたいと思っていることに
精通しているわけではない。
松陰先生も生徒と一緒に学んでいくというスタンスであった。
松陰先生は、生徒にとって師であって、師でない。
共に学んでいく仲間という感覚が近かったのではないのだろうか。
そんな松陰先生の心構えや、スタンスを生徒は尊敬し、
松陰「先生」と呼んでいたのではなかろうか。
・高杉晋作が歩いた道程
高杉晋作が住んでいた城下町から、松下村塾までの道を実際に歩いた。
思っていたよりも遠く、これを継続的に晋作は歩いていたのかという気持ちになった。
その後の梅地さんのお話が印象的だった。
「あの道は、遠い道のりでも、晋作にとっては近い道だった」
どういうことかというと、晋作にとって、松下村塾に行くのは、
ものすごい楽しみであり、50分の道程なんかあっというまだったということである。
行く途中では、松陰先生にこういうことを聞いてみよう。自分の意見はこうだ。
ということを考え、帰りには、松下村塾で学んだことを今一度考えてみる。
そんなことを考えていたら、あれぐらいの距離は短いものである。
晋作にとっての、松下村塾の大切さを感じ取れた。
・松陰先生の人柄
郊外にある、あの小さな松下村塾に、2年間という短い期間で、
なぜ92名ものの塾生が集まったのか。
家族から見放され、野山獄に何年間も入れられていた囚人を
解放してあげることができたのか。
松陰先生は、人によって態度を変えるとかいうことをせず、平等に接し、
物事のありのままを受け入れ、自分が興味を持ったことに対しては、
とことん突き進む、といった人間だった。
そんな松陰先生と接した人々は、松陰先生に感化され、自分の道を見つけ、
変わっていった。
松陰先生にはそんな魅力があったのではないかと感じた。
ここで、先日松下政経塾に伺って、松下幸之助が大事にしていた、
「素直」というキーワードが、まさしく、松陰先生にあてはまるのではないかと思った。
素直に人々と接し、素直にまわりの現象をとらえ、素直に自分の気持ちに沿って
行動をする。
松陰先生は「素直」を実際に実践していた人であったのではないか。
私自身も、「素直」を磨いていく。
From:松田崇義(千葉県出身、慶應義塾大学卒)JVU4期生

山近社長、梅地様、上田宮司、日本ベンチャー大學事務局の方々、
日本ベンチャー大學生、女将さん他多数。
一人では感じることが出来ない体験を、皆様のお陰ですることが出来ました。
今、胸が熱くなっています。
とても素敵な方々と研修を受けることができ、幸せです。
今思います。本当に出会いによって人生は確実に変わる!!
一生のお付き合いをさせて頂きたいと思う方々ばかりです。
●吉田松陰先生の一番の魅力とは。
今回の研修で、梅地様が僕達に何度も投げ掛けられた質問があります。それは、
どうして松下村塾からは、約2年という短期間で、多くの偉人が輩出されたのか。
その答えを、是非見つけて帰ってほしいという事でした。
自分の答えとしては、松陰先生の塾生への強烈な愛故だと思いました。
松陰先生は、塾生の人物表を残しておられたそうで、今回の研修では、伊藤博文への人物表を上田宮司から紹介頂きました。
内容は、
『才能もないし、学もない。性格は素直でよろしいが、華がない。
僕、すこぶるこれを愛す。』
僕、すこぶるこれを愛す。
松陰先生は、全ての塾生を愛しておられました。
愛することで、相手のいい部分は自ずと見えてきます。
また、教育的観点から見れば、愛を受け取っている塾生は、松陰先生のどんな言葉も前向きに解釈します。
これがどれほど重要か。どれだけ成長が早いか。
松陰先生の教育のベースにある愛が、松下村塾を偉大なものにしたのではないかと思います。
●大切な事は、どう生きるべきか、を問い続けること。
松陰先生は、『学問は、人間とは何かを学ぶこと』とされています。
なので、講義の中心は、日本人としてどう生きるべきか、人としてどう生きるべきか、であったそうです。
この問いに向かい合い続けることこそが、『読み、書き、算盤、兵術』、を最大限活かすことに繋がると強く感じます。
士規七則という名の文書があります。これは、松陰先生が野山獄において執筆したものを、
叔父の玉木文之進の添削を経て成ったものです。
士規七則は、野山獄の中で、松陰先生が、武士の武士たる者の生き方について思索を深められ、
その過程で発想されました。士規七則には、次のような記述があります。
士道を確立するために心がけるべきは、死ぬまで努力を惜しまない事。
死してようやく終わる。言葉は簡潔であるが、意味は広く深い。
意思固く我慢強く、決断力があり思いきりよく行動する事、これ以外には何もない。
どう生きるべきかのヒントが溢れている文書だと感じます。
2日間の松下村塾研修で、志が新たになりました。
公に生きる。
目指すべきもの、大切にすべきものを体に染み込ませる事が出来ました。
ありがとうございました。
From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生
 『高杉晋作の辿った道』
『高杉晋作の辿った道』今年の研修では
高杉晋作が松下村塾に行くときに
親の目を盗んで辿ったとされる道を歩いたが、
去年にはないプログラムだったので、新たな発見となるものだと感じた。
それも、私語は一切禁止で、さらに、1メートルぐらい間隔をあけて
当時を感じながら辿るものにもなった。
歩きながらだと、どんな気持ちで通っていたのか当然ながら考えることができた。
高杉晋作は元々通っていた藩校から松下村塾に変えてでも行くということは
通常の武士では、まずありえないことだ。
それほどの志が大きかったことに今の私たちには改めてすごい存在であると考えた。
ちなみに、私もかつては親に黙ってベン大に通っていた。
だが、それとはあくまでまったくの別物だ。
私が歩いた40分の間に日本のことを相当考えられたかを思うととてもかなわない。
ここで歩いた時間を絶対に忘れず、無駄にせず、社会でも活かしていく。
『松下村塾』
松下村塾というところは、
様々なすごい人が一大決心をしたということでも有名な場所である。
今の方たちの闘志が火をつけられたのは、
松陰先生の教育があったからということには違いない。
教えていたことは、主に学び方だったので、
学んだことを、どう実践していくのかは自分次第だと教え、
塾生全員のやる気にも火がついていたことが分かる。
また、松陰先生の考え方にも時代を変えたヒントを感じた。
当時は学ぶ人の身分が問われた時代の中で、
教えていた松陰先生は藩士だけど、塾生を全く差別することがなかった。
牢獄に投獄されていたときに、人には必ず何かしらの才能があることを学び、
それを伸ばせば国を変える力にもできるという発想の転換にもなったのだ。
国を守るのは武士しかいないのは、思い上がりだという
映画での松陰先生の台詞を思い出した。
今後出てくる人というのは、今までの固定概念にとらわれず、
その時代におかしいと思われることでも
まずやってみることを意識し、行動していく。
『JVU全国会議』
東京校、完全に負けている。この一言でしか現状を書けない。
特に、積極性の点で分校よりも劣っていると感じた。
質問時やスピーチ希望時の手を挙げる早さ、
分校生のレベルが格段に上がっていることを痛感した。
それと同時に、分校との差が相当広がってきたなと
このままではいけないと危機感を感じた
また全国会議内で、藤本社長からの言葉にも考えさせられた。
私の中で「院生」というキーワードが、大きな課題だと確信した。
これに関しては、私がその立場である。
本来、ベン大は1年で卒業しないといけないのに、
2年目に突入させてもらっているのが現状だ。
みんなより1年長く在籍しているが、
偉いのではないことを誰よりも自覚しなければならない。
院生になったことで、周りの方からの視線が変わったことも自覚している。
分校生との差にしても、院生にしても、
今の自分に何ができるかを必死に考えないといけない。
全校生と一緒に学べるチャンスは知覧しかない。
その時までに遅れを死に物狂いで取り戻し、最高の状態で知覧入りをしたい。
また、日本遊学の旅ではリーダーになっているので、
絶対に後悔しないような行動をし、
ただのごろつきから、本当のリーダーになり、
最後の締めくくりをよいものにする。
From:安齋義仁(福島県出身、いわき明星大学卒)JVU院生
【平成25年1月7日(月)】 『松下村塾合宿1日目』
2013/01/07
コメント (0)
 『松下村塾合宿』
『松下村塾合宿』1月7・8日に行われた松下村塾合宿ですが、様々なことを感じさせていただきました。
書物などであらかじめ事前知識はあったのですが、
やはり実際に現場に行って感じることが多くありました。
●松陰先生のすごさ
萩の城下町のさらにはずれにある松下村塾から日本を動かす人物が
次々と現れたのはやはり吉田松陰先生の素晴らしい教育が
あったからだなと改めて感じました。
まず塾に来た塾生に君は何がしたいのか、
と尋ねその返答によって教科書を決めるというお話には驚きました。
その背景にすごい数の読書量があるのだなと感じました。
また身分関係なくその人個人の長所を見抜きそこを伸ばすと言われ、
人を見る確かな目も持っているのだなと感じました。
そしてなんといっても公のために尽くす精神はすごいなと感じました。
常に他の人のため、国のためをよく考えれるなと思います。
野山獄での食事の際に、おかずをお金に変え、お供の金子重輔の家族に
渡していたお話は感動し、自分がつらい時でも他人を思いやることができる人は本物だと感じました。
●高杉晋作の想い
今回の合宿で初の試みとして高杉晋作の旧宅から松下村塾まで
歩いてみるということを体験させていただきました。
私語も禁止で黙々とあるいたときに、様々なことを考えました。
初めはくだらないことを考えていたのですが、
日本の現状や未来についてなども考えたりもしました。
この自分が思ったことを誰かに聞いてもらいたいなとも感じました。
高杉晋作ももしかしたらこの40分もかかる長い距離の中で将来の日本のことなどを
考えそれを松陰先生や久坂などに話しては意見をもらえると、
わくわくしながら歩いていたのではないかと感じました。
うらやましいと感じた反面、自分の今の環境を考えたときに共通点が多いなと気付きました。
40分かかる通学や、意見を来てもらえる先生や仲間がいると感じそれを活かせていないと思いました。
今後活かせるよう行動します。
●とにかく「行動」
とにかく「行動」、やることの大切さを改めて再認識することができました。
やってみなければ失敗かどうかもわからない、
ついつい自分は頭で考えてやめてしまうことが多いのでこのことは響きました。
命をかけるという言葉の重さも松陰先生の行動を知ると軽々しく使ってはいけないなと感じました。
一回一回の行動がすべて全力でそのたびに命はなくなると考えており、
助かった時には本当にありがたいという気持ちになっていたのだと思います。
一回一回の行動が全力だからこそ人も信用しついて来てくれるのではないかとも感じました。
とにかくやること、自分の持てる力で全力でやることが大切なのだと
今回の松下村塾合宿を通じて学ぶことができました。
From:渡辺寛高(広島県出身、尾道大学卒)JVU4期生

私は、松下村塾は昨年に引き続き、二回目の参加。
『知識は行動の本(もと)である。正しい行動は深い知識や理解によって、実現するものである。』
という松陰先生の言葉。
前回の参加の際は、松下村塾、そして松陰先生についてほとんど知らなかった。
しかし、今回はこの1年でしっかりと学んだということもあり、
前回以上の学びを得ることができた。
まず行動することももちろん大切であるが、自分の中にいかに正しい知識を入れ、
それをモトに行動する大切さというものも松陰先生に教わった。
★松陰先生の謎
何故これほど狭い範囲の中から、日本を動かす多くの志士たちを輩出できたのか。
4日から、長くても1年通うだけでそれだけの人物を育て上げたことが不思議でたまらない。
明治時代以来だれもが考えてきたこの謎。
梅地さんは松蔭先生の人間的魅力が理由とおっしゃっていたが、私はそれでも納得できなかった。
もちろん松陰先生の言葉では表せない人間的魅力もあっただろう。
しかし、私が今回の研修で最もしっくりきたのは、強みを伸ばすというものである。
松陰先生は人一倍、人を見る目があり、その人の得意分野を見つけ出すのが非常に優れていたと考える。
本人でさえなかなか見つけ出せない強みを見つけ出し、その分野に集中させて学ばせる。
この教育方法が大きかったのではないだろうか。
★門下生の学びに対する姿勢
一般的に子供は塾(勉強)と聞くと、それだけで嫌な気持ちになるのがほとんどである。
それを誰に強要されることなく、自らの意思で通っていた松下村塾の門下生たちは、
学びに対する意識が非常に高かったことが伺える。
今回、高杉晋作が親の目を盗んで松下村塾に通っていた40分ほどのルートを歩いた。
親には遊びにいくと伝えて、じつは松下村塾に通っていた。
何がそうさせるのか。
松陰先生が好きで会いにいくのもあったのだろうが、学ぶことが楽しくて仕方なかったのではないか。
そんな環境が松下村塾にはあったのだろう。
嫌々学ぶのと楽しみながら学ぶのとでは、その伸びは全く異なる。
教育にはこの自分が楽しいと思える、好きなことのみを学ぶというのが非常に重要であると感じた。
★側隠の情
今回も松下村塾に入室させていただき、上田宮司に講義していただいた。
武士道で大事にされたこの側隠の情が今忘れられているというお話をしていただいた。
武士というのは農工商の上に立つ人たちであり、農工商の鏡でなければならない。
側隠の情とは、人の不幸を哀れみ深く自分の痛みとして想い、行動する。
如何に相手の事を想うか。ただ刀で人を殺すのが武士ではない。
この武士道の考え方は心に留めておく。
★留魂録の第8章
上田宮司は日本史上の思想家が書いた文章でもっとも優れたものとおっしゃっていた。
死を直前にした者の文章とは思えないほど澄み切っていると。
「十歳にして死する者は十歳中自ら四時あり。」とあるように
人間は何歳に死のうが四時さえ備わっていれば悔いはないという。
松陰先生も三十歳でそれが備わったと自覚したため、これほど澄み切っているのだろう。
この文章の中で印象に残っているのは、塾生たちが最も奮い立ったと言われている最後の文章。
「若し同志の士其の微衷を憐み継紹の人あらば、乃ち後来の種子未だ絶えず、
自ら禾稼の有年に恥ぢざるなり。同志其れ是れを孝思せよ。」
自分の想いをもし同志のものが継いでくれるならば、自分の蒔いた種は絶える事はないという意。
日本人の死生観として我々が生きている現在を中今と言い、責任のある生き方をしなければならない。
現在を精一杯生きる事により、子孫に伝わっていく。
こういった考え方が日本人の根底にある。
今一度これまでの人生を振り返り、これからの生き方について考えていかなければならない。
★好きな言葉
至誠館の見学で、松陰先生の語録の中から見つけた好きな言葉。
『私は、人を信じて失敗するようなことがあっても、決して人を疑って失敗することはないようにしたい。』
★最後に
私が松陰先生から学んだ中で最も意識していきたいのは、至誠という生き方。
松陰先生が素晴らしいのはこの自分に対して誠を貫いた事だと考えている。
常に自分の私欲のためではなく、公のために考えていた。
これが出来るのは松陰先生だからこそであり、常にというのは不可能かもしれない。
しかし、もっともっと自分に厳しくし、私欲を減らしいくことは可能であると感じた。
今後、私が生きていく上で、何か選択に迫られた際は、迷わず厳しい道を選択していく。
その方が絶対に自分の成長に繋がると感じた。
From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生
 1月7日から8日までの二日間山口県の萩市で松下村塾、吉田松陰先生についていろいろ学びました。
1月7日から8日までの二日間山口県の萩市で松下村塾、吉田松陰先生についていろいろ学びました。短い生涯の間に自らの情熱を激しく燃やし、その情熱で周囲の人たちの心を揺り動かしました。
そして、門人たちの中からやがて明治維新の中心となって活躍する人物が
多く出たのことがなぜこの場所だったのかということを考えました。
この二日間の間で私は、その答えは、偶然がかなりあって出来たものだ
ということではないかと感じました。
その理由は、もともと地元民のために松下村にあった松下村塾。
そして、吉田松陰先生が養子に出され、そこで玉木文之進による教育があった。
その教育の中で彼の吉田松陰先生の人格が形成されるようになった。
また、当時の封建社会の中で身分に関して分けへだてなく受け入れるということは、
松下村塾の根底にそのような精神があったからです。
そのことが高杉晋作の奇兵隊の創設にもつながった。また、偶然は、それだけではなく、
伊藤博文も父親が出稼ぎに萩に行っていなければ松下村塾に行く事もなかった。
そして、そうなれば日本の歴史も変わっている。
今回は、それだけではなく、梅地さんや上田さんのお話もとても興味深かったものです。
それは、梅地さんは、吉田松陰先生だけではなく、その塾生についての知識も博識であり、
だれがだれに似ているということにも当てはめているという人を見る目にも驚きを受け、
その時に私は、吉田松陰先生は人を見る目があるという話を思い出し、
何か対象となる人物を調べるということはその人物のようになるのだと感じました。
From:森優太(長崎県出身、日本大学卒)JVU4期生
【平成24年12月23日(日)】 『現地歴史学in滋賀』 後藤敬一先生(滋賀ダイハツ販売株式会社 代表取締役社長)
2012/12/23
コメント (0)
【平成24年12月20日(木)】 『事業創造』 鳥越昇一郎先生(マーケティングウイング鳥越事務所 代表)
2012/12/20
コメント (0)
【平成24年12月19日(水)】 『手帳学』横前淳子先生 『DJ学』横前忠幸先生
2012/12/19
コメント (0)

































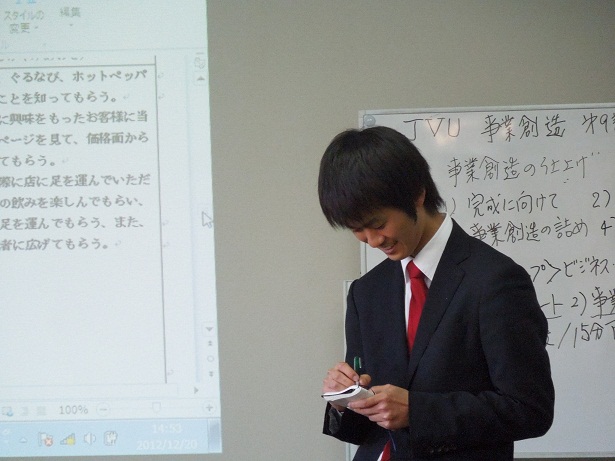





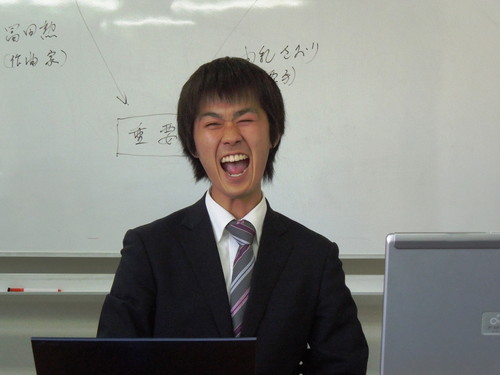


 RSS 2.0
RSS 2.0












