東京校の講義レポート
平成25年(2013)【7月25日(木)】 鹿児島・鹿屋巡業2日目
2013/07/25
コメント (0)
 --------------------------------
--------------------------------8:00 虎南先輩宅出発
8:20 湯遊センターあいら、温泉へ
8:45 あいら出発
9:00 小鹿酒造到着
小鹿酒造 営業部 企画業務課 水上真一係長の講義
工場見学
12:15 海上自衛隊鹿屋航空基地史料館
二式大挺見学
東郷平八郎肉声
零戦の見学
14:00 早田さんと合流
14:15 郷原理事長と面談
児童保育園、農園、障害者福祉
14:45 施設見学
16:00 郷原理事長とお話
19:30 早田さんと再合流
20:00 千本銀杏(垂水市)到着 クワガタ探し
21:00 江の島温泉到着
22:00 クワガタ探し
26:00 虎南先輩宅到着
--------------------------------
 ●小鹿酒造株式会社
●小鹿酒造株式会社鹿児島に酒造工場が110社ある中で
鹿屋には25社がある。
そんななかで小鹿酒造は設立当時で最下位4社が
集まってできた協業組合だった。
かつては自家製で焼酎を作っていたような地域だからこそであり
甘薯の産地だからこその産業なのだろう。
酒税のお話もしていただき
小鹿酒造さんの場合売り上げ20億のうち
酒税は7億円になるそうで
税負担は決して軽くはないそうだ。
その後工場を案内していただいたが
一番大事なのは清掃という言葉が印象に残った。
どんなに良いものを開発しても
それを継続して生産できなくては事業ではない。
その継続のための作業が何より清掃なのだと感じた。
●海上自衛隊鹿屋航空基地史料館
海上自衛隊の基地があるすぐとなりにある史料館で
航空機、魚雷など様々な展示があった。
外に世界にひとつしかないといわれる
二式大挺というものがありかなりの大きさであった。
飛行能力は当時の最高クラスだったそうだが
戦闘向きではなく物資、情報向きだそうだ。
零戦もさわることができ
軽くすることや空気抵抗を減らすことで
驚異の戦闘能力を持つことができたということが感じられた。
ただ何より感動したのは
東郷平八郎の肉声を聴くことができたということだ。
温かいような威厳があるような
うまくは説明できないが
日露戦争を勝利に導いた人の
声という生きていた印を感じることができよかった。
●郷原理事長との面談
お話を聴いていると
人と人を繋ごうとしているのを強く感じた。
玉川大学の人を紹介してくれようとしたり
電話口でベンチャー大學の名前をしきりに口にしてくださったり。
そういった中で協力者を集めているというのを
強く感じた。
また一方的に話すのではなく
学生にも話しかけて質問もしてくださり
そこからのアドバイスもしてくださった。
From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
 ●学んだこと
●学んだこと・小鹿酒造株式会社見学
小鹿酒造株式会社を見学させていただいた。
鹿屋の酒造会社のうち、鹿屋で一番規模が小さい4社が合体し、
今の小鹿酒造ができたとのことだ。
鹿屋の酒造会社で、合併しようという話が上がった中で、唯一決まったという。
個人のこだわりがあり、なかなか決まらない中でこの4社の
経営者は若い人だったということで 柔軟だったそうだ。
その小鹿酒造株式会社が大きくなっているところで、
やはり多くの挑戦ができるのは若い間だなと感じた。
まだ早いとか思わず、挑戦をどんどんしていく。
・ 海上自衛隊鹿屋航空基地史料館見学
本物の零戦に触らせていただき、説明をしていただいた。
零戦についてとても詳しく説明をしていただき、
零戦はただ軽くて早いだけではなく日本の様々な技術の
結晶であることを知った。
零戦は極限まで軽くしていて、運動能力と航続距離が抜群に
優れているという知識があり、それで知っているつもりになっていたことが恥ずかしい。
中途半端に知っていると中々再度興味を持つことはない。
今回全然知らなかったということを知る機会ができて良かった。
・郷原理事長のお話と施設見学
鹿屋の名士である郷原理事長のお話を伺い、施設を
見学させていただいた。
とにかく行動が早い方だなと言う印象を受けた。
いいと思ったことは、例え見切り発車でもされていた。
自分は行動が遅い時が多いので、もっと勢いを大事に行動していく。
施設見学は、障がい者施設や高齢者の施設などで、弱い人を
救いたいという志が実践されていた。
このような方にお会いすることができた機会で、自分の志が弱く、
チャンスを逃してしまった。
京都の極限の中で再び自分を見つめ直す。
From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
 ●酒学
●酒学小鹿酒造さんに、鹿児島の焼酎についてのお話を聞きました。
鹿児島で酒といえば芋焼酎だそうです。
鹿児島の醤油など、料理は甘くて、それには焼酎が合うといいます。
たとえば東北の料理には日本酒が合うなど、地域のお酒はその場所の
料理に合ったものができるようです。
また暖かいところでは日本酒は保存の面でも良くないという理由もあるようです。
本格焼酎とチューハイの違いなど、普段疑問に思っていながら
わからなかったことがわかり、非常に面白かったです。
試飲もさせていただきました。
芋焼酎は匂いに苦手意識がありましたが、今回は美味しく飲め、
味のあまりの違いに驚きました。
焼酎も嗜める人間になりたいです。
●日本の覚悟
海軍の航空自衛隊の史料館に行きました。
鹿屋行く上で最も重要な場所です。
外に二式大艇など、飛行機の本体が展示されていました。
実際のものを間近に見ると、その大きさなどから想像できる領域が
もの凄く広がると思いました。
中では史料館の佐藤さんにゼロ戦のお話をたくさん聞きました。
佐藤さんは細かいところまでとても熱く語っていただきました。
ゼロ戦は小回りがきき、一時世界最強と言われ、その構造も長い間
解明されなかったそうです。
機体は極限まで軽減され、それは安全性がほとんど考えられて
いなかったからだそうです。
アメリカにはその考え方は理解できないようで、それで亡くなった方を
考えると胸が痛みますが、それは見方を変えれば日本人は覚悟が
並大抵ではないと言えると思います。
そのような先人たちの心の強さは見習うべきだと思います。
●燃えている人間になる
郷原理事長という方にお会いして、勉強になるお言葉を
たくさん聞かせていただきました。
お話の中で「本物」という言葉が多く出てきました。
本物は燃えていて熱い。にせ者は金属のように冷たい。
本物には芯がある。
本物には波長がある。
などのお話がありました。
日本ベンチャー大學の人間力の教えと共通していると感じました。
狼のように荒野を駆け抜けろというお話もありました。
また、郷原理事長は小説も出していて、私が作家になりたいと
いうと、アドバイスもくださいました。
映像を浮かばせるということ。映像を描かせるために、目で
書く力を養うことが大切だそうです。
理事長は私たち一人一人と対話し、全員に誠意を込めて向き合ってくださいました。
また、私が玉川大学出身ということで、大学の小原学長のお話や、
理事長の知り合いの玉川大学出身の方と会わせていただくように
電話していただいたりしました。
鹿屋の地で私の母校の話が聞けるとは思いませんでした。
大学への気持ちもより強くなりました。
この日は理事長の運営しているたくさんの施設を見せていただきました。
最近施設の現場へは全然行っていないなと思いました。
良い経験をたくさんさせていただきました。
From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
平成25年(2013)【7月24日(水)】 鹿児島・鹿屋巡業1日目
2013/07/24
コメント (0)
 --------------------------------
--------------------------------●1日の流れ
6:00 成田空港発 ※ジェットスターで格安
8:00 鹿児島空港着
8:30 下調べ
16:00 バレルバレー訪問
18:00 鹿屋入り ※現地で聞き込み調査
19:00 クワガタ採集
23:00 後藤虎南先輩宅
※鹿屋市についてレクチャー受ける
--------------------------------
 ●バレルバレー
●バレルバレー河内源一郎という人が焼酎の父と呼ばれる人で、
河内菌というものが、今世にある焼酎の8割り使われているそうだ。
チェコの民族衣装を纏った女性の案内で見学すると
東郷平八郎なども学んだ自顕流についての展示もあった。
自顕流には薬丸流というものがあり、それは下級武士が行うもので
東郷平八郎や西郷従道が腕を磨いていたようだ。
また同じ読みで示顕流というものもあり、これは身分の高い階級の人の
演舞的な要素が強かったそうだ。
ちなみになぜ案内の女性がチェコの民族衣装を着ていたかというと、
バレルバレーではチェコの製法をそのまま取り入れた
ビール作りも行っているからだ。
焼酎、ビールと続いて、さらにソーセージや地鶏など
つまみまであったので、酒についてのトータルコーディネートのような流れが
完成されていたのが面白かった。
●後藤虎南先輩宅
初めて後藤虎南先輩@JVU一期生にお会いした。
噂は日頃から聴いていたので、お会いできて嬉しかった。
虎南先輩からは鹿屋についてと
特攻について教えていただいた。
鹿屋は大隅半島にある10万人の市で
農業、畜産、水産などの一次産業が発展した土地であり、
かつてこの地に特攻の基地があったという場所で
現在は海上自衛隊の基地がある。
知覧も有名だが、違いとしては知覧は現在は自衛隊と関わりがなく
民間による観光となった点で、鹿屋は自衛隊によって現在も
資料館が管理されており、それが鹿屋が特攻について
PRできない事情に繋がっているそうだ。
あす、その資料館に行けるので楽しみだ。
From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生
---------------------------------
 ●学んだこと
●学んだこと・バレルバレー
老舗の焼酎酒造を見学させていただいた。
そこは麹や製造で、日本全国の多くのところが真似するほどの
技術を持たれていた。
革新的な技術というものは場所を問わず産まれてくるものだなと感じた。
外的要因を原因にせず、できる方法を考える人になっていく。
また、焼酎酒造の会社ながら特徴の麹を使ったビールや、
ソーセージなどの加工製品を作られていて、長所を熟知していると
かなりの応用ができるのだなと感じた。
・後藤虎南さん宅
虎南さんの家に泊めていただいた。
その中で鹿屋についてお話をしていただいた。
知覧と鹿屋の考え方の違いをお話ししていただいた。
状況と環境の違いはあれど.特攻隊に対する思いの違いが
同じ県内でもこんなに違うのだなと驚いた。
どちらが正しいとかはないし、敵対という雰囲気でもないようだ。
知覧の考え方しか見てこなかったので鹿屋の考え方は新鮮だった。
一方からだけではなく、色々な意見に耳を傾けるようにしていく。
From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
 ●世界と歴史の焼酎
●世界と歴史の焼酎近代焼酎の父、河内源一郎さんの匠の技を受け継いだ老舗焼酎メーカー、
バレルバレーを訪問しました。
醸造所を見学させていただき、焼酎醸造を生で見ることができました。
見学していく中で、米焼酎についてのことがありました。
米焼酎は元々、お殿様などかなり上流階級の人たちが飲んでいたそうです。
お米が貴重だった昔は、庶民は飲めなかったということです。
醸造所では海外との関わりがあることもわかりました。
フィリピンの機械を取り入れたり、昔ではできなかった工夫もされているようです。
このように、歴史や世界と関わって、
バレルバレーさんの醸造所は発展していったのだと思いました。
また、河内源一郎さんがとにかくすごいとわかりました。
河内さんの発明した醸造機械を鹿児島県の
会社の80%が使っているそうです。
また、韓国の「マッコリ」というお酒は河内さんが韓国人の方と共同開発し、
韓国で広めるように作られたそうです。
すごい方の視野は制限がないなと思いました。
●鹿屋
鹿屋での研修は一期生の、後藤虎南先輩の家でお世話になります。
夜は後藤先輩に鹿屋についての講義をしていただきました。
鹿児島で人口が3番目の町、ロケットの発射が行われる町など、
たくさんの情報を教えていただきましたが、
やはり知覧と絡めたお話が最も重要だと思いました。
特攻隊についてを観光地として発展させている知覧に対して、
鹿屋は現役の自衛隊の基地があるため、それができないとのことです。
ただ、航空自衛隊の基地の中に史料館があり、
歴史の事実を伝えているということです。
私は、鹿児島が薩摩半島と大隅半島でできているということすら知りませんでした。
まだまだ知らないことばかりです。
今回の合宿でかなり勉強できるなと思いました。
From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生
-------------------------------
平成25年(2013)【7月23日(火)】 HR(京都研修最終確認)、井崎貴富先生「総経元気塾」見学
2013/07/23
コメント (0)
--------------------------------
●1日の流れ
1.京都研修最終確認
2.新聞アウトプット
3.井崎貴富先生「総経元気塾」見学
9:00 五反田本社 集合
・朝礼、掃除
床掃除。5期生と実行生で範囲を分けて競い合う
10:00 京都研修最終確認
・テーマ決め
・スケジュール確認
11:00 新聞アウトプット
・参院選ねじれ解消
・LCC 日本で定着せず
12:00 昼食、調べもの
13:00 王子駅に出発
14:30 井崎貴富先生「総経元気塾」見学
・仕事は手段であって、目的ではない。
・こちらが努力したら売れるというのはお客さんが
望んでいない限り、おかしい。
・人生とビジネスを混同してはいけない
・アイディアのないやつはアイディアなんか出すな。
成功事例をまねよ。
・真空理論の説明
・お客さんに合わせて商売を変えるべき
・いくら勉強しても、実行しなければだめ。
・伸びる会社はお客さんのことを知りつくしている。
伸びない会社は業界を知りつくしている。
・自分に合わせるのではなく、お客さんや社員に合わせる。
・不正は管理能力のなさから生まれる。
14:45 終了、山崎明様に挨拶
15:00 終礼
--------------------------------
●1日の流れ
1.京都研修最終確認
2.新聞アウトプット
3.井崎貴富先生「総経元気塾」見学
9:00 五反田本社 集合
・朝礼、掃除
床掃除。5期生と実行生で範囲を分けて競い合う
10:00 京都研修最終確認
・テーマ決め
・スケジュール確認
11:00 新聞アウトプット
・参院選ねじれ解消
・LCC 日本で定着せず
12:00 昼食、調べもの
13:00 王子駅に出発
14:30 井崎貴富先生「総経元気塾」見学
・仕事は手段であって、目的ではない。
・こちらが努力したら売れるというのはお客さんが
望んでいない限り、おかしい。
・人生とビジネスを混同してはいけない
・アイディアのないやつはアイディアなんか出すな。
成功事例をまねよ。
・真空理論の説明
・お客さんに合わせて商売を変えるべき
・いくら勉強しても、実行しなければだめ。
・伸びる会社はお客さんのことを知りつくしている。
伸びない会社は業界を知りつくしている。
・自分に合わせるのではなく、お客さんや社員に合わせる。
・不正は管理能力のなさから生まれる。
14:45 終了、山崎明様に挨拶
15:00 終礼
--------------------------------
●京都合宿レクリエーション
まだテーマが曖昧だったので
さらに詰める。
前回は文化というテーマから
千利休、わびさび、というところにたどり着いたので
今回は侘びについて調べてみた。
侘びにはもともとは、貧しい様子、
という意味があるが、
千利休のころになると
そこに簡素ながらも質が高いような意味合いが入る。
茶の心にもなっていく。
たださびについては時間が経ったものの美意識のような意味合いだったので
侘びだけに絞った方がベン大らしいと感じ
侘びにしたいと考えた。
ここまで絞ると、
侘びというキーワードから茶、
茶から千利休や古田織部などの茶人、
茶室や寺院などいきたい場所も現れてくるので
いかにテーマを絞るかが大事かよくわかった。
さらに下調べを重ねて充実した京都合宿にする。
●総経元気塾
努力しないと売れないということは
お客さんがほしいものではないという言葉が
繰り返し出てきて印象に残った。
経営者といえどもそれだけ多くの人が
独りよがりな事業を行っているのだろう。
技術や自分のつまらないこだわりで
商品を売っても何も売れない。
お客様がほしいものならなにもしなくても売れる
そういうほしいけどない、待ち望んだ商品という
真空マーケットを見つけ出すことが
大切ということだった。
今成功してない経営者が創意工夫をしたところで
もともとそれができてる人なら
とっくに成功しているはずなので
当然うまくいかないということだった。
大事なのは成功事例を学ぶこと。
特に日本の8年後が今のアメリカとのことで
アメリカは特に学ぶことが多いとのことだった。
真空マーケットの見つけかたで
地理的真空、業態の真空、品種の真空、
品目の真空、品質の真空、
などがありこの順序でビジネスを決めることが成功の秘訣になる。
参考事例をこれらに当てはめるだけで
簡単に売り上げに繋がり
あたかも簡単そうに感じた。
考え方ひとつでこれだけ変わるのだから
いかにお客様の目線でビジネスを行うのが大事かを痛感した。
From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
まだテーマが曖昧だったので
さらに詰める。
前回は文化というテーマから
千利休、わびさび、というところにたどり着いたので
今回は侘びについて調べてみた。
侘びにはもともとは、貧しい様子、
という意味があるが、
千利休のころになると
そこに簡素ながらも質が高いような意味合いが入る。
茶の心にもなっていく。
たださびについては時間が経ったものの美意識のような意味合いだったので
侘びだけに絞った方がベン大らしいと感じ
侘びにしたいと考えた。
ここまで絞ると、
侘びというキーワードから茶、
茶から千利休や古田織部などの茶人、
茶室や寺院などいきたい場所も現れてくるので
いかにテーマを絞るかが大事かよくわかった。
さらに下調べを重ねて充実した京都合宿にする。
●総経元気塾
努力しないと売れないということは
お客さんがほしいものではないという言葉が
繰り返し出てきて印象に残った。
経営者といえどもそれだけ多くの人が
独りよがりな事業を行っているのだろう。
技術や自分のつまらないこだわりで
商品を売っても何も売れない。
お客様がほしいものならなにもしなくても売れる
そういうほしいけどない、待ち望んだ商品という
真空マーケットを見つけ出すことが
大切ということだった。
今成功してない経営者が創意工夫をしたところで
もともとそれができてる人なら
とっくに成功しているはずなので
当然うまくいかないということだった。
大事なのは成功事例を学ぶこと。
特に日本の8年後が今のアメリカとのことで
アメリカは特に学ぶことが多いとのことだった。
真空マーケットの見つけかたで
地理的真空、業態の真空、品種の真空、
品目の真空、品質の真空、
などがありこの順序でビジネスを決めることが成功の秘訣になる。
参考事例をこれらに当てはめるだけで
簡単に売り上げに繋がり
あたかも簡単そうに感じた。
考え方ひとつでこれだけ変わるのだから
いかにお客様の目線でビジネスを行うのが大事かを痛感した。
From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
●学んだこと
1、新聞アウトプット
ねじれ解消についての記事と、LCCについての記事を議論した。
参院選で自民党が圧勝し、ねじれが解消した今後の
安倍政権の戦略について議論した。
今回の参院選は経済政策を押すことで勝利した。そのため
憲法議論はまだ早いのかなと感じた
さらに連立与党である共産党が憲法改正に反対している
こともあり、まだしばらく憲法改正は起こらないのかなと感じた。
経済政策が今後推し進められていくと思うが、
経済政策は私たちの暮らしに直結するものなので、これからも興味を持っていく。
LCCについての記事では、なぜピーチ以外の格安航空が
伸びなかったのかということについて議論した。
成田空港の問題もあるが、やはり日本流のサービスがネックのようだ。
従来のやり方にこだわったエアアジアとジェットスターは
伸びなかったことからも、やはり日本という市場は特殊なのだなと感じた。
2、京都研修事前講義
京都研修のチーム名とテーマを決めた。
テーマを決めたとき、それは文化ではないとのご指摘を受けた。
確かに私は宿交渉しやすいようにとテーマを決めたが、
それは文化という部分から少し外れたものであった。
一週間かけて調べるものであるので、そのような基準ではなく
もっとしっかり考える。
3、総経元気塾
武蔵野さんの教えと大分違う部分もあったが、それでも
共通しているところがあった。
それは原理原則が大事ということと、現状が第一ということだ。
井崎先生は「お客様のため」という言葉を繰り返されていた。
作り手のこだわりや業界常識より、お客様に選んでもらえるかが
大事ということだ。
何だかんだ言っても、倒産させては元も子もない。
一番大事な基本を忘れないことが大事だなと感じた。
From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
1、新聞アウトプット
ねじれ解消についての記事と、LCCについての記事を議論した。
参院選で自民党が圧勝し、ねじれが解消した今後の
安倍政権の戦略について議論した。
今回の参院選は経済政策を押すことで勝利した。そのため
憲法議論はまだ早いのかなと感じた
さらに連立与党である共産党が憲法改正に反対している
こともあり、まだしばらく憲法改正は起こらないのかなと感じた。
経済政策が今後推し進められていくと思うが、
経済政策は私たちの暮らしに直結するものなので、これからも興味を持っていく。
LCCについての記事では、なぜピーチ以外の格安航空が
伸びなかったのかということについて議論した。
成田空港の問題もあるが、やはり日本流のサービスがネックのようだ。
従来のやり方にこだわったエアアジアとジェットスターは
伸びなかったことからも、やはり日本という市場は特殊なのだなと感じた。
2、京都研修事前講義
京都研修のチーム名とテーマを決めた。
テーマを決めたとき、それは文化ではないとのご指摘を受けた。
確かに私は宿交渉しやすいようにとテーマを決めたが、
それは文化という部分から少し外れたものであった。
一週間かけて調べるものであるので、そのような基準ではなく
もっとしっかり考える。
3、総経元気塾
武蔵野さんの教えと大分違う部分もあったが、それでも
共通しているところがあった。
それは原理原則が大事ということと、現状が第一ということだ。
井崎先生は「お客様のため」という言葉を繰り返されていた。
作り手のこだわりや業界常識より、お客様に選んでもらえるかが
大事ということだ。
何だかんだ言っても、倒産させては元も子もない。
一番大事な基本を忘れないことが大事だなと感じた。
From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
●京都研修前夜
京都の最終確認ということで、テーマなどの確認をしました。
私と牛島くんのチームは全然決まっておらず、今日決めたものも
テーマとしては難しいものだった。
準備の甘さを痛感した。
京都研修の期間を有効に使えるように、早くにしっかりとしたテーマを決める。
●総経元気塾
人生とビジネスを混同してはいけない。
人生は自分本位で、自己主張と努力でどうにかなるものであるが、ビジネスは違う。
自己主張とは無関係でなければならないというのが今回の教えだ。
みんなビジネスというものの基本が全然できていない、客の立場にちっとも
立っていないということを何度もおっしゃっていた。
自分に合わせるのではなく、お客さんに合わせるのだと。
そのお考えにはとても納得した。
お客さんのことを考えなければビジネスで成功するはずがない。
そんな基本的なことでも、仕事をしている内に、人は忘れてしまうのではないか。
今回は真空理論ということで、成功したビジネスの例をいくつか学んだ。
アイディアが出ない者がアイディアを出したところで意味がない。
成功する事例を試せばいいんだ。
そのようなことをおっしゃっていた。
ビジネスとはどういうものかをまた一つ学ぶことができた。
仕事は手段であって目的ではない。
今までのベン大の講義とはまた違ったお話を聞くことができた。
From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
京都の最終確認ということで、テーマなどの確認をしました。
私と牛島くんのチームは全然決まっておらず、今日決めたものも
テーマとしては難しいものだった。
準備の甘さを痛感した。
京都研修の期間を有効に使えるように、早くにしっかりとしたテーマを決める。
●総経元気塾
人生とビジネスを混同してはいけない。
人生は自分本位で、自己主張と努力でどうにかなるものであるが、ビジネスは違う。
自己主張とは無関係でなければならないというのが今回の教えだ。
みんなビジネスというものの基本が全然できていない、客の立場にちっとも
立っていないということを何度もおっしゃっていた。
自分に合わせるのではなく、お客さんに合わせるのだと。
そのお考えにはとても納得した。
お客さんのことを考えなければビジネスで成功するはずがない。
そんな基本的なことでも、仕事をしている内に、人は忘れてしまうのではないか。
今回は真空理論ということで、成功したビジネスの例をいくつか学んだ。
アイディアが出ない者がアイディアを出したところで意味がない。
成功する事例を試せばいいんだ。
そのようなことをおっしゃっていた。
ビジネスとはどういうものかをまた一つ学ぶことができた。
仕事は手段であって目的ではない。
今までのベン大の講義とはまた違ったお話を聞くことができた。
From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
●「客の立場で考えろ」
今回のお話の本質はそこでした。
多くの企業は、自分本位で考えすぎてるから、客がこない。
自分の思いを先行させ過ぎている。
ビジネスは、自分を捨てないといけない。自分の主張なんて
出したらいけない。自分の主張を出すから難しくなる。
ビジネスは、お客にスポットライトを当てないといけない。
その為に、客の生態をしらないといけない。
例えば、アンケートで、昼食に、人は300円までなら
出せるという結果が出ているなら、300円のものを出す。
周りの店が500円で販売してるからといって500円で出すと倒産する。
他の例でいうと、回りにいっぱい和食屋さんがあるのに、
自分も和食じゃなかなか厳しい。
車で町をくまなく見回って、他の飲食店がやっていない
業態をやる。中華がなければ中華をやる。
そしたら売れる。
他にも、たくさん「お客をよぶ方法」を教えて頂きました。
パン屋さんをしていて、カレーパンだったら、カレーパンの
種類を増やす。お客が望んでいるのがカレーであれば、
そのままカレーに特化すればいい。
お客様の生態をしらないと商売なんて出来ない。
真剣にお客様の事を学ばないといけない。そこがスタート。
お客様が好きなものはなにか知る。お客様が食べているものは
なにか知る。住んでるのはどこか。お金の使い方はどういった感じなのか。
お客様の事を知り尽くしてはじめて、選ばれる店になれる。
From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生
---------------------------------------------------
今回のお話の本質はそこでした。
多くの企業は、自分本位で考えすぎてるから、客がこない。
自分の思いを先行させ過ぎている。
ビジネスは、自分を捨てないといけない。自分の主張なんて
出したらいけない。自分の主張を出すから難しくなる。
ビジネスは、お客にスポットライトを当てないといけない。
その為に、客の生態をしらないといけない。
例えば、アンケートで、昼食に、人は300円までなら
出せるという結果が出ているなら、300円のものを出す。
周りの店が500円で販売してるからといって500円で出すと倒産する。
他の例でいうと、回りにいっぱい和食屋さんがあるのに、
自分も和食じゃなかなか厳しい。
車で町をくまなく見回って、他の飲食店がやっていない
業態をやる。中華がなければ中華をやる。
そしたら売れる。
他にも、たくさん「お客をよぶ方法」を教えて頂きました。
パン屋さんをしていて、カレーパンだったら、カレーパンの
種類を増やす。お客が望んでいるのがカレーであれば、
そのままカレーに特化すればいい。
お客様の生態をしらないと商売なんて出来ない。
真剣にお客様の事を学ばないといけない。そこがスタート。
お客様が好きなものはなにか知る。お客様が食べているものは
なにか知る。住んでるのはどこか。お金の使い方はどういった感じなのか。
お客様の事を知り尽くしてはじめて、選ばれる店になれる。
From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生
---------------------------------------------------
平成25年(2013)【7月20日(土)】 船井流人間学/船井勝仁先生(船井本社 代表取締役社長)、山近義幸道場長による人間力道場
2013/07/20
コメント (0)
 --------------------------------
--------------------------------●1日の流れ
1、京都研修事前学習
2、船井勝仁先生の講義
3、人間力道場
9:00 朝礼、掃除
9:40 京都研修事前講義
注意点、準備物などレクチャー。
12:10 昼休憩
12:40 小林さんによる京都研修質問会
研修のビデオ鑑賞
13:00「船井流人間学」/船井勝仁先生(株式会社船井本社
代表取締役社長)による講義
・社会人として一番いけないことは約束を破ること
・経営者が知らなければならないこと(2つ)
・時流
・原理原則
・銀行の人がやっていることがパターン化することが多い
・経営者が一番考えていることは資金繰り
・相手の気持ちが分かっている方が仕事がやりやすい
・守破離
・一つ一つの行動で人は評価される
・偉くないのにお金持ちになることが人間力を下げる
・大きくなる会社の社長ほど講演会などでは前に座られる
・知識は説明できて一人前
・ディベートについて
・常識について
U字理論
・変性意識
・文句を言ってもなにも変わらない
・二流のアスリートは緊張すると失敗する。
一流のアスリートは練習でできないことでも本番では成功する。
・リーダーのあり方
JALの稲森和夫さんについて
・議論と寄り合いの違い
・誰よりも働く人をリーダーに
・これからは大人から既得権益を奪うことが大事
16:00 人間力道場
18:00 終了、解散
--------------------------------
 ●京都研修オリエンテーション
●京都研修オリエンテーション・京都合宿をやる意味
もともとの日本の中心である京都に行き
自分の足で歩くことで日本について体で知ることができる。
上り・下りなどの言葉の感覚も歩きながらわかるし、
今回は鹿児島、京都、広島、山口と移動するので
西日本の地理感のざっくりした部分はわかるかもしれない。
・いかに場所に行くか、人と会うか
さまざまなルールがあるが一番大事なことだろう。
京都に行ってネットに乗ってることや
本に書いてあることだけ調べても実りにならない。
行き、見て、話を聴いて体で感じて価値がある。
お金に関してもできる限り使わないからこそ
人に対して何ができるかを考え
お世話になったら感謝する以外のことはできない。
でもそれを学べるのが京都研修なのかもしれない。
・武士は食わねど高楊枝
恵んでもらうような真似をするのではなく
工夫していくことが大事になる。
先輩の話を聴いたり過去の映像を見ても
大食いに挑戦したり、川に入ったりと
挑戦をしているのも同じことだと感じる。
宿交渉のやり方も重要になってくるだろう。
●船井勝仁先生の講義
・守破離
型は守ることも大事だが、
そのあとの方を破り、離れていくことが大事になる。
しかしそれにはそれぞれ10年20年の期間がいるそうだ。
また今の時代は最初から型を破る人もいて
時代で変わってきているようだ。
やるべきことがわかっていないうちは
型を守ることが大事になるだろう。
・時流と原理原則
この講義を通してよく出た言葉だ。
時流がわからなくては会社がつぶれるとおっしゃっていた。
また半歩先のことをやるのが大事であり、
五歩先のことをやってもつぶれるとも言っていた。
いかに時流を読み取れるかは生き抜くうえで大事な
ことなのだと感じる。
・男は5時から11時まで働く。
つまり一生懸命働き、ずっと仕事のことを
考えることができることは強いということだろう。
一生懸命仕事をすることは当然のことかもしれないが
仕事以外の時間を仕事に費やせることは
一種の天才のように感じた。
それができるような仕事に就く、起こすことは
それだけ大事なことなのだと感じた。
良い会社はやはり良く働くそうだ
・日本は自律が弱い
日本は45年周期で好況不況が変わるそうだ。
富国強兵、所得倍増のように欧米をまねている
つまり他律的な時は調子がよく、
自律を目指し始めると下がっていくようだ。
しかし自律をすることは大事なことであり
それは自己主張を持つことでもある。
そのためには欧米の強い土俵で戦うのではなく
日本人の土俵で戦うことも大事だそうだ。
自分の強みをわかっていないとできないことだけに
自分について、日本人について向き合わなくてはいけない。
●人間力道場
・営業で大事なのは質問
山近社長の過去のお話から。
営業において売り込みたい気持ちから
自分から商品についての話をしてしまいがちだが
質問をしないと相手のニーズがわからない。
それを自然とできないと営業にはつながらない。
また質問をしながら自分ではなく相手を光らせることが
必要になる。
自分が輝きたいという気持ちより相手を輝かせる
気持ちがなくては、相手との良い関係が生まれにくい
のかもしれない。
・1日誰にも会わないような仕事では成長しない。
経営者の7割は営業部門からの出身であり
その人脈や交渉能力が経営能力につながる。
営業においていくのが嫌だなという気持ちは
断られたときのいやな気持であるというのはすごく納得がいった。
・量、速さ、継続力
小が大に勝つ方法というところでお話ししていただいたが
量をやり、速くやり、長くやることがそれだ。
だから暇な時間にボーっとしている人には
近づいてはいけないとまでおっしゃっていた。
空いてる時間をいかに有効活用するかで
勝てるかどうかが決まる。
From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
 ●講義の気付き
●講義の気付き1、京都研修事前講義
上司への報告の仕方について少し教えていただいた。
チェックというものは上へ行くほどザルになるそうだ。
なぜならばすでにある程度チェックしてあるものだと思うためだそうだ。
忙しく、すでにチェックしてあるものと思うのならば甘くなるのも当然。
少し上の上司に一度チェックしてもらうこと、覚えておく。
また、チェックを頼んだ場合、返信を頂けるまで追わなければならない。
そこまでしてようやく"伝わった"ことになる。
クレームはそういったちょっとした人的ミスから起こることがほとんどだという。
自分もしっかり覚えておいて活用する。
事前準備については、調べておくものや準備物についてしっかり確認する。
京都という町は特殊らしく、実際にいくことが楽しみだ。
2、船井先生の講義
船井勝仁先生にお越しいただき、講義をしていただいた。
社会人が一番してはいけないことは約束を破ることだと強調されており、
また、一つ一つの行動で人は評価されるということで、
小さな一つ一つの信頼の積み重ねこそが大事なのだなと改めて感じた。
また、一度型にはまることが大事ということも大事だと話されていた。
一度型にはまり、原理原則を学ぶことで破ってもいいラインを知り、
そこを破る。
この順序でなければただの無知な人で終わる。
基礎を全力で学ぶこと、私がまずすべきことはここだなと感じる。
常識、物事の原理原則、基本を学ぶ。
3、人間力道場
1時間程度しか聞くことができなかったが、それでも学べる点は多かった。
目立ちたがり屋な人よりも大人しめの人の方が成功しやすい。
なぜなら相手を光らせようとするから。
自分はあまり相手を光らせようと思ったことがない。
自分が目立つよりも人を目立たせていくことが、物事がうまくいく
基本なのだなと感じた。
質問をすることを意識する。
また、同じ現場に何度か行くということは目から鱗だった。
自分は同じ場所へ再度行くということはあまりしない。
一度行って満足してしまっていた。
しかし一度見ただけで理解できた気になっているのは早すぎた。
新しい場所へ行くことももちろん大事だが、
過去に行ったところへ再び行き、新たな発見をすることも大事。
改めて行くということもしていく。
From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
●京都研修について
遂にベンチャー大學屈指の名物研修が始まる。
実行生の小林さんからもお話を伺った。
私はずっとこの研修が楽しみだった。
普通に生活していたのでは恐らく一生体験しないと思うからである。
今回のレクチャーを聞いてその気持ちの高まりはさらに大きくなった。
いかに場所に行くか、見るか、聞くか、話すかが大事だという。
実際に行くという機会を最大限に生かした研修だと思った。
どれだけ少ないお金で過ごすかが大切だということで、
この研修を乗り越えて逞しい自分になれたらいいと思う。
場所が京都ということも大きい。
昔の日本の中心地を感じて、少しで多く、自分の作品づくりの
ヒントを掴んでくる。
鹿屋、回天について学べることもありがたい。
しっかり準備して臨む。
●船井流人間学
ご本人は今回の講義をベンチャー大學でしていいものかと
おっしゃっていたが、日本ベンチャー大學と相通じる
ところは多々あったと思う。
守破離のお話、今回じっくりと聞くことができて良かった。
今の時代こそ型を破ることが大切。
型をはめたら今度は破ってくる必要という言葉が心に残った。
自分の仕事の分野では最終的には離れることができるようにする。
また船井先生のお話には歴史のことも多く含まれていた。
高橋是清、二・二六事件、ルーズベルト、真珠湾攻撃など。
意欲が出る、過去から教訓を得る、未来へのヒントを得るなど、
歴史から学ぶ意義は、多くの側面があるのだなと改めて感じた。
今はベンチャー大學に所属して勉強している。
型にはまり、内部に入り込んでいるからこそ、見えるものを見る。
いずれベンチャー大學で学んだことを糧にして、私にしか
できないものを作り上げる。
From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
 ●船井勝仁先生「船井流人間学」
●船井勝仁先生「船井流人間学」【時流と原理原則に従う】
経営者に必要なことを2つ教えて頂きました。
・時流
・原理原則(いつの時代にも当てはまる事)
に従った行動をすることです。
常識や慣例に流されずに、人の道理など「原理原則」に
合った行動をすることが、経営者に必要だと教えて下さいました。
原理原則に従った行動として、例えば「型にはまる」ことです。
時間ぴったりに来る社員と、よく働かされる企業を例に教えて下さいました。
この様な企業があるそうです。その企業は取引先と時間を約束したとき、
待ち合わせを10:00としたら、社員には9:56ぴったりに到着させる
そうです。
社会のマナーとして10分前位に来た方がよいというのが常識でしょうが、
毎回9:56ぴったりに来ると印象はどうでしょうか。この社会人は
絶対に時間ぴったりに来るので、信用の証になっているそうです。
また、よく働かされる企業がブラック企業と呼ばれる事もあります。
原理原則としては、社員がよく働く会社は伸びます。しかし時流には
沿っていなく、世の中では批判を受けています。
型を破る事は大切です。時代は常に変化し、それに対応できない
企業は淘汰されてしまいます。
しかし、船井先生より、常識や時流ばかりに流されず
原理原則に従って、一度型にはまる事が大切だと学びました。
●山近義幸道場長による人間力道場
【小が大に勝る方法、質問力】
完璧な人間はいなく、誰しも欠点を持っています。
仕事や生活で"小が大に勝る方法"を、山近道場長より教えて
頂きました。3点あります。それは人より、
1、すぐ行う(スピード)
1、量をやる(回数)
1、長くやる(20代は、長くやらないと身に付かない)ことです。
山近道場長は、かつて上司に「営業もやらせて下さい」と言って、
編集部の仕事の他に営業も自ら行っていました。
当時山近道場長は、なんと朝3時に出社し、夜は長く働かず、
飲み会を重ねて人付き合い大切にし、着々と年収を上げていたそうです。
この話をお聞きし、人より極端に行う、ことも大事かもしれないと感じます。
この3つを実践すると、もっと良いことがあると山近道場長は
話して頂きました。
それは、「質問力というギフトを与えてくれる」ことです。
「もし、スカイツリーに10回行った人と初めて行った人で、
どちらが良い質問が出来るだろうか?
10回行った人はたとえスカイツリーマニアが出て来ても、
質問がどんどん湧いてくる。
一方で、初めて行った人はあたり障りのない質問しかできない」
同じ場所でも、繰り返し行ったら新しい発見がある。
その度に質問力が上がるのだと、非常に腑に落ちました。なかなか私は、
一回行った所へ行こうとしませんが、もう一度行った場所へ行き
新しい発見をしてみようと感じました。
とにかく私は社会の中で見たら、色々な面で太刀打ちない
すばらしい方が沢山います。
そのとき山近道場長の言葉を思い出そうと感じました。
山近道場長、本当にありがとうございました。
From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実行生
---------------------------------------------------
平成25年(2013)【7月19日(金)】 松蔭神社見学、世田谷事務所で企画会議、モノづくり学校見学
2013/07/19
コメント (0)
--------------------------------
●1日の流れ
9:00 松陰神社前集合
9:10 吉田松陰学
・参拝
・墓所へ挨拶
・参拝、手水の仕方の説明
・墓苑にて松陰先生の説明
・石像について勉強
帯に右手を入れた松陰先生の肖像画
10:00 朝礼&世田谷事務所会議
・今後の事業運営について会議
・オープンイベントをどうするか。
アンケート&クワガタプレゼント
クワガタ触り放題
観光ボランティア
展示会などのシェア
10:45 移動
11:00 選挙お手伝い@三軒茶屋
丸川珠代さんの街頭演説に協力しながら
赤池先生のビラを配る。
12:30 移動
12:45 モノづくり学校
各自見学。
13:30 終礼
モノづくり学校についてのアウトプット
--------------------------------
●1日の流れ
9:00 松陰神社前集合
9:10 吉田松陰学
・参拝
・墓所へ挨拶
・参拝、手水の仕方の説明
・墓苑にて松陰先生の説明
・石像について勉強
帯に右手を入れた松陰先生の肖像画
10:00 朝礼&世田谷事務所会議
・今後の事業運営について会議
・オープンイベントをどうするか。
アンケート&クワガタプレゼント
クワガタ触り放題
観光ボランティア
展示会などのシェア
10:45 移動
11:00 選挙お手伝い@三軒茶屋
丸川珠代さんの街頭演説に協力しながら
赤池先生のビラを配る。
12:30 移動
12:45 モノづくり学校
各自見学。
13:30 終礼
モノづくり学校についてのアウトプット
--------------------------------
●吉田松陰学
松陰神社において案内と説明をするように指示されたが
全然説明できなかった。
事前の勉強が全くできていなかった。
今後は行く機会が増え、
人に説明する機会も増えるので
もっとマニアックな知識と松陰神社ピンポイントの情報も
手に入れるようにする。
新しい松陰先生の像は帯に左手を入れていたが
あのような肖像画はあの松陰神社にしか
なかったとのことで作られたようだ。
自分には武士が刀を用意するときのような姿に見えたが
実際あの時の松陰先生は何を思って手を帯に入れていたのだろうか。
●世田谷事務所会議
ついに工事が完了した世田谷の事務所に入った。
とてもきれいになっていて今後の事業が楽しみになる。
今後事業をどのように展開していくかの話になったが
ほとんど意見を言うことができなかった。
こども、クワガタ、ワクワク、
高齢者、パソコンなどいろいろなキーワードがあると思うが
それをアイデアにして提案する必要がある。
思いついたら些細なこともメールでアイデアを送ろう。
●モノづくり学校
モノづくり学校は世田谷にあり廃校を再利用する形で
モノづくりに関する企業が事務所を置いている。
ただ平日だったからか閑散としている印象を受けた。
興味を引くいくつかについては
スノードームの政策やワークショップをしている企業や
パンを作っているところなど
モノづくりという枠においても個性的な印象を受けた。
今後も廃校は増えていくだろうし
それを壊すのには費用が掛かる。
ああいった形で再利用し
さらに土日などにはイベントを行うことで
地域の活性化にもつながるだろう。
学校を運営する側も
その中に事務所を置く企業も
いろんなビジネスがあるのだと感じた。
それにしても
モノづくりにスポットライトを当てたものが多いことに改めて気づく。
日本の武器はやはりモノづくりなのだと感じた。
●新聞アウトプット
・1面中国にIT部品物流網
ヤマトHDが中国に日本と同レベルのサービスの
物流網を整備する。
これにより精密部品の扱いや
配送コストの30%程度の削減、
配送の迅速化が実現する。
現状では製造業の物流の効率化の面が強いが
現段階で物流網を整備することで
消費者向けの面の配送においても
将来的にアドバンテージができるだろう。
日本との地理的な近さを利用した
配送サービスも今後一層充実するだろう。
From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
●ものづくり学校
芸術に関する会社の貸しオフィスが集まる施設を見学した。
オープンになっているが、中は会社ばかり。
不思議な空間だった。
今回直接オフィスへの訪問はできないとのことだったが、
自由大学、若者への支援、出版など、お話を聞けば
面白いところばかりかもしれないと思った。
私の知らない施設はたくさんある。
自分のためとなる場所はまだまだたくさんあるのではないかと感じた。
●新聞アウトプット
・1面 「中国にIT部品物流網」
ヤマトがまた新しい試みに出る。次は海外に出るようだ。
現段階の中国だからこそ有効なビジネスなのかもしれない。
日本での技術、ノウハウは生きるだろう。
またこの試みで築く物流網は次のものへ繋がる足がかりになるかもしれない。
From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
松陰神社において案内と説明をするように指示されたが
全然説明できなかった。
事前の勉強が全くできていなかった。
今後は行く機会が増え、
人に説明する機会も増えるので
もっとマニアックな知識と松陰神社ピンポイントの情報も
手に入れるようにする。
新しい松陰先生の像は帯に左手を入れていたが
あのような肖像画はあの松陰神社にしか
なかったとのことで作られたようだ。
自分には武士が刀を用意するときのような姿に見えたが
実際あの時の松陰先生は何を思って手を帯に入れていたのだろうか。
●世田谷事務所会議
ついに工事が完了した世田谷の事務所に入った。
とてもきれいになっていて今後の事業が楽しみになる。
今後事業をどのように展開していくかの話になったが
ほとんど意見を言うことができなかった。
こども、クワガタ、ワクワク、
高齢者、パソコンなどいろいろなキーワードがあると思うが
それをアイデアにして提案する必要がある。
思いついたら些細なこともメールでアイデアを送ろう。
●モノづくり学校
モノづくり学校は世田谷にあり廃校を再利用する形で
モノづくりに関する企業が事務所を置いている。
ただ平日だったからか閑散としている印象を受けた。
興味を引くいくつかについては
スノードームの政策やワークショップをしている企業や
パンを作っているところなど
モノづくりという枠においても個性的な印象を受けた。
今後も廃校は増えていくだろうし
それを壊すのには費用が掛かる。
ああいった形で再利用し
さらに土日などにはイベントを行うことで
地域の活性化にもつながるだろう。
学校を運営する側も
その中に事務所を置く企業も
いろんなビジネスがあるのだと感じた。
それにしても
モノづくりにスポットライトを当てたものが多いことに改めて気づく。
日本の武器はやはりモノづくりなのだと感じた。
●新聞アウトプット
・1面中国にIT部品物流網
ヤマトHDが中国に日本と同レベルのサービスの
物流網を整備する。
これにより精密部品の扱いや
配送コストの30%程度の削減、
配送の迅速化が実現する。
現状では製造業の物流の効率化の面が強いが
現段階で物流網を整備することで
消費者向けの面の配送においても
将来的にアドバンテージができるだろう。
日本との地理的な近さを利用した
配送サービスも今後一層充実するだろう。
From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
●ものづくり学校
芸術に関する会社の貸しオフィスが集まる施設を見学した。
オープンになっているが、中は会社ばかり。
不思議な空間だった。
今回直接オフィスへの訪問はできないとのことだったが、
自由大学、若者への支援、出版など、お話を聞けば
面白いところばかりかもしれないと思った。
私の知らない施設はたくさんある。
自分のためとなる場所はまだまだたくさんあるのではないかと感じた。
●新聞アウトプット
・1面 「中国にIT部品物流網」
ヤマトがまた新しい試みに出る。次は海外に出るようだ。
現段階の中国だからこそ有効なビジネスなのかもしれない。
日本での技術、ノウハウは生きるだろう。
またこの試みで築く物流網は次のものへ繋がる足がかりになるかもしれない。
From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生
--------------------------------
●集客の悩みを解消する、今の時代らしい企業の形。
モノづくり学校を見学しました。
ここは、廃校になった学校を改装して、アート関係の企業や
団体を誘致している施設です。施設に入っている企業・団体は、
一定の料金を支払い、場所を借り、カフェを行ったり、
工作体験教室、日本酒教室などを行ったりされているようです。
この学校のいいところは、1つ1つの企業・団体が固まって
活動することで、個別で活動していては来てくれないお客様も
呼べるといった効果があります。集客というのは企業に
とって大きな課題なので、それが解消できるいい仕組みだと感じました。
●人に迎合するのではなく、自立した意見を持つための新聞アウトプット
【3面 ネット選挙不完全燃焼】
ネット選挙は想像以上には盛り上がらなかったようだ。
企業が新ビジネスとして準備していたサービスも思うような
成果を得られていないようだ。
僕自身はそうは思わない。ネット選挙解禁一年目なので注目した。
ネット選挙という言葉は、僕の頭の中では物凄く記憶に残っている。
今までで一番政治に関心を持った。
From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生
---------------------------------------------------
●気付き
【経営者を案内する】
まだまだ勉強不足だと感じました。何も知らない経営者もしくは
熟知した経営者に、松陰神社の松陰先生に興味を持って
貰わなければなりません。例えば、最近作られたブロンズ像は
なぜ帯に手を掛けているのか、こういう所を知っていると
私達を見る目も変わります。私は特に世田谷の物件で事業をするに
あたり、町を案内できるレベルまで勉強が必要だと感じました。
【教室での企画会議】
まずアイデアが出なかったな、と反省しました。教室を今後
どう活用するのか、オープンに向けどう仕掛けをするのか、
現地現場に来てイメージが膨らむと思いきや、そうでは
無かった事が少し残念です。子供はの興味を引けても、
繰り返し来てくれる仕組みは工夫が必要です。イベントの
準備も急がなければならないと分かりました。
観光ボランティアなど、地域貢献色を見せた事業が核と
なってくると感じました。
【廃校を貸し出す】
いま空きスペースを、使われていない時間に誰にどう
貸せるか企業が知恵を絞っています。カラオケ屋や映画館を、
プレゼンも出来る会議の場として安く提供する取り組みも
あります。今回も廃校になった小学校を会社にシェアしたり、
講演会に貸し出しています。バブル景気で箱物を作り過ぎた
所があるとよく聞くので、それらも活用次第では貸し出し
出来るのではないでしょうか。私も教室を始めるにあたり、
アイドリングの時間を作らない工夫をしたいと考えています。
廃校は47社も会社が入っていると聞き驚きました。
自分と近い事業をやっている所の現地現場を見て話を聞く事は、大切です。
●【新聞アウトプット】
・2面 「タックスヘイブン、G20でも話題に」
まず企業は売り上げ高などの数字を、幾らでも嘘を付けるから
租税回避の実態が掴めないのだなと思いました。
新興国の何処かの国で密かにペーパー会社を作って利益を集め、
そのお金で密かに工場を建て、利益を上げてしまえば
自国にもばれない。世界中を相手にするグローバル企業なら
なおさら、例えば電話を傍受して調査しても膨大な時間がかかります。
国にとって税収は大きな財源であるだけに、私にはお金持ちの
租税回避の気持ちも分かりますが、税を収めない事は
許せない事です。新聞にもある通り、租税回避地によく
使われる代行会社の情報流出を引き出す調査が必要なのではないでしょうか。
・6面「ロシア野党指導者 有罪」
まず私はロシアのプーチンの抑圧的政治は恐ろしいなと感じました。
反政権派野党勢力のナワリニー氏が本当に木材売却の横領事件を
主導していたのか、同氏や彼の支持者の口封じの意味で事件を
捏造したかは分かりません。野党指導者が禁固5年となれば、
プーチンの主導の政治はより進むでしょう。日本でも参議院は慎重に
物事を決める意味で置いているので、捏造だとしたら野党の
口封じとしては自国を危うくする危険な事だと感じました。
From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実行生
---------------------------------------------------
モノづくり学校を見学しました。
ここは、廃校になった学校を改装して、アート関係の企業や
団体を誘致している施設です。施設に入っている企業・団体は、
一定の料金を支払い、場所を借り、カフェを行ったり、
工作体験教室、日本酒教室などを行ったりされているようです。
この学校のいいところは、1つ1つの企業・団体が固まって
活動することで、個別で活動していては来てくれないお客様も
呼べるといった効果があります。集客というのは企業に
とって大きな課題なので、それが解消できるいい仕組みだと感じました。
●人に迎合するのではなく、自立した意見を持つための新聞アウトプット
【3面 ネット選挙不完全燃焼】
ネット選挙は想像以上には盛り上がらなかったようだ。
企業が新ビジネスとして準備していたサービスも思うような
成果を得られていないようだ。
僕自身はそうは思わない。ネット選挙解禁一年目なので注目した。
ネット選挙という言葉は、僕の頭の中では物凄く記憶に残っている。
今までで一番政治に関心を持った。
From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生
---------------------------------------------------
●気付き
【経営者を案内する】
まだまだ勉強不足だと感じました。何も知らない経営者もしくは
熟知した経営者に、松陰神社の松陰先生に興味を持って
貰わなければなりません。例えば、最近作られたブロンズ像は
なぜ帯に手を掛けているのか、こういう所を知っていると
私達を見る目も変わります。私は特に世田谷の物件で事業をするに
あたり、町を案内できるレベルまで勉強が必要だと感じました。
【教室での企画会議】
まずアイデアが出なかったな、と反省しました。教室を今後
どう活用するのか、オープンに向けどう仕掛けをするのか、
現地現場に来てイメージが膨らむと思いきや、そうでは
無かった事が少し残念です。子供はの興味を引けても、
繰り返し来てくれる仕組みは工夫が必要です。イベントの
準備も急がなければならないと分かりました。
観光ボランティアなど、地域貢献色を見せた事業が核と
なってくると感じました。
【廃校を貸し出す】
いま空きスペースを、使われていない時間に誰にどう
貸せるか企業が知恵を絞っています。カラオケ屋や映画館を、
プレゼンも出来る会議の場として安く提供する取り組みも
あります。今回も廃校になった小学校を会社にシェアしたり、
講演会に貸し出しています。バブル景気で箱物を作り過ぎた
所があるとよく聞くので、それらも活用次第では貸し出し
出来るのではないでしょうか。私も教室を始めるにあたり、
アイドリングの時間を作らない工夫をしたいと考えています。
廃校は47社も会社が入っていると聞き驚きました。
自分と近い事業をやっている所の現地現場を見て話を聞く事は、大切です。
●【新聞アウトプット】
・2面 「タックスヘイブン、G20でも話題に」
まず企業は売り上げ高などの数字を、幾らでも嘘を付けるから
租税回避の実態が掴めないのだなと思いました。
新興国の何処かの国で密かにペーパー会社を作って利益を集め、
そのお金で密かに工場を建て、利益を上げてしまえば
自国にもばれない。世界中を相手にするグローバル企業なら
なおさら、例えば電話を傍受して調査しても膨大な時間がかかります。
国にとって税収は大きな財源であるだけに、私にはお金持ちの
租税回避の気持ちも分かりますが、税を収めない事は
許せない事です。新聞にもある通り、租税回避地によく
使われる代行会社の情報流出を引き出す調査が必要なのではないでしょうか。
・6面「ロシア野党指導者 有罪」
まず私はロシアのプーチンの抑圧的政治は恐ろしいなと感じました。
反政権派野党勢力のナワリニー氏が本当に木材売却の横領事件を
主導していたのか、同氏や彼の支持者の口封じの意味で事件を
捏造したかは分かりません。野党指導者が禁固5年となれば、
プーチンの主導の政治はより進むでしょう。日本でも参議院は慎重に
物事を決める意味で置いているので、捏造だとしたら野党の
口封じとしては自国を危うくする危険な事だと感じました。
From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実行生
---------------------------------------------------













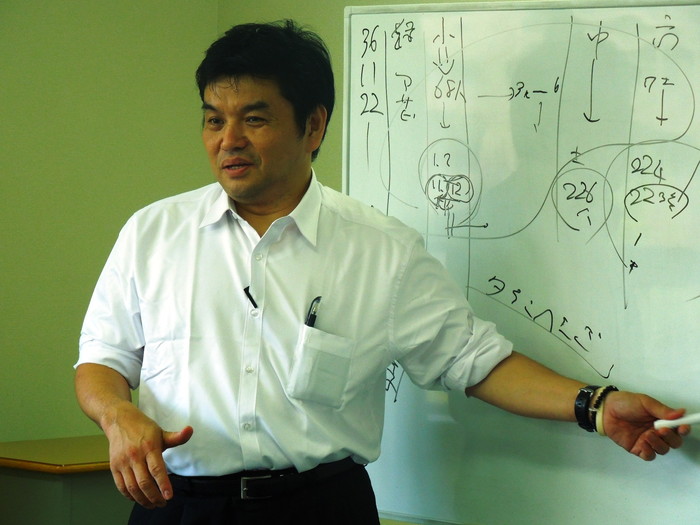
 RSS 2.0
RSS 2.0












